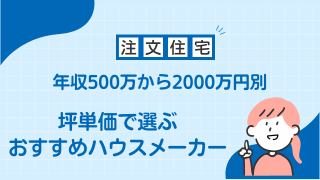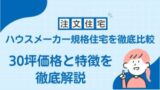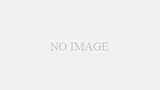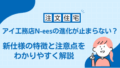家づくりって、調べ始めたばかりの頃は分からないことだらけですよね。
「年収に合ったハウスメーカーってどこ?」「坪単価って結局いくらが妥当なの?」
そんなふうにモヤモヤしている方も多いと思います。
でも大丈夫です。
年収と年齢から「無理のない予算」を割り出せば、自然と選べる坪単価やハウスメーカーの候補が見えてきます。
この記事では、年収500万円から2000万円の方を対象に、
こうしたポイントを、なるべくわかりやすくお伝えしていきます。
家づくりの第一歩として、予算とプランのイメージを整理しておきたい方は、ぜひ参考にしてください。

「私の年収だと、どこまでの家が建てられるんだろう?
- 自分の年収で建てられる家の予算がわかる
- 年齢に合わせた借入の目安がわかる
- 坪単価ごとのおすすめハウスメーカーが見えてくる
家づくり初心者でも分かる坪単価と予算の考え方

坪単価って、そもそもどう見ればいいの?
家づくりを考え始めたときに、まずぶつかるのが「どれくらいの予算で建てられるのか?」という疑問です。
でも、坪単価や建築費の見方って、正直わかりにくいですよね。
実は、住宅価格を考えるときに「坪単価」はとても重要な指標です。
しかし「建物本体の価格」だけを見て予算を立てると、あとから予想以上に費用がかかって後悔するケースも多くあります。

建物代だけで考えてたけど、他にもかかるの?
家づくりには建物以外にも次のような費用がかかります。
- 土地代(この記事では2,000万円で想定)
- 外構(庭・塀・駐車場など)
- 地盤改良・造成費用
- 設備費(照明・カーテン・エアコンなど)
- 登記・ローン関連の諸費用
- 土地仲介手数料(目安は3%+6万円)
さらに、最近では「太陽光」「蓄電池」「高断熱パック」など、性能を高めるオプションをつけると坪単価が跳ね上がることもあります。
知らずに進めると、あとで「そんなにかかるの!?」と驚く人も少なくありません。

「結局、トータルでいくら見ておけばいいの?
ひとつの目安として、この記事では「延床30坪・4人家族」のケースを例にしています。
そのうえで、現実的な総額は次の式で計算できます。
坪単価 × 1.10 × 延床坪数
+ 付帯費用(全国平均で約1,100万円)+ 土地代(2,000万円)+ 仲介手数料(約72万円)
この計算で、土地から建物・初期費用まで含めた“本当に必要な金額”を把握することができます。
建替えの場合は、土地代を差し引いて、代わりに解体費(目安で300万円)を加えましょう。
また、自己資金や親からの贈与がある方は、その分を差し引いて考えます。
年収から逆算して家づくりを始めるべき理由

気になるハウスメーカーがあるけど…私の年収で大丈夫?
家づくりは夢が膨らむ反面、どこかで「自分に本当に手が届くのか…?」という不安もありますよね。
そういう時こそ「年収から逆算する」ことが、最初にやるべきことなんです。
なぜなら、住宅ローンには年収に応じた借入の上限があるからです。
そして、それを先に知っておくことで「選べる坪単価」や「メーカーのグレード」も自然と見えてきます。

どこから逆算すればいいんですか?
年収を基準に考えるときは、まず「建物+土地+諸費用」を合計した総予算を出すことがポイントです。
この総額が「今の自分にとって無理がない範囲かどうか」を、年齢や家族構成に合わせて見ていきます。
たとえば、同じ年収800万円でも、
- 20代ならローンの返済期間が長く取れる
- 40代なら返済期間が短く、子育てや老後資金も意識する必要がある
というように、借りられる金額や選ぶべき価格帯は大きく変わります。

憧れのメーカー、無理だと諦めなくていい?
年収と年齢から逆算して予算を明確にすれば、「このメーカーのこの商品なら現実的」というラインがはっきりしてきます。
オプションの付け方や住宅性能のグレードも、予算内で調整することが可能です。
予算の上限を先に把握することで、ムダに迷ったり、あとから落ち込んだりせずにすみます。

計算って難しそうだけど…?
難しく考える必要はありません。
このあと紹介する「坪単価×延床面積+付帯費+土地代」の目安や、「年齢別の安全な借入額」を使えば、初心者の方でもすぐにイメージができます。
まずは「自分が安全に借りられる金額」=「現実的な予算」を知ること。
それが、後悔しない家づくりの第一歩になります。
「建物価格」だけじゃない 総予算に含めるべき費用一覧

本体価格だけで家は建たないって本当ですか?
はい、実は「建物の価格」だけを見て家づくりを進めてしまうと、あとから思わぬ出費に直面することが多いんです。
たとえば、広告などで「建物価格1,980万円」と見かけたとしても、実際に住める状態にするには、これ以外にも色々な費用がかかってきます。
- 土地代:この記事では2,000万円で想定しています
- 外構費:門柱、フェンス、庭、駐車場など(200万〜300万円が目安)
- 地盤改良・造成費用:土地の状態によっては数十万円〜数百万円かかる場合も
- 設備・備品費:照明、カーテン、エアコンなど生活に必要なもの
- 登記やローン手数料:登記費用、司法書士費用、保証料、火災保険料など
- 土地の仲介手数料:一般的には「3%+6万円」=約72万円
これらはすべて「建物価格とは別」にかかってくる費用です。
中でも外構や地盤改良、登記関連は、最初の見積もりに含まれていないことも多いので注意が必要です。

付帯費用ってまとめるといくらくらい?
全国的な平均では、建物本体以外の「付帯費用」はおおよそ1,100万円前後が目安です。
ただし、仕様や立地条件によっては800万円〜1,300万円と幅があります。
- 外構をおしゃれにこだわる
- 地盤改良が必要になる
- 照明やカーテンをハウスメーカーでまとめる
など、どこまでやるかによって大きく変動するため、予備費を含めて広めに見積もることが大切です。

建物価格だけで考えちゃってた…危なかった!
そうなんです。
「建物価格は抑えたのに、結局トータルで予算オーバー」になってしまう方も少なくありません。
逆に、これらの費用をあらかじめ予算に入れておけば、あとで慌てずに、自分に合ったグレードやオプションを選びやすくなります。
付帯費用と土地費を入れた「リアルな総額」の出し方

ハウスメーカーのカタログだけじゃ総額は分からないんですか?
実は、ハウスメーカーの資料や広告でよく見かける「建物価格」や「坪単価」は、本体部分だけのことがほとんど。
住める状態に仕上げるためには、それ以外にもたくさんの費用がかかってきます。
そこで重要になるのが、「リアルな総額」を最初に把握しておくことです。
坪単価 × 1.10 × 延床坪数+ 付帯費用(目安:1,100万円)+ 土地代(この記事では2,000万円)+ 仲介手数料(約72万円)

この1.10ってなんですか?
これは消費税(10%)を加味した数字です。
ハウスメーカーの価格表は税抜表示が多いため、実際にはこの1.10を掛ける必要があります。
総額シミュレーション(延床30坪・坪単価80万円の場合)
- 建物本体価格:80万円 × 1.10 × 30坪 = 2,640万円
- 付帯費用(外構・登記・設備など):1,100万円
- 土地代:2,000万円
- 仲介手数料:約72万円
合計:5,812万円
この金額が、いわゆる「すぐ住める状態まで仕上げた時の現実的な予算」になります。

「オプションをつけたらもっと高くなりますよね…?
その通りです。以下のような仕様を加えると、総額はさらに上がる可能性があります。
- 太陽光パネル
- 蓄電池・V2H設備
- 全館空調
- 高断熱グレードやトリプルサッシ
- 水まわりのグレードアップ
これらを組み合わせると、坪単価が90万円〜100万円になるケースもあります。
とくに高性能住宅やZEH仕様を検討している方は、最初からその分を見越して予算を組むことが大切です。

思ったよりも全体の金額が大きくなりそう…
はい、最初の段階でこの「リアルな総額」を知っておくことで、
・仕様の優先順位をつけやすくなる
・どこまでが無理のないラインか判断できる
・住宅ローンの事前審査にも自信が持てる
といったメリットがあります。
予算にゆとりがないと、あとからの変更やトラブルでストレスが増えることもあるので、「本体価格だけで考えない」が大前提になります。
自分の年収でどのくらい借りられるのか

気になるハウスメーカーがあるけど、うちの年収で本当に払っていけるのかな…?
こうした不安を感じるのは当然です。
でも安心してください。住宅ローンには「この年収ならここまで借りても安全」という目安があります。
この目安を知っておくと、予算オーバーになる心配を減らすことができます。
逆に、知らずに家づくりを進めてしまうと、ローン返済が苦しくなったり、生活を圧迫したりするリスクも出てきます。
借入可能額は「年収」と「年齢」で決まる
住宅ローンで借りられる金額は、単に年収だけではなく「年齢」によっても大きく変わります。
なぜなら、ローンの返済期間には上限があるからです。

何歳までにローンを完済しないといけないんですか?
一般的には、住宅ローンは65歳〜70歳までに完済するプランが多くなっています。
そのため、若い世代ほど返済期間を長く設定でき、多めに借りられる傾向があります。
年収から安全に借りられる金額の目安
以下は、年代別の「年収倍率」の安全な目安です。
ここでは、年収×○倍で借りられる上限を参考としてご紹介します。
20代:年収の8.2倍

若いうちに建てると、たくさん借りられるって聞いたけど本当?
はい、本当です。返済期間を長く取れるため、借入可能額も高くなります。
たとえば、合算年収500万円の20代ご夫婦なら、最大で約4,100万円の借入が可能とされています。
もちろん、将来の育休や転職も見据えて無理のない返済プランを立てましょう。
30代:年収の7.3倍
30代は収入が安定してくる一方で、教育費や生活コストが上がってくる時期でもあります。
そのため、安全ラインは7.3倍前後が目安とされています。
たとえば、年収700万円なら約5,110万円程度が借入の目安です。
40代:年収の5.4倍
40代は返済できる期間が短くなってくるため、借入金額も少なめに設定するのが一般的です。
たとえば、年収800万円でも、約4,320万円が上限目安になります。

でも貯金がある場合は、その分上乗せして考えていいんですよね?
そうです。自己資金があれば、ローンを減らすことができるので、希望のハウスメーカーも選びやすくなります。
また、親からの贈与(最大1,110万円まで非課税)を活用する方法もあります。
借入額の目安は「上限値」=安全圏内で考えること
この倍率は「無理なく返せる目安」として使います。
実際には、以下のような要素も加味して調整することが大切です。
- 教育費や生活費の上昇見込み
- 車のローンや他の借入状況
- 自営業・正社員・共働きなど、収入の安定度
- 今後の昇給や転職の可能性

わが家は共働きだけど、私が産休に入る予定です…
そのような場合は、収入が減る期間を踏まえて、少し控えめに借り入れるのが安心です。
夫婦合算と片働きでの差に注意

うちも世帯年収は高いけど、片方だけが稼いでるんです。
それって不利なんですか?
結論から言うと、「収入のバランスによって、実際に使えるお金の感覚は変わる」ということです。
同じ世帯年収1,000万円でも…
- 夫婦で500万円ずつの合算
- 夫(または妻)が1人で1,000万円の単独収入
では、可処分所得(手取り)に差が出る場合があります。
なぜ夫婦合算の方が“余裕”が出やすいのか?
収入が分散されることで、各人の所得税・住民税の負担が軽くなるからです。
つまり、「税金が抑えられやすい」というメリットがあります。
そのため、手元に残るお金が比較的多く、
月々のローン返済・生活費・教育費などにも“ゆとり”が生まれやすいのです。

逆に単独高年収だと何が起こるんですか?
単独で900万円〜1,000万円以上の収入がある場合、所得税・住民税の負担が大きくなり、
手取りベースでは想像より少なく感じるというケースがあります。
その結果、「家計の余力が思ったよりない…」という事態にもなりかねません。
片働きの場合の注意ポイント
もし現在が片働きの状態でも、将来的に共働き予定ならまだ良いのですが…
という場合は、今の年収をベースにかなり慎重にローンを検討した方が安心です。

年収は高いけど、子どもの教育費や車のローンもあるし…
そういった支出も忘れずにシミュレーションしましょう。
目安としては、月々の返済額が「手取り月収の25%以内」に収まると、ゆとりある家計管理がしやすくなります。
金利・借入期間にも注意
仮にフルローンで組む場合でも、住宅ローンの金利や返済期間によっても返済総額は大きく変わります。
- 金利は安全側で0.8%前後で試算
- 返済期間は35年〜最長50年も選べるが、途中で繰り上げ返済も視野に

長く借りるのってリスクじゃないんですか?
いえ、若いうちにローン期間を長めに組むことで月々の返済額を抑え、教育費や生活費に回すお金を確保できるというメリットがあります。
そのぶん、後から繰り上げ返済や資産運用でバランスを取ることも可能です。
家づくりは「今の年収」だけでなく、「これからの家計の変化」や「ライフプラン」を含めて考えることが大切です。
特に、片働きで年収が高めな場合は、可処分所得や家計への影響をきちんと試算し、無理のない予算設定を心がけましょう。
年収500万から2000万円別 坪単価で選ぶおすすめハウスメーカー

「自分の年収だと、どこのハウスメーカーが現実的なんだろう?
このセクションでは、年収帯ごとに“手の届く”坪単価と、それに合ったハウスメーカーの例を紹介します。
以下はあくまでも目安ですが、建物本体+付帯費用+土地代をすべて含んだ「総額」から逆算しています。※延床30坪・土地代2,000万円・付帯費用1,100万円・消費税込で試算
年収500万円(20代の場合)【予算目安:約4,100万円】
年収500万円(20代)で家づくりを考える場合、予算的には「コスパ重視の企画住宅」をベースに選ぶのが現実的です。
- 想定借入可能額(8.2倍):約4,100万円
- 坪単価目安:〜65万円程度
- 土地代:2,000万円(保有済みなら予算アップ可)
土地を購入する場合は、建物本体・外構・登記費などに使える予算は1,900万円前後となるため、坪単価60万円台前半〜65万円までが安全圏です。

「土地を親から譲ってもらえるなら、70万円台も狙えますよ!
- 桧家住宅「スマートワンセレクト」
- タマホーム「大安心の家」
- アイフルホームの企画住宅プラン
- ライフデザインカバヤ(ローコスト仕様)
この帯のハウスメーカーは、基本性能を確保しつつ、間取りの工夫や設備仕様でコスト調整がしやすいのが魅力です。
外構や太陽光などは後回しにして、まずは“家を建てる”ところを重視すると予算内に収まりやすくなります。
年収600〜700万円(30代~40代)【予算目安:約4,900〜5,700万円】
- 想定借入可能額(7.3倍):年収700万なら約5,110万円
- 坪単価目安:70〜80万円台
- 断熱・気密・全館空調の選択肢が拡大するゾーン
この年収帯は、住宅性能と価格のバランスが取りやすく、「どのグレードにするか」で選択肢が大きく広がります。
断熱性能の数値(UA値0.28〜0.25)も横並びになりやすいため、全館空調の有無や保証の厚さ、メンテナンス費用での差別化が重要です。

「どれも高性能だから、差がわかりづらい…迷ったら“将来のコスト”で選びましょう!
- 一条工務店「i-smart」
- クレバリーホーム「Vシリーズ」
- ウィザースホーム「2×6」
- ヤマダホームズ「ラシオダブル断熱」
- ダイワハウス「スマートデザイン」
- トヨタホーム「SINCE BiSS(シンセ・ビス)」鉄骨企画住宅
同じ坪単価帯でも、商品のパッケージ内容が異なるため、断熱の仕様・全館空調の有無・太陽光の搭載などを基準に見比べるのがおすすめです。
年収800万円(20代後半~30代)【予算目安:約5,800〜6,500万円】
- 想定借入可能額(20代:6,560万円、30代:5,840万円)
- 坪単価目安:80〜90万円台前半まで対応可能
この帯になると、太陽光・蓄電池・高断熱パッケージを組み合わせた“性能もブランドも欲しい”層に人気のグレードが狙えるようになります。

同じハウスメーカーでも、商品で坪単価が全然違うんですね…!
- セキスイハイム(木造:グランツーユーなど)
- クレバリーホーム「CXシリーズ」
- 一条工務店「グランセゾン」
- ヤマダホームズ上位仕様
- トヨタホーム「SINCE BiSS(シンセ・ビス)プレミアム」
年収900万円(30代〜40代)【予算目安:約6,570〜7,380万円】
- 夫婦合算なら非常に安定、単独高収入の場合は手取りに注意
- 坪単価目安:90〜100万円前後+α
この帯になると、上位グレードやプレミアムシリーズのハウスメーカーが現実的な選択肢になってきます。
外構や照明、カーテン、全館空調、太陽光なども最初から盛り込んだプランニングが可能です。

夫婦で450万ずつだと、手取りも安定してて選びやすいですね
- セキスイハイム「鉄骨構造」モデル
- パナソニックホームズ「カサート」
- 三井ホーム「プレミアムシリーズ」
- ミサワホーム(大空間+省エネ系)
注意点としては、仕様を“盛りすぎる”と、外構・照明・登記などの付帯費が上振れしやすいため、トータルバランスで検討しましょう。
年収1000万円超(30代〜40代)【予算目安:約7,300万〜8,200万円以上】
- 坪単価目安:100万円超えも射程圏内
- 銀行の融資条件が有利になるボーダー帯
この層では、性能と意匠性を両立した「ハイブランド系」が現実的に選べます。
若くて年収が高い場合は、金利交渉やネット銀行の通過率も高く、有利な条件でローンが組める可能性があります。

老後も快適に暮らしたいから、設備より“断熱と全館空調”を優先したいなあ
- 積水ハウス「イズ・ロイエ」
- 三井ホーム(全館空調搭載グレード)
- 住友林業「BF構法×和モダン住宅」
- パナソニックホームズ上位構造体シリーズ
ただし、40代以降になると借入倍率が下がるため、予算との兼ね合いで坪単価を抑える方向に調整する必要が出てきます。
年収1200万〜2000万円(40代〜50代)【予算目安:9,800万円〜1億円超】
- 土地+建物で1億円を超えるケースも多数
- 都市部では“建物より立地優先”の選択肢も
この帯では、「土地を活かしたプラン」や「景観に合わせた設計提案」など、設計自由度の高い注文住宅が主流になります。
また、外構・ガレージ・外装材にこだわることで、住宅としての資産性も高く維持できます。

東京だと土地だけで6,000万超え…地方ならハイグレードで建てられるのに!
- 積水ハウス「イズ・ステージ」
- 三井ホーム「グランドフレッサ」
- 住友林業プレミアムグレード
- 一条工務店「グランセゾン+フル装備」
注意点として、1億円を超えるローンは一部の金融機関で金利が上がるケースもあるため、事前審査で条件確認をすることが重要です。

まずは情報収集が大事!
タウンライフなら、ハウスメーカーがあなたオリジナルの間取りプランを「無料」で作ってくれるので、効率よく家づくりを進められるよ♪
タウンライフ注文住宅は、希望や条件に合わせて、複数のハウスメーカー・工務店から“あなただけの提案”がまとめて届くサービスです。
プロ視点の比較・要望整理・見積もりチェックが「ワンストップ」で可能なので、迷っている方や情報をまとめて整理したい方に特におすすめです。

\入力はわずか3分で完了/
最大で5社分の間取りを無料で取り寄せ可能!
まとめ
この記事では、「年収500万から2000万円別 坪単価で選ぶおすすめハウスメーカー」について解説しました。
- 家づくりの予算は「坪単価×延床面積+付帯費+土地代」で考える
- 年収と年齢から「安全に借りられる額」を逆算するのが家づくりの第一歩
- 年収帯ごとに、現実的な坪単価・おすすめハウスメーカーが変わる
- 単純な価格比較ではなく、「性能」「保証」「将来の運用コスト」まで含めて検討することが大切

この記事を読んで、なんとなくの不安が“現実的な計算”に変わりました!
「年収がこれくらいだけど、どこまでの家が建てられるのか分からない…」
そんな悩みを持つ方でも、坪単価の目安や総額の試算ができれば、自分に合ったハウスメーカーが見えてきます。
ご自身の年収、家族構成、ライフプランに合った判断軸を持てるようになれば、家づくりはもっと安心して進められるものになります。
ハウスメーカー選びを本格的に始めたい方は、まずカタログや資料を取り寄せて比較するのがおすすめです。

同じ予算でも、メーカーによって仕様が全然違うんですね…!
今のうちに複数の資料を見ておくことで、
といった判断がしやすくなります。

まずは情報収集が大事!
タウンライフなら、ハウスメーカーがあなたオリジナルの間取りプランを「無料」で作ってくれるので、効率よく家づくりを進められるよ♪
タウンライフ注文住宅は、希望や条件に合わせて、複数のハウスメーカー・工務店から“あなただけの提案”がまとめて届くサービスです。
プロ視点の比較・要望整理・見積もりチェックが「ワンストップ」で可能なので、迷っている方や情報をまとめて整理したい方に特におすすめです。

\入力はわずか3分で完了/
最大で5社分の間取りを無料で取り寄せ可能!