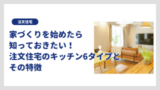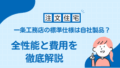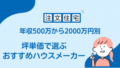注文住宅を建てるとき「せっかくだから人気の設備を入れたい」と思う方は多いですよね。けれども建築のプロの視点では「おすすめしない」と判断されるものもあります。たとえば無垢床はおしゃれで憧れる人が多いですが、手入れや費用の面から考えると時代遅れと感じられる場面もあり、ライフスタイルによっては後悔につながることもあります。
プロが避けるのには理由があります。それは「コストに見合わない」「暮らしに合わない」「施工や維持が難しい」といった現実的な事情です。見た目や流行に流されてしまうと、入居後に「思っていたのと違った」と感じるケースが少なくありません。

えっ、あんなに人気のある無垢床が時代遅れって本当なの…?
この記事では、人気があってもプロがあえて避ける住宅設備とその理由を紹介します。さらに、自分に合った設備を選ぶための考え方も解説します。
- なぜ人気の設備でも後悔する人が多いのか
- プロが避ける具体的な理由
- 自分の暮らしに合った設備を見極める方法

注文住宅は一生に一度の大きな買い物です。
しっかり情報を知ったうえで選べば、後悔のない住まいづくりに近づけますよ。
ガス床暖房は本当に必要?コストと相性をチェック

注文住宅を建てるとき、床暖房は「快適そうだから入れたい」と人気の設備です。その中でもガス温水式床暖房は高性能といわれますが、実際にはランニングコストや家の断熱性能との相性で後悔する人もいます。

友人の家で体感した床暖房がとても快適で、うちも欲しいと思っていました。
でも調べてみると、プロはあまり勧めないんですね。
このように一見理想的に思える設備でも、家の性能や暮らし方と合わなければ負担になってしまいます。そこで、光熱費の仕組みや断熱との相性、そして代替案まで整理してみましょう。
光熱費が想定以上にかかる理由
ガス式床暖房は温水を循環させるため、稼働中は常にガスを消費します。
エアコンのように一度温めれば休むわけではなく、長時間つけっぱなしになることが多いのです。その結果、冬の光熱費が大きく膨らみがちです。
さらに最近はガス料金そのものが上昇傾向にあります。最初の数年は「快適だから」と納得できても、10年20年と暮らす中で家計に重くのしかかる可能性があります。
ここで注意したいのは、ガス会社が行う導入キャンペーンです。例えば「○畳分無料」「ガス機器プレゼント」などは魅力的に見えますが、長期的に見ればガス契約が固定化され、結果的に総費用が高くなるケースも少なくありません。
床下断熱との相性問題
床暖房の効率は、住宅の断熱方式と深く関わります。
特に注意が必要なのが「床下断熱」です。
床下断熱は外気の影響を受けやすく、せっかく温めた熱が逃げやすいため、床暖房の効果が十分に発揮されにくいのです。その結果、ガスを大量に使い続けることになってしまいます。
一方で「基礎断熱」の住宅は床下空間も室内に含めるため、外気の影響を受けにくくなります。この場合、床暖房の稼働時間を短くできる可能性があり、効率面で有利に働きます。
つまり、床暖房の快適さは「断熱性能が前提」であり、断熱を整えずに設置しても十分な効果は得られません。
代替におすすめの方法
ガス温水式のデメリットを踏まえ、次のような代替手段も検討する価値があります。
- 高断熱住宅×エアコン暖房
高断熱高気密住宅ならエアコン1台でも家全体を効率的に暖められます。ランニングコストもガスに比べて安く、メンテナンスも容易です。 - ヒートポンプ式床暖房
電気の効率を最大限に活用するヒートポンプは、消費エネルギーに対する暖房効率が高く、ガスに比べて光熱費を抑えやすい方式です。特に基礎断熱の住宅と相性が良好です。 - 部分暖房の活用
どうしても足元の冷えが気になる場合は、電気カーペットやパネルヒーターなどを組み合わせる方法も有効です。必要な場所だけを暖められるため無駄がありません。
- ガス床暖房は快適だが光熱費が高額になりやすい
- 床下断熱住宅では熱が逃げやすく効率が悪い
- 基礎断熱住宅なら比較的相性が良いが、費用面では注意が必要
- エアコンやヒートポンプ式など、代替案の方が長期的には合理的
最終的に大切なのは「意匠性よりもまず躯体性能」です。断熱と気密を整えたうえで、ライフスタイルに合う暖房方式を選べば、快適さとコストのバランスを長く維持することができます。
エコカラットは見た目だけで選ぶと失敗するかも

「壁に貼るだけでおしゃれに見えるし、湿気やニオイも抑えられる」――そんな理由からエコカラットを検討する方は多いと思います。モデルハウスでもよく目にするので、つい惹かれてしまいますよね。
でも実際に建築のプロからは「性能は悪くないけど、見た目だけで選ぶと後悔することがある」と言われることもあります。

展示場で見て素敵だと思ったけど、うちの家にも本当に合うのかな…?
ここからは、エコカラットのメリットと注意点、さらに今のインテリアとの相性や代わりに検討できる素材について見ていきましょう。
実際の効果と注意点
エコカラットの魅力は「調湿」と「消臭」。玄関やトイレ、リビングの一部に使えば、湿気や生活臭をある程度和らげてくれます。
ただし気をつけたいのは「目的をはっきりさせずに採用すると満足度が低い」という点です。
「おしゃれだから」「流行っているから」と広い面積に施工すると、費用ばかりかかってしまうことも。
本当に必要な場所を見極めてポイント使いすることが大切です。

玄関にちょっと使うくらいならいいけど、全面はちょっとコスパ悪そうですね。
インテリアトレンドとの相性
エコカラットがブームになったのは2010年代。テレビの背面や玄関に貼ると「おしゃれに見える」と人気を集めました。
でも今のインテリアトレンドは少し変わってきています。
最近は「シンプルでフラットな壁」が好まれ、ホテルライクやミニマルデザインの人気も高まっています。そのため、凹凸のあるタイル仕上げが逆に古く見えてしまうケースもあるのです。

せっかく高いお金をかけたのに『ちょっと古い感じ』って言われたらショックかも…。
代わりに検討したい壁材
「機能性もデザインも両立させたい」という方には、自然素材を使った壁材もおすすめです。
たとえば、しっくいや珪藻土の塗り壁は調湿や消臭の効果を持ちながら、シンプルで上質な雰囲気を演出できます。コストは上がりますが、仕上がりの満足度は高めです。
また、予算を抑えたい方なら「部分的に塗り壁を取り入れる」「シンプルなクロスをきれいに張る」だけでも、十分に洗練された空間をつくることができます。

無理してエコカラットにしなくても、塗り壁やクロスでおしゃれにできそうですね。
- エコカラットは効果があるけれど、見た目重視で広く施工すると後悔しやすい
- 今のインテリアトレンドは「シンプルでフラットな壁面」が人気
- しっくいや珪藻土など自然素材の塗り壁も選択肢としておすすめ
「なんとなく人気だから」ではなく、自分の暮らし方や好みに合わせて選ぶことが、長く満足できる家づくりにつながります。
エネファームはコストを理解しないと危険

「家庭で発電できるから環境にやさしい」「光熱費を抑えられる」――そんなイメージでエネファームを検討する方は多いです。住宅メーカーやガス会社からも積極的に提案されるので、安心感があるように思えますよね。
けれども、実際に導入した人からは「ガス代が想定以上にかかった」「エコどころかコストが増えた」という声も少なくありません。仕組みを理解せずに導入すると、長期的に家計を圧迫してしまうリスクがあるのです。

えっ、発電できるのに光熱費が高くなるなんて想像してなかった…
ここでは、エネファームの仕組みとコストの落とし穴、そして代替の選択肢について整理します。
二重でガスを使う仕組み
エネファームはガスを燃料にして発電し、そのときに発生する熱でお湯をつくるシステムです。
仕組みだけ聞くと「無駄がなくて効率的」と思えます。
しかし実際には、
- 発電用にガスを消費する
- さらにバックアップ用の「エコジョーズ」でもガスを使う
という二重構造になっています。つまり「発電+給湯」でガスを2度使っているため、光熱費が思った以上に膨らみやすいのです。

発電してるのにガス代がかさむなんて、本末転倒な気がしますね。
導入費とランニングコストの落とし穴
エネファームは導入費が高額で、設置に80〜100万円ほどかかるケースが一般的です。しかも、光熱費削減で元を取れるかというと難しいのが現実です。
実際に利用した人の多くが「思ったよりもガス代が高かった」と感じており、販売元の担当者でさえ「元が取れる商品ではありません」と説明しているケースもありました。
つまり「長期的に節約できる」と思って導入すると、逆に支出が増えてしまう可能性が高いのです。

最新設備ならお得だと思ってたけど…逆にコストが増えるなんてショックですね。
代替の選択肢
「じゃあ何を選べばいいの?」と感じる方に、現実的な選択肢を挙げます。
- エコキュート(電気式給湯機)
夜間の安い電気を利用でき、ランニングコストを抑えやすい。多くの家庭で導入されており実績も豊富。 - エコワン(ハイブリッド型給湯機)
電気とガスを組み合わせ、状況に応じて効率の良い方を使う。省エネ性能が高く、安定した運用が可能。
これらは導入費も比較的現実的で、長期的な光熱費削減にもつながります。

最新だから安心、ではなくて実績のある機器を選ぶ方が確実そうですね。
- エネファームは「発電+給湯」で二重にガスを使う仕組み
- 導入費が高く、光熱費も下がらないどころか増えるケースもある
- 代替ならエコキュートやエコワンの方が現実的
タッチレス水栓は便利?それともストレス?

「手をかざすだけで水が出るなんて、清潔で便利そう」と思ってタッチレス水栓を検討する方は多いです。料理中や手が汚れている時には確かに便利そうですよね。
しかし実際に使ってみると「反応が鈍い」「思ったように水が出ない」といった声も少なくありません。初めは最新設備のように感じても、毎日使う中で小さな不便が積み重なり、逆にストレスになることもあるのです。

清潔で便利だと思って入れたけど、結局レバーをひねった方が早かった…
ここでは、タッチレス水栓の注意点と選び方について整理します。
反応ラグで使いにくいケース
タッチレス水栓は「手をかざしてから水が出るまでのタイムラグ」が気になる人が多い設備です。
こうしたケースは珍しくありません。毎日使うキッチンで、こうした「ちょっとした不便」が積み重なると大きな後悔につながります。
高品質モデルなら快適に使える?
一方で、すべてのタッチレス水栓が使いにくいわけではありません。
例えば海外メーカーの「デルタ」は、センサー式ではなく“どこでもタッチ”できる仕組みを採用しています。水栓の根元や先端を軽く触るだけで水が出たり止まったりするため、ラグがほとんどなく直感的に使えます。

ただし価格は10万円前後と高めで、施工が不十分だと誤作動を起こすリスクもあります。導入を検討する際は「施工業者の腕」も含めて確認しておきたいところです。

本当に便利なのはこういう高品質モデルなんですね。
標準水栓を選ぶメリット
最新設備に魅力を感じる一方で、シンプルなレバー式水栓にも大きなメリットがあります。
- 直感的に操作できるので、使い勝手に迷いがない
- 故障や不具合が少なく、メンテナンスコストも抑えられる
- 導入コストが低く、デザインや機能を幅広く選べる
つまり「特別な理由がなければ標準水栓でも十分」という考え方もできます。むしろ操作のシンプルさや確実性を重視する人にとっては、標準水栓の方が快適な暮らしにつながるでしょう。

シンプルな方が結局長く使いやすいのかもしれませんね。
- タッチレス水栓は便利に見えても反応ラグがストレスになることが多い
- 高品質モデルなら快適に使えるが、コストや施工の注意が必要
- 標準水栓はシンプルで壊れにくく、長期的には安心
パントリーは必須じゃない?造作収納で代用できる

キッチンの間取りを考えるとき、「パントリーはあった方が便利」と思う方は多いでしょう。確かに食品や日用品をまとめて収納できるスペースがあれば安心です。
ですが実際には「パントリーを作らなくても快適に暮らせる」ケースが増えています。その理由の一つが、造作収納の存在です。
ここでは、なぜパントリーが“必須ではない”と言えるのかを整理してみましょう。
既製品キッチン前提の発想
パントリーが一般的に勧められる背景には、「既製品キッチンの収納不足」があります。
既製品キッチンはある程度の収納力がありますが、細かく分けて設計されているわけではないため、どうしても入りきらない物が出てきます。そこで不足分を補うために「パントリーを作りましょう」と提案されるのです。
しかしこれはあくまで“既製品を前提にした発想”です。

確かに、既製品キッチンを選ぶならパントリーが欲しくなる気がします。
造作収納ならスッキリ解決
一方で、最初から「造作キッチン+造作収納」で設計すれば話は変わります。
- どんな物をどれだけ収納するかを打ち合わせで決められる
- 必要な位置に必要なサイズの棚や引き出しを作れる
- しまいやすい場所に収納があるため、散らかりにくい
こうした工夫ができるので、そもそもパントリーを作る必要がなくなります。実際に造作収納を導入した家庭では「キッチンがすっきり片付く」「ストレスなく使える」と満足度が高い傾向があります。

造作で作ってもらったら、自然と物が片付くんですよね。
パントリーが本当に必要なケース
もちろん「すべての家庭にパントリーは不要」とまでは言えません。生活スタイルによっては、パントリーが役立つケースもあります。
- 家族が多く、食品や日用品のストックが大量にある
- コストコやまとめ買いをよく利用する
- 保存食や飲料などを“見える形で”まとめて管理したい
こうした暮らし方をしている人にとっては、やはりパントリーがあると安心です。
つまり「パントリーは絶対に必要」というよりも、「自分たちの暮らし方に合わせて必要か判断する」が正解です。

収納は“量”ではなく“使いやすさ”で考えると失敗しませんよ。
- パントリーは既製品キッチンの収納不足を補うための発想が中心
- 造作収納を活用すれば、散らかりにくくパントリー不要になる場合も多い
- 家族構成や買い物習慣によってはパントリーが役立つケースもある
ガス乾燥機は便利だけど衣類ダメージに注意

ガス乾燥機は「一度使うと手放せない」と言われるほど人気の設備です。洗濯物が短時間でふんわり乾き、特に梅雨や冬場には重宝します。
しかし便利さの一方で「衣類の素材を選ぶ」「洋服の傷みが早い」というデメリットもあります。ここでは導入前に知っておきたいポイントを整理します。
素材によっては使えない
ガス乾燥機はナイロンやポリエステルなどの化学繊維には強い一方で、ウールやシルクといった自然素材には不向きです。
高温で乾燥させることで繊維が傷んだり縮んだりする可能性が高いからです。
おしゃれ着やお気に入りの洋服を長く着たい人にはデメリットが大きいかもしれません。

気に入っていたセーターが一度で縮んでしまいました…
子育て家庭でのメリット
一方で、子育て家庭や洗濯物の量が多い家庭にとっては非常に頼もしい存在です。
こうしたメリットから「洗濯のストレスが激減した」という声も少なくありません。時間と手間を節約できるのは大きな魅力です。
使う前に考えたいポイント
ガス乾燥機の導入は、ライフスタイルとの相性を見極めることが大切です。
導入コストやランニングコストも踏まえ、自分たちの生活スタイルに合っているか冷静に判断しましょう。

効率を取るか、洋服を大事にするか…悩みどころですね。
- ガス乾燥機は便利だが自然素材の衣類には不向き
- 子育て世帯や共働き家庭には大きなメリットがある
- 「効率」か「洋服の寿命」か、暮らしに合わせて判断することが大切
大判タイルの床は見た目重視だと後悔する?

大判タイルの床は、ホテルのような高級感を演出できることから近年人気が高まっています。グレーの石目調タイルを取り入れると一気に洗練された空間になるため、ショールームなどで心惹かれる方も多いはずです。
しかし、プロの立場から見ると「見た目だけで選ぶと後悔しやすい床材」です。理由は冷たさや硬さ、そして住宅の断熱方式との相性にあります。
冷たさと硬さの問題
タイルは石質素材のため、どうしても「冷たい」「硬い」という性質を持っています。
夏場は心地よく感じることもありますが、冬場には床からの冷えが体に伝わりやすくなり、居心地の悪さを感じる人が少なくありません。
また硬さゆえに転倒時の衝撃が大きい点もデメリットです。小さな子どもや高齢者がいる家庭では注意が必要でしょう。

効率を取るか、洋服を大事にするか…悩みどころですね。
断熱方式による違い
大判タイルの床が快適に使えるかどうかは、住宅の断熱方式に大きく左右されます。
- 基礎断熱の住宅
外気の影響を受けにくいため、タイルでも冷たさを感じにくい。 - 床下断熱の住宅
外気が床下に入り込むため、タイルの冷たさがダイレクトに伝わりやすい。
床下断熱の家で「流行っているから」という理由だけでタイルを採用すると、寒さに悩まされる可能性があります。

まずは断熱方式を確認し、性能と相性を見極めてから選ぶことが大切です。
代替しやすい床材
ホテルライクなインテリアを目指すなら、必ずしもタイルにこだわる必要はありません。
おすすめはグレー色味の挽板フローリングです。

木の質感を残しながら、タイル風の上品な雰囲気を演出できます。さらに木材なら温かみがあり、冬場も快適です。
近年は特殊加工が施された挽板も登場しており、耐久性やデザイン性に優れた商品が増えています。こうした代替床材を活用すれば、デザインと快適性を両立できます。

無理して冷たいタイルを選ばなくても、おしゃれな空間は作れるんですね。
- 大判タイルは見た目は魅力的だが、冷たさ・硬さがデメリット
- 基礎断熱ならまだしも、床下断熱では不向き
- グレーの挽板など代替床材でホテルライクな雰囲気を再現可能
吹き付け断熱は施工次第で良し悪しが大きく変わる

吹き付け断熱は、壁に発泡ウレタンなどを吹き付けて膨らませ、隙間を埋めながら断熱性能を確保する工法です。
施工性の高さからローコスト住宅を中心に採用が広がっていますが「メリットもあるが、施工次第で仕上がりの差が大きい工法」と言えます。
品質にばらつきが出やすい理由
吹き付け断熱は、膨張して隙間を埋める特性があるため、施工が多少雑でも「見た目上は隙間なく仕上がったように見える」という特徴があります。
しかし実際には、削りすぎや気泡の入り方によって性能が不安定になることもあります。
施工精度が大工の腕に左右されやすいため、「丁寧な施工をしているかどうか」で断熱性能の差が大きく出やすいのです。

見た目はきれいでも、中の品質に不安が残ると感じました。
将来の解体費も考慮すべき
吹き付け断熱は、壁材と密着して固まるため、将来のリフォームや解体時に撤去が難しくなります。
通常の断熱材よりも手間がかかり、解体費用が1.5倍〜2倍程度になるケースもあると言われています。
住宅は数十年単位で使うものです。施工時だけでなく「将来のメンテナンスや解体まで見据えて選ぶ」ことが大切です。
選ぶなら確認したいポイント
吹き付け断熱を採用する場合は、以下の点を必ずチェックしておきましょう。

安さや施工の手軽さだけで選ばず、施工品質と将来コストも含めて総合的に判断しましょう。
- 吹き付け断熱は施工次第で性能差が出やすい
- 解体時にコストがかかる点も忘れてはいけない
- 採用するなら施工精度や将来リスクを確認して判断
キッチンハウスはブランドだけで決めると失敗する

キッチンハウスは「高級でおしゃれ」というイメージから、注文住宅で人気が高いキッチンブランドのひとつです。
ただし、名前だけで判断してしまうと「思ったより作りがシンプル」「他社と比べてコストに見合わない」と感じる人もいます。
ブランド力やデザイン性は確かに魅力ですが、冷静に比較しないと失敗につながる可能性があります。
同価格帯で差が出るポイント
キッチンは見た目だけでなく、素材の質や内部の仕上げに大きな違いが表れます。
例えば同じ価格帯でも、他社製品の方が収納の種類が多かったり、引き出しの作りがしっかりしていることも少なくありません。
つまり「高い=品質も高い」とは限らず、価格に対するバリューは実際に比べてみないと分からないのです。

ショールームで比較してみたら、思った以上に差があることに驚きました。
ショールームで確認すべきこと
カタログや営業担当の説明だけでは、細かい違いは分かりません。
必ずショールームに足を運び、以下の点を確認してみましょう。
こうした部分は写真では伝わらないため、実物を体感することが重要です。
比較して初めて見える違い
「ブランドだから安心」と思って選んでしまうと、冷静な判断を見失いがちです。
一方で、他社のキッチンと比べてみると、収納力や仕様に大きな違いが見えてきます。
複数メーカーを見比べて、価格・デザイン・使い勝手のバランスを確かめることで、後悔のない選択につながります。

ブランド名ではなく、実際の“作り”を見て判断することが失敗を防ぐ一番の近道です。
- キッチンハウスはブランド力で選ばれがちだが、作りは意外とシンプルな面もある
- 同価格帯の他社製品と比較すると収納や仕上げで差が出ることがある
- ショールームで実物を確認し、複数メーカーを比較することが重要
無垢床は万能じゃない トレンドとの相性に注意

無垢床は「自然素材の温もりを感じたい」と考える人に根強い人気があります。
ただし、どんなスタイルにも合う万能な床材とは限りません。
とくに最近人気のホテルライクやグレー系インテリアを希望する場合、無垢床では理想の雰囲気を再現できないことがあります。
無垢ならではの魅力
無垢床の一番の魅力は、本物の木ならではの質感と経年変化です。
- 歩いたときの柔らかさや心地よさ
- 木の香りや自然素材ならではの安心感
- 使い込むほどに色味や風合いが深まる楽しみ
こうした特性は合板フローリングにはないもので、無垢を選ぶ人が多い理由といえるでしょう。

自然素材に包まれて暮らしたいから、やっぱり無垢床に惹かれます。
グレー系やホテルライクには合わないことも
一方で、色味の選択肢には注意が必要です。
無垢材は茶系や黄みがかった色が多く、最近流行している「グレー系」「海外ライク」な空間に合わせにくいのが実情です。
また、木目の主張が強い無垢床は、スタイリッシュで無機質なホテルライク空間では浮いてしまうこともあります。
流行を重視するなら、無垢床=万能ではないと理解しておいた方が安心です。
突板という選択肢
近年は「突板(つきいた)」と呼ばれる床材が大きく進化しています。
突板とは、表面に2〜3mmの本物の木を貼り合わせた床材のこと。
- 無垢と見分けがつかない質感
- グレーなど最新のカラーバリエーションが豊富
- 加工技術により耐水性・耐久性が向上
- 無垢よりも安定して使える
中には石の粉を練り込んだ特殊加工の突板もあり、耐久性は無垢の6倍ともいわれています。

“本物の木=無垢”という固定観念にとらわれず、突板も選択肢に入れると理想の空間づくりがしやすくなります。
- 無垢床は自然素材ならではの温もりや経年変化が魅力
- ただしグレー系やホテルライクな空間には相性が合わない場合がある
- 最新の突板はデザイン・機能性ともに進化しており、無垢の代替候補になり得る
まとめ
この記事では、注文住宅で後悔しやすい人気設備について解説しました。
- ガス温水式床暖房やエネファームはコスト面に注意
- エコカラットや大判タイルの床はトレンドや相性を要確認
- 無垢床は魅力的だが万能ではなく、突板などの選択肢も検討すべき
設備選びで大切なのは「なんとなく評判がいいから」ではなく、コスト・相性・暮らし方を基準に判断することです。これができれば、将来の後悔をぐっと減らせます。
最後に、家づくりは一度きりの大きな選択です。目先の流行や営業トークに流されず、自分や家族の生活に合った設備を選ぶことが、満足できるマイホームへの一番の近道です。

まずは情報収集が大事!
タウンライフなら、ハウスメーカーがあなたオリジナルの間取りプランを「無料」で作ってくれるので、効率よく家づくりを進められるよ♪
タウンライフ注文住宅は、希望や条件に合わせて、複数のハウスメーカー・工務店から“あなただけの提案”がまとめて届くサービスです。
プロ視点の比較・要望整理・見積もりチェックが「ワンストップ」で可能なので、迷っている方や情報をまとめて整理したい方に特におすすめです。

\入力はわずか3分で完了/
最大で5社分の間取りを無料で取り寄せ可能!