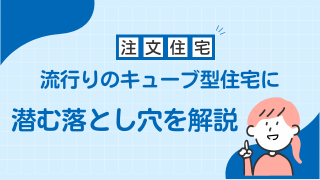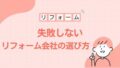おしゃれでスタイリッシュな外観が人気のキューブ型住宅。
その多くに採用されているのが、軒の出がない“軒ゼロ住宅”という構造です。
軒ゼロ住宅とは、屋根の先端(軒)が建物の外壁からほとんど張り出していない住宅のことを指します。
スッキリとした見た目と現代的な印象から、近年注目を集めています。
中でも気をつけたいのが、見た目の美しさとは裏腹に指摘される構造上のリスクや後悔の声です。
軒ゼロ住宅には確かにコストやデザイン面でのメリットがありますが、
住み始めてから「想定外の出費が続いた」「夏は暑く冬は寒い」と感じるケースも少なくありません。
この記事では、軒ゼロ住宅の実態やメリット・デメリット、後悔しないための対策について詳しく解説していきます。
- 軒ゼロ住宅とキューブ型住宅の構造的な特徴と実態
- 見落としがちなデメリットとトラブルの具体例
- 後悔しないための設計・施工・メンテナンスの対策方法
そもそも軒ゼロ住宅とキューブ型住宅とは何か
住宅のデザインを考える際、まず知っておきたいのが「軒ゼロ住宅」と「キューブ型住宅」の違いと関係性です。
この2つの言葉は似ているようで、意味や設計の観点では明確に区別する必要があります。
軒ゼロ住宅の定義と特徴

軒ゼロ住宅とは、屋根の先端である「軒(のき)」が、建物の外壁からほとんど張り出していない構造の住宅を指します。
本来、軒は雨や日差しを防ぐために外壁より大きく出すのが一般的ですが、軒ゼロ住宅ではこれを極力省略します。
軒をなくすことで、フラットでシャープな外観になり、現代的で洗練された印象を与えるのが特徴です。
また、軒の出を省略することで、屋根の面積や部材が減り、施工手間も抑えられるため、コスト面でもメリットがあります。
実際、軒ゼロ住宅の普及はもともと、ローコスト住宅の流れの中で“コストを削減する設計”として生まれた背景があります。
現在ではデザイン性が注目され広く採用されていますが、出発点が「価格重視の家づくり」であった点は押さえておくべきです。
キューブ型住宅との関係性

キューブ型住宅とは、四角い箱のようなシンプルな外観を持つ住宅のことを指します。
無駄な凹凸がなく、直線的で統一感のあるフォルムは、都市的でモダンな印象を与えます。
そして、このキューブ型住宅の多くは、構造的に「軒ゼロ住宅」に分類されます。
立方体のデザインを実現するには、軒の張り出しをなくすことがほぼ必須だからです。
つまり、軒ゼロ住宅は構造上の考え方、キューブ型住宅は見た目や形のカテゴリであり、
実際の住まいでは両者が重なるケースが非常に多いのです。
なぜ今人気なのか
軒ゼロ住宅やキューブ型住宅が人気を集める背景には、見た目の美しさと都市部の土地事情という2つの要因があります。
まず、InstagramやPinterestなどのSNSで見かける*映える住宅”としての注目が高まっています。
色合いは白や黒といったモノトーン、形状は直線的で無駄がなく、外構を含めたデザインもすっきり統一されているため、写真や動画での見栄えが良く、若い世代を中心に「おしゃれな家」として評価されています。
次に、都市部の厳しい土地制限が関係しています。
斜線制限や建ぺい率の制約がある狭小地では、軒を出すと建築面積が圧迫されてしまいます。
軒をなくせばその分居住スペースを最大限確保できるため、狭い土地でも効率的な間取りが可能になります。
ただし一方で、注意すべきなのは「なぜ従来の日本建築では必ず軒があったのか」という点です。
古くからの木造住宅では、深い軒が雨風や日差しを遮る役割を果たし、家の寿命を延ばす知恵として活用されてきました。
軒ゼロ住宅はその対極にある考え方とも言えます。
つまり、過去の住宅にほとんど例がなかったということは、それだけ慎重な判断が求められる構造だとも言えるのです。

見た目はおしゃれだけど、構造まで考えて建ててる人って少ないかも

まずは情報収集が大事!
タウンライフなら、ハウスメーカーがあなたオリジナルの間取りプランを「無料」で作ってくれるので、効率よく家づくりを進められるよ♪

\入力はわずか3分で完了/
最大で5社分の間取りを無料で取り寄せ可能!
軒ゼロ住宅のメリットとは

軒ゼロ住宅は、デザイン性の高さが注目されがちですが、実は見た目以外にもさまざまなメリットを持っています。
特に、コストや土地活用、将来のメンテナンスまで幅広い観点で合理的な住宅構造だといえます。
ここでは、軒ゼロ住宅を選ぶ際に知っておきたい主なメリットを6つに分けて解説します。
デザイン性が高く現代的な印象
軒の出がないことで建物のラインがフラットになり、シンプルで洗練された外観を実現できます。
無駄のないデザインは、白や黒などのモノトーンカラーとよく調和し、外構や植栽と合わせても美しく映えます。
近年はInstagramやPinterestなどSNSの影響もあり、「映える家」=軒ゼロ+キューブ型住宅というイメージが定着しつつあります。
建築コストを抑えられる
軒ゼロ住宅は、建材や施工の手間を減らすことで建築費を抑えることができます。
屋根の面積が小さくなるため、屋根材や防水シートの使用量も少なく済みます。
さらに、軒先部分の加工や雨樋の設置も省略でき、工期短縮や人件費削減にもつながります。
建築コストが高騰する中、初期費用を抑えたい方には大きなメリットと言えるでしょう。
狭小地でも建築面積を確保しやすい
都市部では、斜線制限や建ぺい率など、建築にかかわる法律的な制限が多いのが現実です。
軒を張り出すと、建物の端部が制限ラインに触れてしまい、思うように設計できないケースもあります。
軒ゼロであれば、外壁のラインまで建物を寄せて配置できるため、限られた土地を有効に使いやすくなります。
特に間口が狭い敷地では、居住空間を無駄なく確保できる構造として重宝されています。
凹凸が少なく掃除やメンテナンスがしやすい
軒ゼロ住宅は、外壁や屋根に凹凸が少なく、見た目がすっきりするだけでなく、メンテナンスの面でも利点があります。
軒裏のような高所の細かい部分がないため、足場の設置も効率的で、塗装や補修作業がスムーズに行えます。
長期的に見れば、メンテナンスコストを抑えやすい構造であるとも言えるでしょう。
建築面積に含まれにくく固定資産税が軽くなる可能性も
建築基準法では、軒が80cm以上張り出すと建築面積に含まれる場合があります。
軒ゼロ住宅はこの張り出しがないため、結果的に建築面積が小さくカウントされることがあります。
その分、固定資産税の算出基準となる面積が小さくなる可能性があり、税負担が軽くなるという副次的なメリットもあります。
ただし、これは地域のルールや設計条件によって異なるため、事前に確認することが大切です。
隣地境界ギリギリまで建物を寄せられる
軒が出ていないということは、外壁から隣地境界線までの距離をより詰められるということでもあります。
これにより、住宅密集地や変形地でも、敷地を最大限に活用して建てることが可能になります。
また、隣地とのトラブルを避けやすく、外構(フェンス・塀)計画もしやすくなるという実務上のメリットもあります。
軒ゼロ住宅のデメリットと起きやすいトラブル
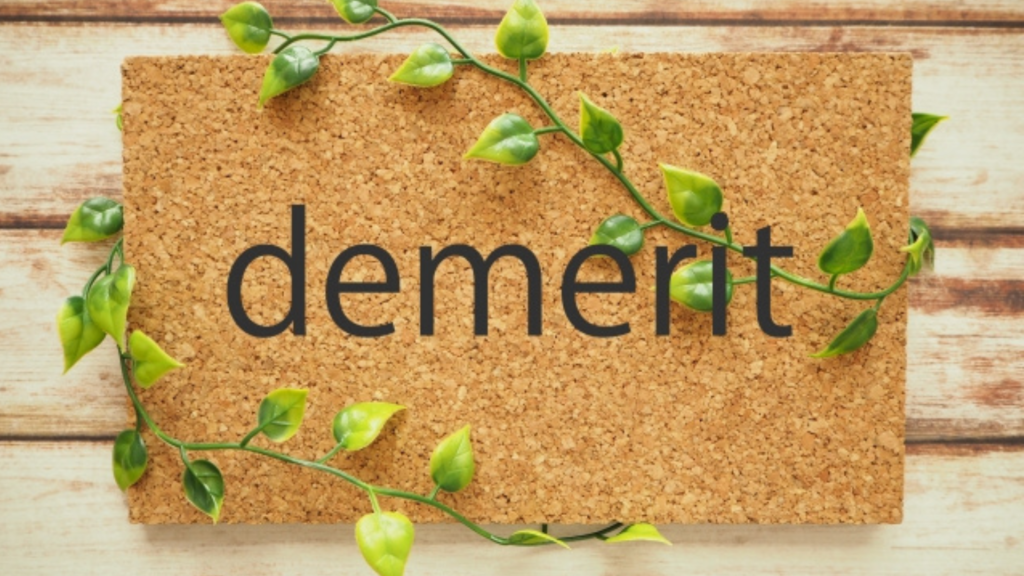
軒ゼロ住宅は、デザイン性やコスト面での魅力がある一方で、構造上の注意点や住んでからわかる不便さも存在します。
ここでは、軒ゼロ住宅に多く見られる具体的な5つのデメリットと、見落とされがちな2つのトラブル要因をあわせて紹介します。
雨漏りしやすい構造
軒ゼロ住宅は、屋根と外壁が接する「取り合い部分」から雨水が侵入しやすいという構造的な弱点を持っています。
従来の住宅は軒が張り出しており、雨の直撃を防いでくれますが、軒がないと横殴りの雨や風を伴う雨が壁に直接当たりやすくなります。
さらに、現代の住宅は通気構法を採用しているため、壁の中に意図的に通気用の穴が開いていることも多く、
施工の質が低かったり、防水処理が不十分だったりすると、そこから雨水が侵入してしまうリスクがあります。
外壁が劣化・汚れやすい
軒のない外壁は、常に雨や紫外線を直接受ける状態になります。
そのため、塗装の劣化が早まり、雨だれ汚れやチョーキング(粉ふき現象)が起こりやすくなります。
特に外壁材がサイディングの場合は、防水性能の低下が雨漏りや構造材の腐食に直結するため、
他の構造よりもメンテナンス周期が短くなりやすいことも認識しておく必要があります。
冷暖房効率が落ちやすい
軒にはもともと夏の強い日差しを遮り、冬の低い陽射しを取り込む役割(パッシブ設計)があります。
軒ゼロ住宅ではこの機能が期待できず、設計に工夫がなければ、直射日光が室内に入り込んで室温が上昇することもあります。
その結果、夏は冷房効率が下がり、電気代が想定以上にかかるケースも。
見た目はスマートでも、設計段階で日射遮蔽や断熱対策が不十分だと、快適性に大きな差が出ます。
通気・換気設計が難しくなる
軒がないと、屋根裏や壁内部に空気を逃がす「通気経路」が取りにくくなるという点も無視できません。
本来、住宅は壁の中に湿気がこもらないよう通気層を確保し、上昇した空気を軒裏や棟から排出しますが、
軒ゼロ構造では通気口の配置や通気量の確保が難しくなります。
通気が不足すると、壁内部で結露が発生し、断熱材や柱が腐食する原因になります。
特に冬場は結露リスクが高く、長期間気づかずに放置されてしまうケースもあります。
設備機器が雨ざらしで劣化しやすい
軒ゼロ住宅では、室外機・給湯器・換気フードなどの外部設備が常に雨や直射日光にさらされます。
その結果、金属部分が錆びたり、電子基板が劣化しやすくなったりして、機器の寿命が短くなる、メンテナンス費用がかさむといったトラブルにつながります。
住宅の構造だけでなく、機器類までトータルで守る工夫が必要です。
雨音・反響音が気になる場合も
もうひとつ、住んでから「意外と気になる」と言われるのが雨音の反響です。
軒がない構造では、屋根からの雨がそのまま地面やサッシの上に落ちるため、「カンカン」「ポタポタ」と音が強く響きやすくなります。
夜間や静かな環境では、睡眠の妨げになるほど音が気になるという声もあり、見た目にはわからない「感覚的ストレス」が生じることもあります。
保険や保証の対象外になる可能性もある
雨漏りの中でも、台風などの強風を伴う「吹き込み雨」は、火災保険や住宅瑕疵保険の補償対象外となることがある点にも注意が必要です。
これは、「通常の雨による劣化」と見なされないためで、突発的な事故として認定されにくい傾向があります。
トラブルが発生した後に「対象外です」と言われるケースもあるため、保険内容を事前に確認しておくことが重要です。

え…音が響いたり外壁が早く痛んだりって話も聞きますね
実際にあった後悔の声と体験談
軒ゼロ住宅はその見た目のスタイリッシュさから人気がありますが、
実際に住み始めてから「こんなはずじゃなかった…」という声が聞かれるのも事実です。
ここでは、実際の施主やユーザーが語った体験談をもとに、軒ゼロ住宅ならではの後悔やトラブル事例を紹介します。
「3年でサイディングの継ぎ目から浸水して修理費20万円」
築3年の軒ゼロ住宅で、サイディングの継ぎ目(コーキング部)から雨水が侵入し、壁内の断熱材まで濡れてしまったというトラブルが発生しました。
原因は、雨が外壁に直撃し続けることによって、コーキングが予想より早く劣化してしまったこと。
部分補修には約20万円の出費がかかりました。
「デザインに満足していたけど、施工や耐久性についてもっと深く調べておけばよかった」とのことです。
「築7年で再塗装の必要が出て想定外の出費」
外壁の塗装が想定よりも早く劣化し、築7年で再塗装が必要になった事例もあります。
特に軒ゼロ住宅は紫外線や雨に直接さらされるため、塗膜の寿命が短くなりがちです。
再塗装には約80万円がかかり、「初期コストは抑えられても、長期的には維持費が高くつくと実感した」と話されています。
「夏の日差しが強烈で冷房効率が落ちた」
南向きの大開口窓からの採光を重視した設計でしたが、軒がないことで夏の直射日光がフローリングに入り込み、室温が上昇。
エアコンの効きが悪くなり、冷房費も増えたといいます。
追加で遮熱フィルムや室内ブラインドを導入する手間と費用が発生し、「建てる前にパッシブ設計を理解しておくべきだった」との声がありました。
「外付けシェードが設置できず夏の対策が難しい」
外観を重視して軒ゼロ+フラットな壁にした結果、外付けブラインドや日よけシェードが取り付けられないという不便があったケースも。
「夏の強い日差し対策がカーテンしかなく、インテリアに影響が出てしまった」と感じたそうです。
軒や庇をあらかじめ少しでも設計に入れておけば、暮らしの快適さが変わっていたかもしれないとのことです。
「雨の日に窓が開けられず通風できない」
雨の日に自然換気をしたくても、軒がないため窓に直接雨が当たりやすく、窓が開けられないという悩みも多く聞かれました。
特に引き違い窓や縦すべり窓では、風向きによって室内に雨が吹き込みやすくなるため、実質的に「閉めっぱなし」状態になることも。
「せっかく大きな窓をつけたのに活用できず、設計時にもっと通風計画を考えればよかった」と振り返っています。
本音:「見た目に惚れて建てたけど、住んでから気づいた」
どの事例にも共通していたのは、「見た目が気に入って軒ゼロを選んだ」という点です。
SNSで見た外観写真に惹かれた、モデルハウスでおしゃれだと思ったなど、デザイン重視で判断したケースが多く見受けられました。
しかし実際には、快適性・耐久性・暮らしやすさといった視点が不足していたことを後悔する声が多く、「もっと深く調べてから決断すべきだった」というのが多くの本音です。

建ててみて初めて分かること、たくさんあるんですね…
軒ゼロ住宅に向いている人と避けた方がいい人

軒ゼロ住宅はデザイン性や都市部での建築効率の面で魅力的ですが、すべての人に最適な住まいではありません。
住まい方や住環境との相性をしっかり見極めることが、後悔しないための重要なポイントです。
ここでは、軒ゼロ住宅が「向いている人」と「避けた方がいい人」の特徴を具体的に紹介します。
軒ゼロ住宅が向いている人
都市部などの限られた敷地に建てたい人
都市部では敷地が狭く、斜線制限や建ぺい率によって建築に制約が生じやすくなります。
軒ゼロ構造にすることで、建物を境界ギリギリまで寄せられるため、室内空間を広く取ることができます。
特に間口が狭い土地では有効です。
外観デザインにこだわりたい人
軒ゼロ住宅は、四角くシンプルな外観になりやすく、キューブ型デザインやミニマルな住宅スタイルを好む方に人気です。
外観の統一感が出やすく、SNS映えや現代的な印象を求める人に適しています。
メンテナンスを計画的に行える人
軒ゼロ住宅は外壁や設備が風雨に直接さらされるため、メンテナンスの頻度がやや高くなる傾向があります。
その分、施工の品質や外装材の選定が重要になりますが、定期的な点検や補修に前向きに取り組める方であれば、十分に長く快適に暮らせます。
軒ゼロ住宅を避けた方がいい人
郊外や自然環境が厳しい地域に住む人
郊外や風雨が強い地域、積雪の多いエリアでは、軒の存在が住宅を守る大きな役割を果たします。
軒ゼロ住宅では、こうした自然環境への耐性が下がり、外壁の劣化や雨漏りのリスクが高くなる恐れがあります。
自然の光や風を活かしたい人
パッシブデザインに関心があり、太陽光や通風を活かした省エネ住宅を目指したい人には、軒のない設計はやや不利です。
特に夏の日射遮蔽や雨天時の通風が制限されやすいため、自然との調和を重視するライフスタイルとは相性が良くない可能性があります。
初期費用だけで家を選んでしまいがちな人
軒ゼロ住宅は、初期の建築費用が抑えられるというメリットがありますが、
その分、外壁やコーキングの早期劣化、設備の交換などが想定より早く発生するリスクもあります。
維持管理を含めた長期的な視点での資金計画がないと、「思ったより費用がかかった」と後悔しやすい住宅です。
雨音や湿気に敏感な人
軒がないことで、屋根からの雨音が地面や設備に直接響きやすくなることがあります。
また、外壁や窓に雨が直接当たるため、換気や通風のしづらさから湿度がこもりやすくなる傾向もあります。
こうした感覚的なストレスに敏感な方にとっては、日々の快適性に影響が出やすく、避けたほうが無難といえるでしょう。
環境配慮・長寿命志向の人にも再検討の余地あり
「100年住める家」「世代を超えて住み継ぐ家」を目指す方にとっても、軒ゼロ住宅は慎重な検討が求められます。
軒は、建物の耐久性を高め、塗装や設備を保護することで、メンテナンス周期を延ばす役割を担います。
近年は最終処分場の逼迫や建築廃材の問題もあり、環境負荷を減らす長寿命住宅が注目されています。
軒ゼロ構造が、その価値観と一致するかどうかをよく見極めることが大切です。
軒ゼロ住宅を建てる前にできるリスク対策

軒ゼロ住宅は見た目の美しさや土地活用の効率面で支持されていますが、
その構造上のリスクをしっかり理解し、設計段階で防げるトラブルを回避する工夫が必要です。
ここでは、実際に建てる前に施主ができる「具体的なリスク対策」を紹介します。
事前に準備しておくことで、後から後悔するリスクを大きく減らすことができます。
外壁材・シーリング材の選定を重視する
軒ゼロ住宅では外壁が常に雨や紫外線にさらされるため、使用する外壁材やシーリング材の性能が住まいの寿命に直結します。
【対策のポイント】
このように、外装材の性能や施工法にこだわることで、雨漏りや劣化のリスクを最小限に抑えることが可能です。
通気層と小屋裏換気の設計を確認する
軒がない構造では、壁内や屋根裏の通気・換気計画が甘いと結露や劣化が進行しやすくなります。
【確認すべき設計ポイント】
特に高断熱仕様の住宅では、湿気の逃げ道を確保しないと壁内結露が発生しやすくなります。
換気経路の設計がしっかりしているかは、施工会社と十分に確認すべきポイントです。
庇・シェード・断熱カーテンで日射遮蔽を工夫する

軒ゼロ住宅では日射遮蔽が不十分になりがちですが、小さな庇(ひさし)や外付けシェードで代用することは可能です。
【具体的な工夫例】
こうした対策によって、夏場の直射日光による室温上昇を抑え、冷房負荷を減らすことができます。
建てた後に気づいても設置が難しいケースが多いため、設計段階で計画しておくことが大切です。
建築会社に対してヒアリングすべき具体例
軒ゼロ住宅はディテールの設計が重要です。
そのため、依頼先の建築会社に対しては、漠然とした希望ではなく具体的な質問を用意しておくことが重要です。
【ヒアリングの例】
こうした質問を投げかけることで、建築会社の知識レベルや施工品質へのこだわりも見えてきます。

設計段階で防げること、結構ありますね
将来的な売却や資産価値への影響はあるのか
軒ゼロ住宅は、現代的でスタイリッシュなデザインが魅力のひとつです。
しかし、将来マイホームを手放す可能性があるなら「資産価値」という視点からも考えておく必要があります。
構造上の特徴が評価にどう影響するのか、事前に知っておくことで後悔を防ぐことができます。
軒ゼロ住宅は劣化が目立ちやすく査定に影響する
軒がない分、外壁や設備が直接風雨にさらされるため、劣化や汚れが目につきやすいのが軒ゼロ住宅の特徴です。
中古住宅市場では、築年数だけでなく見た目の状態=“印象”が評価に直結する傾向があります。
特に外壁のコーキング割れやチョーキング(白い粉が出る現象)、汚れなどがあると、「手入れが行き届いていない家」と見なされやすく、査定価格が下がる要因になります。
設備の傷みも価格評価に影響する
軒ゼロ住宅では、エアコンの室外機や給湯器などが雨ざらしになりやすいため、寿命が短くなったり、使用感が劣化として目立ちやすくなる傾向にあります。
購入検討者は、水回りや屋外設備の状態も気にするため、修理や交換の必要があるとわかれば、価格交渉につながるケースが多くなります。
雨漏りへの先入観が査定に影響するケースも
軒ゼロ住宅は、「雨漏りしやすそう」「メンテナンスが大変そう」といったイメージを持たれやすい構造です。
実際に問題が発生していなくても、購入希望者の心理的な懸念が価格評価を引き下げる要因になることがあります。
このため、目に見える劣化が少なくても、設計や施工の信頼性が問われやすい傾向があるのです。
建築会社の信頼性も資産価値に影響する
軒ゼロ住宅は、設計や施工技術によって性能差が出やすいため、「どの会社が建てたか」が売却時の評価に大きく関わってくる場合があります。
特に地元密着型の工務店や、軒ゼロ住宅の施工実績が多く信頼されている会社であれば、買い手の安心感が高まり、物件の価値も維持しやすくなる傾向があります。
対策されていない家は「短寿命住宅」と見なされるリスク
もし防水処理や通気設計、日射対策が不十分なまま建てられている場合、査定時に「これは長く住めない家=短寿命住宅」と判断される可能性も否定できません。
特に中古市場では、以下のような点がチェックされます。
設計・施工段階での工夫と、維持管理記録の有無が資産価値を大きく左右します。
長期視点で「資産になる家づくり」を意識することが重要
将来的な住み替えや相続、売却を見据えるなら、以下のような工夫が価値を守るポイントとなります。
これらを丁寧に実行することで、軒ゼロ住宅であっても評価を落とすことなく、資産としての価値を保ちやすくなります。
住宅寿命と環境への影響も考慮すべき理由
家づくりでは、目先のデザインや初期費用だけでなく「この家は何年住めるのか」という視点も重要です。
軒ゼロ住宅に限らず、構造と維持管理次第で住宅の寿命は大きく変わります。
加えて、住宅が短命になればなるほど、社会や環境への負荷も増えていくという現実があります。
日本の住宅は平均30年で建て替えられている
国土交通省の資料によると、日本では住宅の平均的な建て替え時期が約30年前後であることが示されています。
例えば、『住宅の資産価値に関する研究(国交省)』では、実際に取り壊された住宅の平均築年数が「約31年」と明記されています。
これは、アメリカ(約55年)やイギリス(約80年)と比較しても非常に短く、日本の住宅が“長く使う”という設計思想に乏しい傾向があることを示しています。
軒ゼロ住宅では20年以内に建て替えも起こりうる
軒ゼロ住宅は、屋根や外壁が直接雨や紫外線にさらされるため、防水性能や通気構造が不十分だと、20年を待たずに構造的な問題が生じるケースもあります。
実際に、「築3年で外壁の継ぎ目から浸水」「築7年で再塗装が必要になった」といった体験談があり、
早期から修繕費がかかりはじめ、トータルで高コストになる可能性も指摘されています。
短寿命住宅は環境負荷を高める原因にもなる
住宅を短期間で建て替えるということは、それだけ多くの建築資材・廃材を消費・排出することになります。
実際、日本の最終処分場(ごみの埋立地)は、現行のペースではあと20年ほどで容量を使い切る見通しとされています。
こうした背景からも、一つの家を長く大切に使うことは、環境問題への重要なアプローチでもあるのです。
「100年住宅」は理想論ではなく、すでに実現されている
最近では、「100年住める家」を目指して設計・施工を行う住宅会社も増えています。
実際に、通気層・断熱・防水・換気計画をしっかり行い、定期的なメンテナンスを施すことで、軒ゼロ住宅でも長寿命化は十分に実現可能です。
長く快適に住むためには、次のような工夫が欠かせません。

長く住める家って、子どもたちへの贈り物でもありますよね
後悔しない軒ゼロ住宅にするための3つのポイント

軒ゼロ住宅は、スタイリッシュな見た目や都市部での敷地活用という点で人気が高まっています。
しかし、安易にデザインだけで選んでしまうと、数年後に思わぬ修繕費や住みにくさに直面することもあります。
ここでは、後悔を避けながら快適で長持ちする軒ゼロ住宅を建てるために押さえておきたい3つのポイントを紹介します。
「見た目重視」だけでなく暮らしやすさとメンテ性を天秤にかける
軒ゼロ住宅を選ぶ理由の多くは、「おしゃれでモダンだから」。
しかし、建てた後に「外壁の汚れが目立つ」「冷暖房効率が悪い」など、実際の住み心地や維持のしやすさで不満を感じるケースも少なくありません。
「見た目」だけでなく、雨風の影響や日射遮蔽なども含めた“暮らしやすさ”や“メンテナンス性”とのバランスをしっかり検討しましょう。
設計段階での通気・遮熱・防水の仕組み確認
軒がない分、建物の防水や通気構造は非常に重要になります。
設計段階で「通気層の取り方」「小屋裏換気の経路」「防水シートの重ね方」「日射遮蔽の有無」などを、図面や模型を用いて丁寧に確認しておくことが欠かせません。
設計士や建築会社には、具体的に次のような質問をしてみてください。
さらに、10年・20年後にかかる可能性のある外壁や屋根のメンテナンス費用も、概算で聞いておくと後々の備えになります。
信頼できる設計士・施工会社と相談してリスクを共有する
軒ゼロ住宅は構造的な注意点が多いため、経験豊富で誠実に対応してくれる設計士や施工会社の存在が不可欠です。
「デザイン重視で流行っていますよ」と軽く勧めてくるだけではなく、通気・雨漏り・断熱性能などの具体的なリスクについてもきちんと説明してくれるかを見極めましょう。
また、雨漏りや結露に対する保証制度、火災保険でカバーできる内容なども、建築前に確認しておくと安心です。

設計段階で防げること、結構ありますね

まずは情報収集が大事!
タウンライフなら、ハウスメーカーがあなたオリジナルの間取りプランを「無料」で作ってくれるので、効率よく家づくりを進められるよ♪

\入力はわずか3分で完了/
最大で5社分の間取りを無料で取り寄せ可能!
まとめ 軒ゼロ住宅の実態を理解して賢く選ぼう
軒ゼロ住宅は、現代的でスタイリッシュな外観や建築コストを抑えやすい点など、多くの魅力があります。
一方で、構造や住環境の観点では注意点も多く、見た目だけで判断してしまうと後悔につながる可能性も否定できません。
そこで重要なのが、事前にリスクを理解し、設計段階からしっかりと対策を講じておくことです。以下のポイントを押さえておくことで、軒ゼロ住宅でも後悔のない快適な住まいづくりが実現できます。
事前にしっかりと情報を集め、設計者・施工会社と丁寧に打ち合わせを行えば、
軒ゼロ住宅でも美しさと機能性を両立させた住まいは十分に可能です。
「知らなかった」では済まされない時代だからこそ、正しい知識と判断力を持って、後悔のない家づくりを進めましょう。

まずは情報収集が大事!
タウンライフなら、ハウスメーカーがあなたオリジナルの間取りプランを「無料」で作ってくれるので、効率よく家づくりを進められるよ♪

\入力はわずか3分で完了/
最大で5社分の間取りを無料で取り寄せ可能!