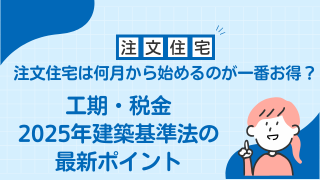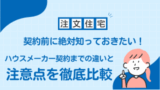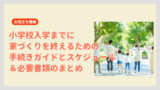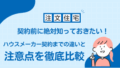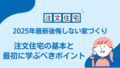注文住宅って、どの月から始めると一番お得なのか、やっぱり気になりますよね。
家づくりはそう何度も経験することじゃないですし、「どうせなら損をせずに進めたい」と思う方も多いはずです。
でも、税金や補助金、工期のこと、それに最近は法律まで変わるなんて話もあって、考えれば考えるほど迷ってしまう…というのが本音ではないでしょうか。
結論から言うと、「秋(10月ごろ)に家づくりを始めて、翌年の秋に引き渡しを受ける」のが、税金・補助金・工期など全体で見てお得になる可能性が高いです。
この時期を選ぶことで、固定資産税や住宅ローン控除、各種補助金、引越し費用までトータルでメリットを受けやすくなります。

家づくりって、結局いつから始めるのが一番得なんだろう?
税金や補助金のことも気になるし、最近は法律も変わるって聞くから余計に迷いますよね。
この記事では、注文住宅を始めるベストな時期や、税金・補助金・工期のこと、そして2025年の建築基準法改正の影響など、これから家づくりを考えている方が気になるポイントをわかりやすくまとめました。
「家づくりって結局いつから始めればいいの?」と迷っている方は、ぜひ最後まで参考にしてみてください。
- 注文住宅は何月から始めるのが一番お得なのか
- 税金や補助金、工期・引越し費用のポイントと注意点
- 2025年建築基準法改正による影響と最新情報
注文住宅は何月から始めるとお得?税金・補助金・引越し費用のトータルで考える
家づくりのタイミングは「なんとなく」ではなく、税金やお金の動き、スケジュールをしっかり押さえて選ぶことで大きな差が生まれます。ここでは、特に注意しておきたい4つのポイントから、損をしないための“ベストな時期”を詳しく解説します。

結局、いつから家づくりを始めたら“損しない”の?
タイミングを間違えると、思わぬ出費や損が出てしまうって聞いたことがあるし…。
固定資産税(建物・土地)のベストタイミング
注文住宅の最大の“落とし穴”がこの固定資産税です。
毎年1月1日時点で家や土地を持っている人に課税されるため、12月末に引き渡しだと、すぐ税金の請求が来るのがポイント。
【実例】例えば建物評価額が2,000万円の場合、都市部だと年間でおよそ28万円前後の固定資産税がかかるケースもあります。
一方、1月2日以降に引き渡しを受ければ、その年の税金はかからず、最大で1年分が浮く計算です。
家計に与えるインパクトは大きく、「引き渡し日だけで数十万円違う」ということも。
また、土地には「小規模住宅用地の特例」があり、1月1日時点で建物が建っている場合、土地の税額が1/6になることも。
都市部など土地が高い場合、この特例の有無で納税額が10万円単位で変わることもあるので、自分の土地の評価額を確認して、どちらが得か必ず試算しましょう。

引き渡しのタイミングによって、同じ家でも税金額がまったく違ってきます。
契約前に営業担当や税理士さんに“うちの場合はどちらが得か”必ず相談してみてください。
住宅ローン控除を最大化する月
住宅ローン控除は「年末のローン残高×0.7%」が13年にわたり所得税から差し引かれる制度。
例えば3,000万円借りていて年末残高が2,900万円なら、初年度だけで約20万円以上が戻ってくる計算です。
ここで大事なのは、「年末時点で残高が多いほど控除額も多い」ということ。
12月に引き渡しを受ければ、まだほとんど返済していない=残高も多い=控除も最大化。
逆に1月や2月の引き渡しだと、最初の年末までに毎月返済分が差し引かれ、控除対象の残高がその分だけ減ってしまいます。
【ポイント】住宅ローン控除の条件や上限は年度によって変更されることがあるため、家づくりを始める際は必ず“今の制度内容”をチェック。住宅会社や金融機関で最新情報を確認することも忘れずに。

ローン控除は“年末残高”がカギです。
もし引き渡しが年明けになりそうなら、できるだけ早めに金融機関や住宅会社に“控除額のシミュレーション”を頼んでおくと安心ですよ。
補助金・支援金の“申請時期”に要注意
「子育てグリーン住宅支援事業」や「省エネ住宅補助金」など、最近はさまざまな支援制度がありますが、どれも申請のタイミングに注意が必要です。
たとえば「着工日が○月末まで」「予算上限に達した時点で受付終了」など、タイミングを逃すと数十万円分の補助が受けられません。
2023年度の省エネ補助金では、実際に5月ごろに予算がなくなり締め切られたというケースも。
【体験談】知り合いは、住宅会社との打ち合わせが長引いて着工が遅れた結果、希望していた補助金の申請ができず、30万円ほど“取り損ねた”経験があります。
補助金を確実に受けるなら、「いつから工事を始めれば間に合うのか」を契約前にハウスメーカーへしっかり確認。
国土交通省や各自治体の公式サイトで最新の情報を必ず確認しましょう。

補助金の予算は“早いもの勝ち”がほとんど。
気になる制度があれば、早めにハウスメーカーや行政窓口へ問い合わせて、申請のスケジュールを逆算しておくと安心です。
引越し費用が高くなる時期・安くなる時期
引越し費用も、見落としがちな“損益ポイント”です。
大手引越し会社の調査によると、3月~4月は通常期の2倍以上の料金になることも珍しくありません。
一方、10月~12月は閑散期で費用が安く、希望の日程も取りやすい傾向があります。
【数字例】見積もりを取ったところ、3月は15万円、10月は同条件で9万円ということも。
また、引越し先の入居日を焦って決めてしまい「高い時期に当たってしまった」という声も多いです。
家づくりのスケジュールを決める時は、「引越しのピーク時期を避ける」こともぜひ意識してみてください。

引越しの日程は“工事の遅れ”や“急な天候不良”でずれ込むことも多いので、余裕を持ったスケジューリングがおすすめです。
引越し会社の仮予約や早期割引も活用しましょう。
- 【固定資産税】1月2日以降の引き渡しで1年分浮くことも
- 【住宅ローン控除】年末引き渡しが最大化のコツ
- 【補助金】着工タイミング・予算枠は“最新情報を必ず確認”
- 【引越し費用】閑散期(10~12月)が狙い目
2025年建築基準法改正で何が変わる?家づくりの注意点
2025年から建築基準法が大きく変わることで、これから注文住宅を検討する方にもいろいろな影響が出てきます。
「何が変わるのか?」「自分たちの家づくりにどう関係するのか?」
このパートでは、気になるポイントを分かりやすく整理してご紹介します。

来年から建築基準法が変わるって本当?うちも関係あるの?
法律って難しそうだけど、これから家づくりする人にとって何が変わるのかは、やっぱり気になりますよね。
4号特例の廃止・耐震基準の強化ポイント
2025年の建築基準法改正で最も大きなポイントは、「4号特例」の見直しです。
これまで木造2階建て以下の注文住宅(4号建築物)は、構造や防火など一部の審査が省略されていました。
つまり、「建築士が設計していれば、詳細な構造チェックは不要」という特例があったのです。
しかし2025年以降、この特例が大幅に廃止・縮小されます。
具体的には、2階建て木造住宅の多くが「新2号建築物」となり、今までよりも厳しい構造審査や耐震性の確認が必要になります。
特に、壁の配置や量を確認する「壁量計算」の提出が義務化されるなど、耐震基準が一段と厳しくなります。

これまで“見逃されていた”耐震性のチェックがしっかりされるようになるので、2025年以降に家を建てる人にとっては“安全性アップ”という意味ではメリットも大きいです。
ただし、審査が増える分、設計や工事のスケジュールには余裕を持っておきましょう。
建築基準法改正で工期が伸びる
今回の法改正により、注文住宅の工期が今までより長くなるケースも予想されています。
なぜなら、これまでは省略されていた“構造や耐震性に関する審査”がしっかり行われるようになるからです。
これまでは設計から着工までスムーズに進んでいた部分も、2025年からは申請や審査にかかる期間が増えたり、設計内容の追加チェックが必要になったりします。
結果として「思ったより着工が遅れる」「完成までの期間が数週間~1ヶ月ほど長くなる」といった声が出てくる可能性があります。
特に年度末や繁忙期には、審査機関が混み合ってさらに時間がかかることも。
希望のタイミングで引き渡しを受けたい場合は、いつも以上に早めの計画・打ち合わせがおすすめです。

これから家づくりを考えている方は、“今までより余裕を持ったスケジュール”で動くのがコツです。
工事の着工時期だけでなく、申請や審査にかかる期間も事前に確認して、全体の流れをしっかり把握しておきましょう。
「最低基準」だけで安心できる?最新の審査内容
法律で定める「最低基準」に適合していれば、とりあえず家は建てられます。
ですが、「最低基準=絶対安心」ではないことも知っておいてください。
実際に、今回の法改正で義務化される「壁量計算」は、あくまで“最低限”の耐震性があるかどうかを確かめるものです。
専門家のあいだでは「この基準さえ満たしていれば地震が来ても絶対安心、というわけではない」という声も少なくありません。
本当に安心して長く住める家を目指すなら、「許容応力度計算」や「性能表示制度」のような、より詳しい耐震チェックを住宅会社に依頼するのがおすすめです。
これらは追加費用が発生することもありますが、耐震等級アップや将来的な資産価値の維持につながるケースも多いです。

“法律の基準を守っていれば安心”と思いがちですが、本気で地震や災害に備えたいなら“ワンランク上”の耐震診断も検討してみてください。
将来の安心料と考えれば、決して高い投資ではありません。
どんな住宅会社を選ぶべきか(信頼できる会社の見極め方)
2025年の法改正で審査が厳しくなるとはいえ、「住宅会社の実力や姿勢」による差はなくなりません。
これまで通り、法律で定められた“最低限”しかやらない会社もあれば、もともと法改正前からしっかり構造計算や耐震診断を行ってきた会社もあります。
「これから家づくりを始めるなら、住宅会社選びがとても重要」です。
たとえば、「許容応力度計算」や「耐震等級3」など、より高い基準で設計・施工してくれるかどうか、担当者にしっかり質問してみましょう。
また、「自社の取り組みや過去の実績をきちんと説明してくれるか」「分からないことに親身になって答えてくれるか」も大事なポイントです。
口コミや、実際に建てた人の評判も参考になります。

担当者に“御社は構造計算をもともとやっていましたか?”“今回の法改正で対応が増えますか?”と率直に聞いてみましょう。
そのときにしっかり説明してくれる会社こそ、信頼できる住宅会社と言えます。
注文住宅のスケジュールとおすすめの進め方(工期も解説)
家づくりを考え始めたとき、まず気になるのが「全体でどれくらい期間がかかるのか?」ということではないでしょうか。
引越しや子どもの進学、仕事の都合など、スケジュールに関わる心配は誰もが感じるものです。
ここでは、注文住宅の標準的なスケジュールや、実際にスムーズに進めるためのコツ、トラブルを防ぐポイントまでまとめて解説します。

家づくりって実際、どれくらい期間がかかるの?
仕事や子どもの予定もあるし、具体的な流れやコツを知っておきたい…
家づくり全体の流れと工期目安
注文住宅づくりは「思ったより長い」と感じる方が多いです。
全体の流れは大きく分けて「検討」「契約」「設計・打合せ」「着工・建築」「引き渡し」の5ステップ。
平均的な目安は次のとおりです。
- 情報収集・住宅会社探し:1~3ヶ月
- 土地探し・契約:1~3ヶ月
- プランニング・設計打合せ:2~4ヶ月
- 工事(基礎~建物完成):4~6ヶ月
- 完成・引き渡し:1ヶ月
全体を合計すると8~14ヶ月が一般的な所要期間。
特に最近は法改正や補助金申請の手続きも増え、やや長めになる傾向です。

「“家を建てよう!”と思ったら、まずは逆算スケジュールを書き出してみましょう。
入居希望日から余裕を持って、1年以上前に動き始めるのが安心です。
理想的なスケジュール例(10月スタート~翌年秋引き渡し)
“お得なタイミング”と“スムーズな進行”を両立させたい方には、「10月ごろに家づくりをスタート→翌年の秋(10月~11月ごろ)引き渡し」というスケジュールがおすすめです。
- 10月:家づくりスタート(住宅会社探し・土地探し・資金計画)
- 11月~1月:プラン打ち合わせ・土地契約
- 2月~4月:設計確定・詳細打合せ・各種申請
- 5月~6月:着工(基礎工事)
- 7月~9月:上棟~内装工事
- 10月~11月:外構・最終仕上げ・引き渡し・引越し
この流れなら、補助金申請のタイミングや引越し費用が高くなる時期(3~4月)も避けられ、税金・住宅ローン控除も有利になりやすいです。

年末年始は住宅会社の“値引きキャンペーン”が出ることも。
予定が合えば活用してみるのも一つの手です!
予定通り進めるコツ・トラブルを防ぐポイント
家づくりは、思い通りに進まないことが少なくありません。
実際、契約から設計打ち合わせが長引いたり、天候不順や審査の遅れで工期が延びるケースもよくあります。
スケジュール通り進めるためのポイントは、
また、トラブル防止のためには
など、“段取り力”と“相談のしやすさ”がカギです。

うまくいかない時こそ、焦らず担当者に相談しましょう。
“何が不安か”を整理して伝えるだけで、次の一手が見えてきます。
【ケース別】こんな人はこの時期に始めると得!失敗しないための判断基準
「うちの場合は、何月から家づくりを始めるのが一番得なの?」
実は、注文住宅の“お得なタイミング”は土地や建物の価格、家族の予定、地域によっても変わってきます。
ここでは、都市部や地方、家族構成やライフスタイルなどケース別に、失敗しない“自分に合った時期の選び方”を詳しく解説します。

ウチは土地が安いエリアだけど、何月から始めたら一番得なんだろう?
同じ家づくりでも、人や場所によって“お得な時期”って違うのかな…
土地・建物の価格や状況別“得する開始月”まとめ
注文住宅で“損しないタイミング”を考えるとき、まず大切なのは「土地と建物、どちらによりコストがかかるか」を明確にすることです。
税金や特例のインパクトは、土地と建物のバランス次第で大きく変わります。
例えば、都市部で土地評価額が2,000万円を超えるような場合、年内(12月末まで)に建物が完成すれば「小規模住宅用地の特例」で土地の固定資産税が1/6に軽減され、年間で数十万円も節税できるケースもあります。
一方で、土地が安く建物価格が高い地域では、1月2日以降に引き渡しを受ければ「建物の固定資産税1年分を先送り」できるメリットが大きくなります。
【体験談】
ある地方の方は、土地価格が600万円・建物が2,500万円と建物比重が高く、
「1月2日引渡し」にして建物税の1年分(約20万円)を先送りでき、結果的に初年度の出費がかなり抑えられたそうです。
逆に都市部で土地2,500万円・建物2,000万円のケースでは、「年内引き渡し」にして土地税特例を狙う方が“総額で得”になった例も。
このように、自分の土地・建物価格を試算し、複数のパターンで税金や補助金のシミュレーションを住宅会社や税理士に依頼してみるのが安心です。

土地と建物、どちらの価格が高いかで損得が大きく変わります。
契約前に“税金の試算シート”を必ず出してもらいましょう。
専門家の意見を活用するのが一番確実です。
都市部・地方/若年層・共働き世帯などケース解説
家族の状況やライフスタイル、働き方によっても、“得する開始月”や家づくりの進め方は変わります。
【都市部×共働き世帯】
都市部は土地が高く、特例の節税額も大きい一方、共働きで時間が取りにくい家庭が多いです。
引越しを3~4月に合わせると費用が高く、手続きも混雑しがち。
「秋や冬に引き渡し→年末年始にゆっくり入居準備」という流れなら、費用も抑えられ余裕を持って新生活がスタートできます。
【地方・雪国・農村部】
地域によっては、雪や繁忙期の影響で工期が伸びやすいです。
「秋に着工、春先に引渡し」など、天候や地域行事を避けて動くことでトラブルを減らせます。
また、地域密着の工務店なら地元事情に詳しいのでスケジュール相談も安心です。
【若年層・初めての家づくり】
「まずは無理せず情報収集をじっくり」「住宅ローンや補助金の審査を確実に通したい」など、手続きや資金計画に余裕をもった動き出しがカギ。
早めに検討を始めて、1年以上前から準備を始めるとトラブルや見落としも少なくなります。

“周りの家族と同じ時期に”と考えず、自分たちの生活・働き方・お子さんの予定に一番合うタイミングを優先してみましょう。
“ちょっと早め”が理想の家づくりへの近道です。
「家族の予定」「学校の入学」「転勤」も考えた時期選び
家づくりは「お金」だけでなく「家族みんなのタイミング」に目を向けることが大切です。
たとえば、お子さんの進学・転校、家族の転勤・転職、育休の復帰――
こうしたライフイベントに合わせて「いつ入居したいか?」を最初に決めておけば、スムーズに新生活を始めやすくなります。
【実例】
「子どもの小学校入学に間に合わせて4月入居!」を目指してギリギリに動き始めると、工事の遅れや引越しの混雑に巻き込まれることも多いです。
逆に、「10月~11月引き渡し→年末年始で荷物整理→新学期に新生活スタート」なら、
引越し費用も抑えられ、家族の心にも余裕が生まれます。
また、住宅ローン控除や補助金の締切も年度ごとに異なることがあるため、「家族のイベント」と「お金のメリット」を並行してチェックしましょう。

“この月に入居したい”が決まったら、そこから逆算して1年~1年半前には家づくりを始めておくのが理想です。
家族会議も早めにやっておきましょう。

まずは情報収集が大事!
タウンライフなら、ハウスメーカーがあなたオリジナルの間取りプランを「無料」で作ってくれるので、効率よく家づくりを進められるよ♪
タウンライフ注文住宅は、希望や条件に合わせて、複数のハウスメーカー・工務店から“あなただけの提案”がまとめて届くサービスです。
プロ視点の比較・要望整理・見積もりチェックが「ワンストップ」で可能なので、迷っている方や情報をまとめて整理したい方に特におすすめです。

\入力はわずか3分で完了/
最大で5社分の間取りを無料で取り寄せ可能!
FAQ・よくある質問
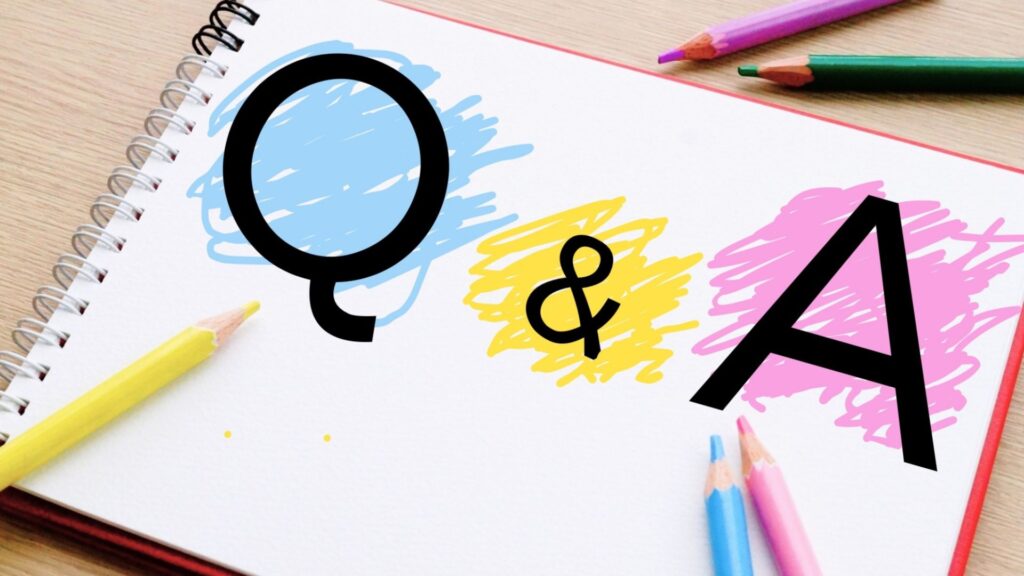
注文住宅を計画していると、「これって本当に大丈夫?」「自分の場合はどうなんだろう?」と疑問や不安がたくさん出てくるものです。
ここでは、最近よく相談されるポイントや多くの方が気になる質問について、わかりやすくまとめました。
ぜひ、家づくりのヒントや安心材料としてご活用ください。
Q1. 建築基準法改正で注文住宅は本当に高くなる?
2025年の建築基準法改正によって、設計や構造チェックの手間が増えることで「設計料や申請コストが少し上がる」傾向は出てきます。
特に、今まで“審査が省略されていた”2階建て木造住宅も構造計算などの提出が必要になり、ハウスメーカーや工務店によっては10~30万円程度コストアップするケースもあります。
ただし、すべての会社・すべての家が値上がりするわけではありません。もともと高い基準で設計していた住宅会社なら、「ほとんど変わらない」ことも多いです。

心配な方は、「今回の法改正でどこが変わる?費用は増える?」と契約前に必ず担当者に確認を。
相見積もりで内容・価格を比較するのも失敗しないコツです。
Q2. 工期はどれくらい余裕を持てばいい?
注文住宅の場合、計画スタートから引き渡しまで8ヶ月~14ヶ月ほどかかるのが一般的です。
法改正や申請手続きが増えることで、着工までの“事務手続き”や審査が1ヶ月ほど長引くケースも出てきています。
- 打ち合わせや設計…2~4ヶ月
- 各種申請・審査…1~2ヶ月(今後はやや長めを想定)
- 工事(着工から完成まで)…4~6ヶ月
引越しや入学など「この時期までに入居したい!」という希望があれば、最低でも1年以上前から逆算して動き出すのが安心です。
Q3. 今から始めても補助金は間に合う?
補助金や支援金は、年度ごと・制度ごとに「着工時期」や「予算枠の上限」で締切が決まるのが一般的です。
たとえば「子育てグリーン住宅支援事業」や「省エネ住宅の補助金」は、春から申請が始まって予算がなくなり次第終了、という年が多いです。
今から家づくりを始めても間に合うかは、
によって異なります。まずは希望の補助金の「最新の受付状況」をハウスメーカーや国・自治体の窓口で確認を。

「補助金が間に合うかどうか」不安なときは、まず住宅会社に「この制度に間に合いますか?」と遠慮なく質問しましょう。
早めの相談がベストです。
Q4. 土地探しはいつから始めると有利?
土地探しは、家づくりのスケジュールの中でも“最初に動き出すべき”部分です。
狙い目は「冬~春(12月~4月ごろ)」で、新しく売りに出る物件や掘り出し物が出やすい時期です。
特に相続やライフスタイルの変化で土地の流通が活発になるのは、年末年始から春先が多い傾向にあります。
- 希望エリア・予算を明確にしておく
- 住宅会社と連携しながら探すと、条件の良い土地を見逃しにくい
- すぐに決めず「複数候補を比較」「周辺環境や将来の用途も検討」するのが失敗しにくいポイントです
Q5. 失敗しないために気を付けたいことは?
トラブルや「こんなはずじゃなかった!」を防ぐには、「疑問点や不安を後回しにしない」ことが大切です。
まとめ
この記事では「注文住宅は何月から始めるのが本当にお得か?」という一番の疑問を、税金や補助金、工期、法改正まで幅広く解説しました。
- 注文住宅の“お得な開始月”は、税金・補助金・工期・建築基準法改正など、さまざまな要素を総合的に見て判断することが大切です。
- 固定資産税・住宅ローン控除・補助金は「時期」次第で得する額が大きく変わります。
- 2025年の建築基準法改正では構造審査や工期・費用の変化も見逃せません。
- 土地・建物・家族のライフイベントによって、“ベストなタイミング”は一人ひとり異なります。
- 早めの情報収集・計画・専門家への相談が、後悔しない家づくりのコツです。
自分の状況や家族の予定、土地・建物のバランスに合わせて、「納得できるタイミング」を見つけるヒントが見つかっていれば嬉しいです。
理想の家づくりは、少し早めの一歩と丁寧な準備から始まります。
まずは「気になる土地や住宅会社の資料を取り寄せてみる」「家族で入居時期や希望条件を話し合ってみる」など、できることから始めてみましょう。

まずは情報収集が大事!
タウンライフなら、ハウスメーカーがあなたオリジナルの間取りプランを「無料」で作ってくれるので、効率よく家づくりを進められるよ♪
タウンライフ注文住宅は、希望や条件に合わせて、複数のハウスメーカー・工務店から“あなただけの提案”がまとめて届くサービスです。
プロ視点の比較・要望整理・見積もりチェックが「ワンストップ」で可能なので、迷っている方や情報をまとめて整理したい方に特におすすめです。

\入力はわずか3分で完了/
最大で5社分の間取りを無料で取り寄せ可能!