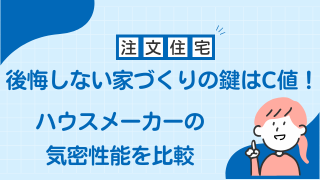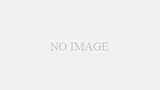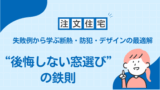せっかくのマイホーム、後悔したくないですよね。
しかし「C値」と言われても、どのハウスメーカーが本当に気密性能に優れているのか分かりにくいものです。C値0.5と1.0の違いでどれほど快適性が変わるのか、数字だけでは想像しづらいですよね。
モデルハウスでは暖かく感じても、実際に住んでみると冬に足元が冷えたり、夏に湿気がこもったりするケースもあります。

見学会では快適だったのに、住んでみたら違ったという話をよく聞きます
こうした差の多くは、家の「気密性=C値」に関係しています。
C値(シーチ)とは住宅の隙間の小ささを数値化した指標で、値が小さいほど隙間が少なく、空気が漏れにくい高性能住宅といえます。
C値は家の快適さ・光熱費・耐久性を左右する大切な要素です。断熱性能と並んで住宅性能を判断する基準のひとつであり、長く快適に暮らすためには欠かせません。

簡単に言うと、C値が低い家ほど“冬は暖かく・夏は涼しい”ということです。
数値で住宅性能を比較できるのがC値の特徴なんですよ。
とはいえ、メーカーごとにC値の測定方法や公表の仕方が違うため、単純に数字だけを比べても正しい判断はできません。
中にはモデルハウスの値をそのまま使っていたり、測定時期が異なっていたりするケースもあります。
だからこそ、C値の正しい見方を知り、信頼できる情報で比較することが大切です。
この記事では、2025年最新版のデータをもとに、ハウスメーカーの気密性能を中立的かつ客観的に分析し、C値の本当の意味と選び方を分かりやすく解説します。
- C値の正しい意味と基準値
- ハウスメーカーごとの気密性能の傾向と比較ポイント
- 後悔しないためのC値チェックリストと選び方のコツ

この記事を読めば、“数値の意味”から“メーカーごとの傾向”まで一気に理解できます。
後悔しない家づくりの第一歩を一緒に進めましょう。
C値とは 気密性能を表す数値の基本

C値ってよく聞くけど、実際には何を表しているの?
家づくりの打ち合わせでそう感じる人は多いはずです。
C値は、家の気密性(すき間の少なさ)を示す数値。
つまり「どれだけ外気を遮断できるか」を客観的に表すものです。

C値は“どれだけ空気が漏れないか”を数値で示すものです。
値が小さいほど高気密な家になります。
C値の定義と基準の変遷
C値とは、1㎡あたりにどれくらいの隙間があるかを表す数値で、単位は「cm²/m²」です。
たとえば、延べ床面積100㎡の家でC値が1.0なら、家全体で約100cm²(はがき1枚分程度)の隙間がある計算になります。
C値が0.5ならその半分、0.3ならさらに高気密な住宅です。

たった“はがき1枚分”の隙間でも、家の性能に影響があるんですね!
C値の計算方法
C値は、気密測定(ブロワドア試験)によって求めます。
測定時に家を密閉し、送風機で50Paの圧力差をかけ、空気の漏れ量を測定します。
その結果から「相当隙間面積(家全体のすき間の合計)」を算出し、以下の式で求められます。
C値=相当隙間面積(cm²) ÷ 延べ床面積(m²)
【例】
延べ床面積100m²・相当隙間面積50cm²の場合→ C値=0.5
つまり、C値0.5の家は、100㎡あたり“はがき半分”ほどの隙間しかない高気密住宅ということです。

C値は一度測ると明確に比較できる指標です。
特に“どの段階で測定したか”を確認するのも大切ですよ。
基準の変遷と海外との違い
かつては旧省エネ基準のもとで、地域別にC値の目安が定められていました。
寒冷地では2.0以下、温暖地では5.0以下が基準でしたが、2013年にこの基準は撤廃されました。
現在は、ハウスメーカーや工務店が独自の基準を設定しています。

今は全国で統一された基準がないんですね。
じゃあ、どうやって比較すればいいの?

そのとおりです。
メーカーごとに測定条件や時期が異なることがあるので、“どう測ったか”をセットで見るのがポイントです。
なお、北欧やカナダなど寒冷地域ではC値0.3以下が一般的で、日本の住宅よりも基準が厳しく設定されています。
気候や建築技術の違いはありますが、日本でもC値1.0以下を目指す住宅が増えています。
断熱と気密の違いと相互関係
家の性能を考えるうえで、「断熱」と「気密」はセットで理解する必要があります。
- 断熱:熱を通しにくくする(外気温の影響を防ぐ)
- 気密:空気の流れを遮断する(室内の空気を逃がさない)
どちらか一方だけ高めても快適な室内環境は保てません。
高断熱でも隙間が多ければ暖気が逃げ、逆に気密が高くても断熱が弱ければ外気温の影響を受けやすくなります。

断熱と気密、どっちかだけ良くても意味がないってことですね!

そうです。C値(気密)とUA値(断熱)は“家の性能を支える両輪”です。
どちらもバランスよく備えた住宅が理想的です。

まずは情報収集が大事!
タウンライフなら、ハウスメーカーがあなたオリジナルの間取りプランを「無料」で作ってくれるので、効率よく家づくりを進められるよ♪
タウンライフ注文住宅は、希望や条件に合わせて、複数のハウスメーカー・工務店から“あなただけの提案”がまとめて届くサービスです。
プロ視点の比較・要望整理・見積もりチェックが「ワンストップ」で可能なので、迷っている方や情報をまとめて整理したい方に特におすすめです。

\入力はわずか3分で完了/
最大で5社分の間取りを無料で取り寄せ可能!
なぜC値が重要なのか 快適性と耐久性の視点から
家づくりを考えるとき、断熱やデザインは注目されやすいですが、
実は「C値(気密性能)」こそが、暮らしの快適さと家の寿命を左右する要素です。
C値が悪い=すき間が多い家は、冷暖房効率が落ちるだけでなく、結露やカビの原因にもなります。

気密が低いと、足元の冷えや光熱費の高さにつながるんですね

そうなんです。C値は“数字で見える快適性”とも言えます。
具体的にどんな違いがあるのか見ていきましょう
快適性への影響
C値が高い(=すき間が多い)家では、室内の空気が外に逃げやすく、外気も入りやすくなります。
その結果、部屋ごとに温度差が生まれたり、足元だけ冷えるといった不快さが起こりやすくなります。
- 冬:暖房しても足元が冷たい
- 夏:湿気がこもり、エアコンの効きが悪い
- 年間:冷暖房費が増え、光熱費のムダが発生
一方で、C値が良い(=高気密)家では、空気の出入りが少なくなり、冷暖房の効果が安定します。
部屋ごとの温度差が減り、家全体が一定の体感温度で保たれます。

C値が良いと、夏も冬もエアコンの効きが均一になるんですね!

はい。
特に最近は“全館空調”を導入するハウスメーカーが増えていますが、
これも気密性が高くないと本来の性能を発揮できません。
つまり、C値が良い家は省エネ・快適・静音性の3拍子がそろった空間を実現できます。
耐久性への影響
C値が低い家では、外気が壁内に入り込みやすく、温度差によって壁内結露が発生するリスクが高まります。
この結露が長期間続くと、木材の腐朽やシロアリ被害の原因になることもあります。
反対に、C値が良い家では空気の流れがコントロールされるため、湿度変化が安定し、結露やカビの発生を抑えやすい構造になります。
結果として、構造体(柱・梁)の耐久性を長く維持できるのです。

C値が高いと、家の“寿命”まで左右されるんですね。

その通りです。
見た目では分からない部分ほど、気密性能が家を守っています。
漏気経路の実測データと対策
高気密住宅を目指すうえで、「どこから空気が漏れやすいのか」を知ることが大切です。
下表は、気密測定でよく見られる漏気部位とその割合、対策のポイントをまとめたものです。
| 部位 | 漏気の割合(%) | 対策ポイント |
|---|---|---|
| 床と壁の取り合い | 約34 | パッキン・テーピング処理で隙間を封止 |
| 壁と天井の取り合い | 約31 | 気密シートを連続して施工 |
| 窓・建具まわり | 約9 | サッシの選定と取り付け精度の確保 |
| コンセント・配線まわり | 約3 | 専用気密カバーの使用で空気漏れを防止 |

床と壁のつなぎ目って、そんなに空気が漏れているんですか!

意外ですよね。
実際、床と壁の“取り合い部”だけで漏気の3割以上を占めます。
ここを丁寧に処理できているかがC値の差になります。
こうした細部の施工精度こそが、ハウスメーカーや工務店の技術力と品質管理の違いとして現れます。
換気計画とC値の関係 第1種と第3種の比較
C値(気密性能)は、換気計画の正確さにも大きく関係します。
いくら高性能な換気システムを導入しても、すき間が多ければ思ったように空気が流れず、
本来の効果を発揮できません。

C値が悪いと、計画換気ではなく“すき間から勝手に外気が入る”状態になります。

つまり、高気密な家ほど“計画通りに空気が流れる”んです。
では、換気方式ごとの違いを見てみましょう。
換気方式の基本とC値の関係
住宅の換気方式は大きく分けて「第1種」と「第3種」の2種類があります。
どちらを選ぶかによって、必要なC値の水準や空気の流れ方が変わります。
| 項目 | 第1種換気 | 第3種換気 |
|---|---|---|
| 給排気 | 機械+機械(両方ファンで制御) | 自然+機械(給気はすき間から) |
| 熱交換 | あり(排気熱を再利用) | なし |
| C値の影響 | 低いほど安定して機能 | 高いと外気の流入が不安定 |

第3種って、すき間から空気を入れるんですか?
それじゃC値が悪いと大変ですね。

その通りです。
C値が高い=すき間が多い家では、
外気が制御できずに流れ込み、湿度や温度がバラつくんです。
第1種換気+高気密が理想的な理由
第1種換気は、機械で給気も排気もコントロールする方式です。
C値が低いほど外気の影響を受けず、計画どおりに空気が循環します。
さらに、排気時に熱を回収する熱交換システムがあるため、暖房や冷房のエネルギー損失を抑えられます。
一方、第3種換気は、給気を“家のすき間”に依存する仕組みです。
そのためC値が悪い住宅では、外気が勝手に入り込み、換気量が安定しません。
この状態を「漏気換気」と呼び、エネルギー効率が著しく低下します。

つまり、第3種だとC値が高い家では“意図しない換気”が起こるんですね。

そうなんです。
計画換気は“家の気密性能が前提”。
C値が良くないと、
どんな高性能換気装置でも本来の機能を発揮できません。
数値で見る換気方式の違い(シミュレーション)
外気温0℃・湿度70%、室内温度20℃・湿度40%の条件で、1時間後にどのような変化が起こるかを比較してみましょう。
| 条件 | 室温 | 湿度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 第1種換気(熱交換あり・高気密) | 約18℃ | 約38% | 外気を熱交換して取り込むため、温度・湿度が安定 |
| 第3種換気(熱交換なし・低気密) | 約10℃ | 約55% | 外気がそのまま侵入し、室温低下と湿度上昇が発生 |
このように、同じ外気条件でもC値と換気方式の組み合わせで結果が大きく変わります。
高気密+第1種換気の家では、エネルギーロスが少なく快適性を保ちやすい一方、C値が悪い家では、暖房を強くしても効率が下がり、湿気や結露の原因にもなります。
換気と健康・省エネの関係
C値が悪い住宅では、計画換気が乱れることで二酸化炭素濃度の上昇やホルムアルデヒドの滞留など、
健康面への影響が懸念されます。
また、外気の侵入が増えることで冷暖房エネルギーが余分に必要となり、年間光熱費も上昇します。

C値って、空気の流れや健康にも関係するんですね!

はい。
だからこそ“気密と換気のセット設計”が重要なんです。
換気計画は、C値を前提に考えましょう。
ハウスメーカーのC値 公開情報の見方
ハウスメーカーのサイトを見ていると、「C値0.5」や「高気密住宅」といった表現をよく目にします。
しかし、この数値がどのように測定され、どの範囲のデータなのかを理解していないと、正確な比較はできません。

“C値0.3”って書いてあるとすごく良さそうですが、全部の家がそうなんでしょうか?

実は、C値には“どんなタイミングで・どんな対象で測ったか”によって信頼度が変わるんです。
公表値の種類と信頼度
C値の公表データには、大きく分けて3つのタイプがあります。
どれも「意味」と「測定対象」が違うため、見分け方を知っておくことが大切です。
| 種別 | 内容 | 信頼度 | コメント |
|---|---|---|---|
| モデルハウス値 | 展示場などのサンプル住宅で測定した値 | 低 | 実際の施工条件とは異なり、性能が高めに出やすい |
| 平均実測値 | 実際に建築された複数棟の平均値 | 中〜高 | 実態を反映しており、比較的信頼できる |
| 約束値(保証値) | 契約時に保証される最大値 | 高 | 明確な基準で保証されるため、安心感が高い |

“平均実測値”と書かれていれば信頼度が高いですね。

そうです。
“モデルハウス値”だけで判断するのは危険。
複数棟の実測や保証値を確認するのがポイントです。
測定タイミングで変わるC値の精度
C値はどの段階で測るかによっても結果が変わります。
特に「木工事中」と「完成時」では目的が異なります。
- 木工事中に測定
→ 壁や床が仕上がる前に測定するため、気密施工の改善が可能。理想的なタイミングです。 - 完成時に測定
→ 施工の最終チェックとして行われる。引き渡し時の品質確認として有効ですが、是正は困難です。

木工事中に測ると、まだ修正できるんですね!

その通りです。
最近は両方測定して、施工精度と最終品質をダブルで確認するメーカーもあります。

まずは情報収集が大事!
タウンライフなら、ハウスメーカーがあなたオリジナルの間取りプランを「無料」で作ってくれるので、効率よく家づくりを進められるよ♪
タウンライフ注文住宅は、希望や条件に合わせて、複数のハウスメーカー・工務店から“あなただけの提案”がまとめて届くサービスです。
プロ視点の比較・要望整理・見積もりチェックが「ワンストップ」で可能なので、迷っている方や情報をまとめて整理したい方に特におすすめです。

\入力はわずか3分で完了/
最大で5社分の間取りを無料で取り寄せ可能!
ハウスメーカー別 C値比較と特徴【2025年最新版】
※本章の内容は、各社の公式資料・技術ページ・公開レポートに基づいており、数値は地域・仕様・施工条件により変動します。最新情報は必ず公式サイトでご確認ください。
C値(気密性能)はメーカーごとに差があり、「どこまで全棟測定を行っているか」や「公表値の根拠」が信頼性を左右します。数値だけでなく、測定体制も比較のポイントです。

どのメーカーが“本当に高気密”なのか知りたいです。

数値の高さだけではなく、測定の透明性を見ることが大切ですよ。
公表データに基づくC値比較表(2025年時点)
| メーカー | 実測・公表傾向 | 測定方針・特徴 | 参照元 |
|---|---|---|---|
| 一条工務店 | 実測平均 0.59(全棟測定) | 全棟で中間・完成の2回測定を実施。安定して0.6前後を達成。 | 一条工務店公式「性能へのこだわり」(ichijo.co.jp)/住宅産業新聞「一条工務店 技術特集」(2023) |
| スウェーデンハウス | 実測平均 0.64(2022年度) | 木製サッシ+三層ガラスを採用。全棟でC値測定を実施し、寒冷地対応に強み。 | スウェーデンハウス公式「性能データブック2022」(swedenhouse.co.jp) |
| セキスイハイム | 数値非公表(品質管理体制に強み) | 工場ユニット生産で接合部精度を高く保つ。気密性能にバラつきが少ない。 | セキスイハイム公式「施工品質」(sekisuiheim.com) |
| 住友林業 | 実測事例 0.8〜1.0台(地域差あり) | 木造BF構法に気密シートを併用。完成時に測定を行うケースもある。 | 住友林業公式「技術情報」(sfc.jp) |
| アイ工務店 | 平均 0.32(全棟測定) | 契約時に「C値0.5以下」を標準目標。施工後全棟で実測。 | アイ工務店公式「高性能住宅」(ai-koumuten.co.jp) |
| アイフルホーム | 実測平均 0.46(加盟店平均) | FC加盟工務店単位で気密測定を実施。安定した施工品質を維持。 | LIXIL住宅研究所公式ブログ(eyefulhome.jp/2022年) |

意外と数値を公表していないメーカーも多いんですね。

そうなんです。公表している会社ほど、測定制度や品質管理に自信がある傾向があります。
比較のポイント

C値の数値だけを見比べても、本当の意味での“気密性能の良し悪し”は判断できません。
なぜなら、メーカーによって測定の方法・タイミング・公表の基準が大きく異なるからです。
そこでここでは、C値を比較するときに知っておきたい3つの視点を整理してみましょう。
① 数値よりも“測定制度”を見ることが重要
全棟測定を行うメーカーは、棟ごとの差を把握して改善に活かせます。
モデルハウスだけの値では実際と異なる場合があります。
② 測定タイミングにも注目
木工事中(中間測定)であれば是正が可能ですが、完成時のみの測定では修正が難しくなります。
③ 公開姿勢=施工品質への意識
C値を非公表にしているメーカーが必ずしも低性能とは限りませんが、公開している企業は施工体制が確立していることが多いです。

なるほど、C値の“数字の大きさ”だけで判断してはいけないんですね

その通りです。測定の透明性こそ、気密性能を見抜く最大のポイントなんです。
※最新情報は必ず各メーカー公式ページまたは担当窓口にてご確認ください。

C値を見るときは、“数値+測定方法+公表の信頼性”の3点セットで比べるのがコツです。
たとえば一条工務店やスウェーデンハウスのように全棟測定を実施しているメーカーは、施工の再現性が高い傾向にあります。
一方で、セキスイハイムや住友林業のように品質体制で支えている企業も信頼性があります。
自分が重視するポイント(性能・保証・施工管理)を軸に選ぶことが、後悔しない家づくりにつながります。

まずは情報収集が大事!
タウンライフなら、ハウスメーカーがあなたオリジナルの間取りプランを「無料」で作ってくれるので、効率よく家づくりを進められるよ♪
タウンライフ注文住宅は、希望や条件に合わせて、複数のハウスメーカー・工務店から“あなただけの提案”がまとめて届くサービスです。
プロ視点の比較・要望整理・見積もりチェックが「ワンストップ」で可能なので、迷っている方や情報をまとめて整理したい方に特におすすめです。

\入力はわずか3分で完了/
最大で5社分の間取りを無料で取り寄せ可能!
設計段階でC値を下げる方法
家の気密性能(C値)は、完成後に決まるものではなく設計段階の工夫で大きく変わります。
外形や窓配置をシンプルにするだけでも、漏気リスクを大幅に減らすことができます。

間取りの工夫でもC値を良くできるんですね。

そうなんです。実は“設計の引き算”こそ、C値を安定させる最大のコツなんです。
設計でできる工夫
家の形や構造をシンプルにすることで、気密施工の難易度が下がり、安定したC値が得られます。
複雑な凹凸や吹き抜け、入り組んだ屋根形状は、気密シートや断熱層の連続性を途切れさせる原因になります。
- 凹凸の少ない外形にする
四角形に近いプランは、接合部(取り合い)を減らし、漏気を防ぎます。 - 床・壁・天井取り合いの連続気密処理
気密シートやテープを連続して貼ることで、継ぎ目の隙間をなくします。 - 換気ダクト・配管貫通部を最小化
穴の数を減らすだけで漏気リスクが低下。点検口周辺もテーピング処理を徹底します。

なるほど、設計の段階で“隙間ができにくい構造”を意識するのが大事なんですね。

その通りです。
図面上で“どこを空気が通るのか”を想定しておくと、現場での補修も減らせます。
窓計画のコツ
気密性能を左右する最大の要素のひとつが「窓」です。
窓の形・配置・性能を工夫することで、C値をさらに安定させることができます。
- 引き違い窓よりも開き窓・FIX窓を採用
引き違い窓は構造上どうしても隙間が生まれやすいため、開き窓やFIX(固定)窓に置き換えると効果的です。 - 樹脂サッシ+Low-E複層ガラスを選ぶ
アルミサッシよりも気密・断熱性能が高く、漏気と結露の抑制に優れます。 - 窓の数と位置を最適化
南面に集約して採光を確保しつつ、北面や風上側の開口部を減らすと、漏気量をコントロールしやすくなります。

窓ってデザインだけじゃなく、性能にも大きく関わるんですね。

そうなんです。窓は“断熱と気密の要”。
性能と配置のバランスを取ることで、C値も住み心地も安定します。
構造別の気密戦略 木造と鉄骨
構造によって気密を確保するための課題は異なります。
木造は施工精度によるばらつきが出やすく、鉄骨は開口部や接合部での漏気リスクに注意が必要です。

構造ごとに“弱点”が違うので、対策方法も変わってきます。
木造住宅の気密戦略

木造住宅は、構造体そのものが「呼吸する素材」であるため、施工精度によってC値が大きく変わります。
特に在来工法では、柱・梁・合板の取り合い部や、配管まわりの処理で差が出やすい傾向があります。
- 合板の気密ラインを連続させる
壁・床・天井の気密ラインを“1本の線”として設計し、構造体を貫通する箇所を最小限に抑えることが大切です。 - 透湿・防湿シートの整合性を確認
防湿シートが連続していないと、壁内に湿気が侵入して結露の原因になります。
継ぎ目のテーピングやコーナー部の処理を丁寧に行うことで、長期的な気密性能を維持できます。

木造は“気密の精度=職人の技術力”なんですね。

そうですね。構造の性質上、現場ごとの施工品質がC値を大きく左右します。
鉄骨住宅の気密戦略

鉄骨構造は、柱や梁の接合が金属で固定されるため、構造体自体の隙間は少ない傾向があります。
しかし一方で、金属の熱伝導やサッシまわりの納まりが原因で気密性を損ねるケースがあります。
- サッシまわりの処理を重点管理
鉄骨造では、サッシと下地の取り合いに微細な隙間が生じやすいため、発泡ウレタンや気密パッキンで密閉します。 - 大開口部・接合部のパッキン処理を入念に
リビングなどの大開口サッシでは、熱橋(ヒートブリッジ)と漏気の両方が発生しやすいです。
ゴムパッキンや防水テープで外気の侵入を防ぐ施工が効果的です。

鉄骨って密閉性が高そうなのに、意外と開口部が弱点なんですね。

構造体そのものよりも“接合部とサッシ周辺”が要注意ポイントなんです。
木造と鉄骨のC値比較の目安
| 構造 | 一般的なC値の傾向(実測目安) | 気密確保の難易度 | 主な注意点 |
|---|---|---|---|
| 木造(在来・2×4) | 0.3〜1.0 | ★★★☆☆ | シート連続性・配管まわり処理 |
| 鉄骨(軽量・重量) | 0.5〜1.5 | ★★☆☆☆ | サッシ納まり・大開口部の気密管理 |
※数値は公表事例や実測平均に基づく一般的な目安です。地域・施工条件により変動します。
木造は“施工精度”、鉄骨は“ディテール管理”がカギです。
どちらの構造でも、設計段階で気密ラインをどう確保するかを明確にしておくと、完成時のC値が安定します。
ハウスメーカーを選ぶ際は、“どのタイミングでC値測定を行っているか”も確認すると安心ですよ。

まずは情報収集が大事!
タウンライフなら、ハウスメーカーがあなたオリジナルの間取りプランを「無料」で作ってくれるので、効率よく家づくりを進められるよ♪
タウンライフ注文住宅は、希望や条件に合わせて、複数のハウスメーカー・工務店から“あなただけの提案”がまとめて届くサービスです。
プロ視点の比較・要望整理・見積もりチェックが「ワンストップ」で可能なので、迷っている方や情報をまとめて整理したい方に特におすすめです。

\入力はわずか3分で完了/
最大で5社分の間取りを無料で取り寄せ可能!
契約前のチェックリスト

ハウスメーカーと契約する前に、気密性能(C値)まわりの確認項目を整理しておくことが大切です。
C値の数値だけでなく、「どう測定しているのか」「未達時の対応が明確か」を確認しておくと、後悔のない判断ができます。

契約時にここを聞いておけば安心ですね。

はい。C値の“数値”より、“運用ルール”を押さえるのが本当の安心です。
チェックリストの使い方
このチェックリストは、打ち合わせ・契約前に印刷して確認するための実践用ツールです。
営業担当者に質問するときの“トークスクリプト”としても活用できます。
聞きにくい内容ほど、契約前にクリアにしておくことでトラブル防止につながります。
| チェック項目 | 確認ポイント | 理由・背景 |
|---|---|---|
| C値の表記種別 | 「モデルハウス値」「平均実測値」「約束値」のどれかを確認 | 種別により信頼度が異なり、実際の施工品質を判断する基準になる |
| 測定時期 | 木工事中・完成時のどちらか、または両方実施か | 中間測定があると、是正が可能でC値の安定度が高まる |
| 目標値未達時の是正体制 | 契約書・仕様書に補修手順の明記があるか | 数値未達時の対応があいまいだと、施工後にトラブルになるリスクがある |
| 換気方式の確認 | 第1種・第3種など、住宅に採用される換気方式を確認 | 気密性能と換気方式はセットで考えるべき要素 |
| 窓種・サッシ仕様 | 樹脂サッシ・アルミ樹脂複合・Low-Eガラスなどを確認 | サッシ性能がC値・断熱性能・光熱費に直結する |
| 地域別の施工再現性・事例数 | 同地域での施工実績があるかを確認 | 断熱・気密は地域の気候や施工習慣によって差が出る |

約束値”や“中間測定”って、言われないと気づかない点ですね。

その通りです。契約書に“測定方法”が書かれているかどうかが、信頼できるメーカーの分かれ道なんです。
契約時に確認しておきたい質問例
- 「C値はどのタイミングで、誰が測定しますか?」
- 「モデルハウスと実際の施工現場で数値に差がありますか?」
- 「もしC値が目標を下回った場合、どんな是正を行いますか?」
- 「気密測定の結果は施主にも開示されますか?」
このように質問しておくことで、営業トークでは見えにくい“品質管理の実態”を把握できます。

家づくりは“数値の良さ”よりも、“数値をどう保証するか”が大切です。
契約前にC値や測定体制を明確にしておくと、引き渡し後のトラブルも少なくなります。
このチェックリストを印刷して打ち合わせに持参すれば、信頼できるメーカーを見極めやすくなりますよ。
まとめ:C値を知ることが、後悔しない家づくりの第一歩
この記事では、「ハウスメーカーの気密性能(C値)」について、中立的に比較・解説してきました。
C値は単なる“数値競争”ではなく、家の快適さ・光熱費・耐久性・健康性を支える重要な指標です。
- C値とは?
家の「隙間の大きさ」を表す数値で、小さいほど高気密。0.5〜1.0が高性能住宅の目安。 - なぜ重要?
気密が低いと、冷暖房効率が悪化し、結露やカビの原因にもなります。
C値は“家の寿命”を左右する指標でもあります。 - 比較の際の注意点
公表値が「モデルハウス」「平均実測」「約束値」かを確認し、測定時期や補修体制をチェック。 - 設計・構造での工夫
シンプルな外形・気密ラインの連続・樹脂サッシの採用などで安定したC値を実現。
木造は施工精度、鉄骨は開口部の処理がカギ。 - 契約前のチェックリスト
C値の表記・測定方法・是正対応・換気方式を確認し、トラブルを防止。

C値って、専門的な話かと思ってたけど、実は家づくりの基本なんですね。

そうなんです。C値を理解する=“快適で長持ちする家を選ぶ力”を持つことなんですよ。
C値の理解が深まったら、次は具体的なメーカー比較に進む段階です。
ハウスメーカーごとに「公表値」や「測定方法」「地域実績」は異なります。
まずは、気になるメーカーから実際の性能資料を取り寄せて、数字の根拠を確かめてみましょう。

資料を見れば“約束値”とか“測定体制”がわかるんですね。

そうです。資料請求=数字の裏付けを自分で確認する最初の一歩なんです。
- C値の表記方法と根拠
「モデルハウス値」か「実測平均」か、「約束値」なのかを明記しているか。 - 測定体制と保証の有無
全棟測定を実施しているか、数値が未達だった場合に再測定・是正の仕組みがあるか。 - 地域別の施工事例
自分の建築予定エリアで同条件の施工があるかどうか。気候・職人精度でC値は変わります。
料請求は“営業資料を集める”というより、施工品質の裏付けを取るリサーチです。
複数社を比較して、自分たちの暮らし方に合う性能バランスを見つけてくださいね。

まずは情報収集が大事!
タウンライフなら、ハウスメーカーがあなたオリジナルの間取りプランを「無料」で作ってくれるので、効率よく家づくりを進められるよ♪
タウンライフ注文住宅は、希望や条件に合わせて、複数のハウスメーカー・工務店から“あなただけの提案”がまとめて届くサービスです。
プロ視点の比較・要望整理・見積もりチェックが「ワンストップ」で可能なので、迷っている方や情報をまとめて整理したい方に特におすすめです。

\入力はわずか3分で完了/
最大で5社分の間取りを無料で取り寄せ可能!