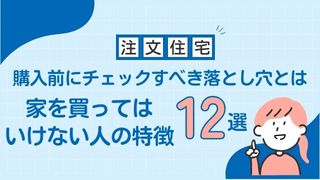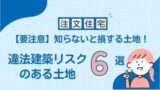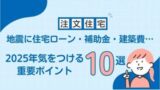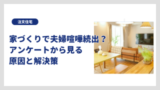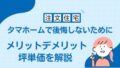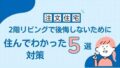家の購入を考えるとき、自分は本当に「買ってもいい立場なのか」と不安になる方も多いのではないでしょうか。
住宅ローンは数十年にわたる長期の返済が前提となるため、少しの判断ミスが思わぬ苦労や後悔につながってしまいます。
実際に、家を買ってから後悔してしまう人にはいくつかの共通点があります。
たとえば、将来の見通しが甘い、家計が不安定、必要な知識が不足しているといったケースです。
もしこれらに当てはまる場合は、マイホーム購入をいま決断すべきか慎重に見極める必要があります。
この記事では、家を買ってはいけない人の特徴12個とその背景にある理由を、実例も交えてわかりやすく解説していきます。
ご自身の状況を照らし合わせながら、後悔しない家づくりの判断材料としてお役立てください。
- 家を買ってはいけない人の特徴と、その背景にある共通点
- 住宅購入で後悔しやすいリスクや注意点、実際の事例
- どんな人なら家を買っても安心なのか、その判断基準
特徴①将来の家族計画を立てていない人
家を購入するとき、将来の家族構成についてどのくらい具体的に考えていますか?
子どもが何人になるか、進学先はどうするかといった計画は、家計に大きな影響を与える要素です。
教育費は想像以上にかかる
文部科学省の調査によれば、子ども1人を大学まで進学させる場合、すべて公立でも約800万円、私立を含めると1,000万円を超えるケースもあります。
このほかにも、食費や衣類、習い事、医療費などが年々積み重なっていきます。
見通しの甘さが破綻の引き金に
これらの支出を十分に見込まないまま住宅ローンを限界まで組んでしまうと、家計が圧迫されるリスクが高くなります。
特に、共働き前提の返済計画やボーナスを頼りにしたローン設定は、将来的な変化に弱く、不安定です。
家族構成の変化を見越した計画を
住宅購入は一時的な判断ではなく、長期的な視点で計画を立てる必要があります。
現在の生活費や収入だけでなく、10年後・20年後にかかる家族の費用も踏まえた上で資金計画を組むことが大切です。
特徴②収入が不安定な業種・職種の人
「収入は今のまま、ずっと続いていく」と、なんとなく思っていませんか?
しかし、景気や働き方が大きく変わる中で、収入が安定しているとは言いきれない職種も少なくありません。
景気に左右される職種は要注意
飲食業、観光業、イベント業界などは、外部環境の影響を受けやすい代表的な業種です。
コロナ禍では、こうした分野に携わる多くの方が、急な収入減や雇止めなどの影響を受けました。
賞与のカットや残業代の減少によって、予定していたローン返済が苦しくなった方も少なくありません。
今は大丈夫でも、将来はわからない
特にフリーランスや歩合制の仕事は、収入に波がありやすい特徴があります。
体調、景気、契約先の都合などで、思わぬタイミングで収入が減るリスクがあるのです。
住宅ローンの返済は毎月固定で発生するため、収入が減ったとしても支払いが免除されることはありません。
「毎月の支出が増え続ける中で、返済だけは確実にやってくる」──
この現実をきちんと見つめる必要があります。
家の購入は“いつでもできる”選択肢
家は今すぐに買わなければならないものではありません。
将来、収入が安定し、余裕を持った資金計画が立てられるようになってから購入を検討しても遅くはないのです。
焦らず、自分の働き方や収入の見通しが立ってから判断することが、後悔しない家づくりへの第一歩になります。
特徴③リストラや転職の可能性がある人
「この会社であと何年働けるのか」
そう問いかけたときに不安を感じるなら、住宅購入は慎重に検討すべきです。
リストラは誰にでも起こりうる時代
近年は、年齢や勤続年数にかかわらず、人員整理や早期退職の対象になる可能性があります。
真面目に働いていても、会社の経営判断や外部環境の変化で、突然職を失うことは十分にあり得ます。
実際に50代を中心に、希望退職や業務縮小をきっかけとした早期退職の事例も増えています。
こうした状況で住宅ローンを抱えてしまうと、退職後の家計に大きな負担がのしかかることになります。
転職にはリスクとブランクがつきもの
キャリアアップや働き方の見直しを目的に転職を考える方も注意が必要です。
転職後は収入が一時的に下がることが多く、待遇や試用期間に不安を感じるケースもあります。
さらに、転職先がすぐに決まらず、数カ月間の空白期間が発生する可能性もゼロではありません。
このような時期にローンの返済が始まってしまうと、精神的・金銭的に大きなプレッシャーとなります。
審査後の転職や退職にも注意
住宅ローンは、申込み時点だけでなく、実行時点でも在職状況や収入が確認されることがあります。
そのため、ローン審査が通った後に転職や退職をすると、契約そのものが無効になったり、条件が見直されてしまうこともあるのです。
これを知らずに転職してしまい、「審査は通ったのに融資が降りなかった」というケースも実際に発生しています。
安定してからの購入でも遅くない
住宅購入は、焦って決めるものではありません。
リストラや転職の可能性があるなら、まずは収入と生活の基盤を安定させてから判断することが大切です。
落ち着いたタイミングで購入を検討すれば、無理のない返済計画を立てることができ、将来の不安も軽減できます。
特徴④脱サラや起業を考えている人
「会社を辞めて、自分の力で挑戦したい」
そんな前向きな思いを抱く方もいるでしょう。しかし、脱サラや起業を考えている時期に家を購入するのは、慎重な判断が必要です。
起業直後の生活は予想以上に不安定
会社員を辞めれば、毎月の安定した給与はなくなります。
起業当初は収入が不安定になりやすく、売上が思うように伸びず赤字になるケースも少なくありません。
確定申告でも赤字計上となることが多く、生活費やローン返済のプレッシャーが日々重くのしかかります。
また、「退職金でなんとかなる」と思っていると、老後資金を先食いしてしまうことにもなりかねません。
いったん使ってしまった資金は、簡単には取り戻せません。
実績がないとローン審査は通らない
住宅ローンは、過去の安定した収入実績を前提に審査されます。
開業したばかりでは実績とみなされず、融資を受けることは極めて難しくなります。
さらに、起業後1〜2年では銀行からの信用も得にくいため、希望の金額を借りられない、あるいはそもそも審査が通らないこともあります。
事実として、「会社を辞めてから買おうと思ったが、ローンが通らずに断念した」という声も少なくありません。
タイミングを見誤ると、家そのものを諦めなければならなくなる可能性もあります。
事業の基盤が整ってからでも遅くはない
事業が軌道に乗るまでには、一般的に2〜3年はかかると言われています。
この期間は収入が安定せず、先の見通しが立たない状況が続くことが多いです。
焦って家を買ってしまうと、ローン返済と事業運営の両方で精神的にも金銭的にも追い詰められてしまいます。
まずはビジネスの土台を築き、安定した収入を確保できるようになってから、家の購入を検討するのが現実的です。
理想の住まいは、事業と生活が安定してからでも十分に実現できます。

まずは情報収集が大事!
タウンライフなら、ハウスメーカーの資料を無料で一括請求できるから、効率よく家づくりを進められるよ♪
ハウスメーカーを悩んでいるあなたへ。
タウンライフ家づくりで資料請求してみませんか?
無料で間取りプラン・見積もり・資金計画書を作成してくれます。

- 家づくりのアンケートに回答(約3分)
- ハウスメーカーを選ぶ(1,100社提携)
- 待つだけ!間取り・見積もりが届く!
特徴⑤転勤の可能性が高い人
転勤の可能性が高い人にとって、住宅購入は慎重に判断すべき大きな決断です。
どれほど理想のマイホームを手に入れても、そこに住み続けられない可能性があるならリスクは大きくなります。
家を買った直後に転勤が決まることも
「家を買ったとたんに転勤が決まった」
このような話は決して珍しいことではありません。
特に全国転勤のある企業や異動の多い業種に勤めている人は、常に転勤リスクを抱えています。
実際、マイホームを購入した直後に転勤辞令が出るケースも多く、「家を買うと転勤になる」という“あるある”が現実になることもあります。
そうなれば、自宅を残して単身赴任を選ぶか、家族ごと引っ越すかという判断を迫られます。
どちらを選んでも生活コストは増え、精神的にも家計的にも負担が大きくなります。
賃貸に出すと赤字になる可能性も
「転勤になったら家を貸せばいい」と安易に考えるのは危険です。
まず住宅ローンは、自分が住む前提で契約されています。無断で賃貸に出すと、ローン契約違反となり、最悪の場合、一括返済を求められることもあります。
仮に正規の手続きを経て貸し出せたとしても、家賃収入でローンの返済・固定資産税・管理費をすべてカバーできるとは限りません。
利便性が低い立地であれば、借り手が見つからず空室になるリスクも十分にあります。
さらに、「売ってしまえばいい」と思っても、購入後間もない家は住宅ローンの残債が売却価格を上回っていることが多く、売っても返済しきれない“債務超過”状態になることも珍しくありません。
住めない家は、心の負担にもなる
家を購入したのに、そこに住めないという状況は、金銭面だけでなく精神的なストレスにもつながります。
自宅に帰れない生活が続くと、愛着も薄れ、家族関係に影響を及ぼすケースもあります。
「自分の家があるのに、そこにいられない」──
そんな状況が長引けば、住まいが「安心の場所」ではなく「見えない負担」になってしまうかもしれません。
転勤リスクがあるなら今は買うべきではない
住宅購入は、「この場所で長く暮らせる」という前提があるからこそ成立するものです。
勤務地が確定していない、今後異動の可能性が高い、という状況で家を買うことは、のちのち大きな後悔につながる可能性があります。
まずは職場の人事方針が見直されるのを待つ、あるいは転勤のない職種へ移るなど、将来の生活が見通せるようになってから購入を検討しても遅くはありません。
特徴⑥新築信仰が強い人
「どうせ買うなら、やっぱり新築が一番」
そう考える方は多いかもしれませんが、“新築=正解”とは限らないのが住宅購入の難しいところです。
新築は購入直後に価値が下がる
新築住宅は、契約・引き渡しの瞬間から「中古」扱いとなり、資産価値が大きく下がる傾向にあります。
これは、新車を買った直後に市場価値が落ちるのと似ています。
特に分譲住宅や建売住宅には、販売会社の利益が価格に上乗せされているため、購入価格と実際の価値にギャップがあるケースが多く、買った瞬間に“割高な買い物”になるリスクもあるのです。
さらに注意すべきなのは、どんなに新しい家でも「立地」が悪ければ資産価値は下がるという点です。
新築かどうか以上に、「どこにあるか」が資産性に直結します。
設備やデザインへのこだわりが、返済を圧迫することも
新築住宅では、間取り・設備・インテリアなどの自由度が高いため、「せっかくだから」とオプションやグレードを追加していくうちに、当初の予算を大きく超えてしまうことがあります。
特にモデルハウスや完成見学会は、購買意欲を刺激するように設計されており、「こんな家に住みたい!」という感情が先行してしまうことも。
その結果、冷静さを失ってローン返済に無理が出るような契約をしてしまう人も少なくありません。
住宅ローンは数十年にわたる大きな負担です。
見栄や理想を優先しすぎると、家を持つ喜びがプレッシャーに変わる可能性があるのです。
中古住宅でも、賢い選択ができる
一方で、中古住宅は価格が落ち着いており、築20年程度の物件であれば資産価値が安定している場合も多くあります。
必要に応じてリフォームやリノベーションを施すことで、自分らしい暮らしを実現しつつ、無理のない資金計画を立てやすいのがメリットです。
また、中古住宅は「ローン残債」と「家の価値」が釣り合っていることも多く、万が一売却することになっても債務が残りにくいという安心感もあります。
新築は魅力的、でも冷静な判断が大切
新築住宅にはたしかに魅力があります。
しかし、資産形成・返済計画・将来設計という視点を持たずに“新築=正解”と考えるのは非常に危険です。
家を買うことは、人生の中でも大きな選択です。
新築か中古かではなく、「自分にとって無理のない選択はどちらか」を基準に考えることが、後悔しない家づくりの第一歩になります。

まずは情報収集が大事!
タウンライフなら、ハウスメーカーがあなたオリジナルの間取りプランを「無料」で作ってくれるので、効率よく家づくりを進められるよ♪

\入力はわずか3分で完了/
最大で5社分の間取りを無料で取り寄せ可能!
特徴⑦郊外の広さを優先する人
「同じ価格で2倍の広さが手に入るなら、郊外の方が得では?」
そう思う方も少なくありません。しかし、広さを優先して郊外を選ぶことが、将来の負担や後悔につながるケースは少なくないのです。
今は得に見えても、将来は資産価値が下がる
たしかに、都心部に比べて郊外では広くて新しい家を手頃な価格で購入できます。
しかし、その「お得感」は短期的なものであり、20年後、30年後には大きく価値が下がる可能性があります。
背景には、人口減少と少子高齢化があります。
住宅需要が利便性の高い都市部に集中し、郊外や地方では空き家が増加しています。
将来的に買い手が見つからず、「売りたくても売れない」という状況に陥るリスクもあります。
さらに、同じ価格でも立地によって価値の推移は大きく異なります。
都心の狭小地は価格が維持・上昇することもありますが、郊外では値下がりしやすく、資産価値の差が年々広がっていくのです。
維持費・固定資産税など“目に見えない負担”も大きい
郊外の広い住宅には、もう一つの落とし穴があります。
それは、購入後にかかる維持コストの大きさです。
広い土地・建物は、固定資産税が高くなりやすく、将来的には修繕費や管理の手間も増えていきます。
特に、子どもが独立した後や老後の生活に入ると、「広すぎて持て余す」「掃除や管理が負担になる」という声も多く聞かれます。
コスト面だけでなく、時間や労力といった“見えない負担”が家にのしかかることも忘れてはいけません。
売却しづらいという“出口リスク”にも注意
広さ重視で郊外の住宅を選んだ場合、売却時に苦労するケースも多く見られます。
人口減と需要の低下により、買い手がつきにくく、想定していた価格で売れないばかりか、大幅な値下げを求められることも珍しくありません。
さらに、次の住み替えや相続時にトラブルが起きやすく、
「売れない」「相続人が要らないと言う」など、思わぬ形で悩みの種になる可能性もあるのです。
土地選びは「広さ」より「立地の資産性」が重要
住宅購入で最も重視すべきは、建物の広さではなく土地そのものの資産価値です。
建物は時間とともに価値が下がりますが、良い立地の土地は将来的に売却や賃貸といった“選択肢”を残してくれます。
たとえ狭くても、利便性の高いエリアや将来の人口が見込める地域を選ぶ方が、長期的に見て“損しにくい選択”と言えるでしょう。
特徴⑧家は資産だと思い込んでいる人
「家を買えば、資産になるから安心」
そんなふうに考えていませんか?
実はこの思い込みこそが、住宅ローン破綻や後悔の大きな原因になるのです。
純資産がプラスになってはじめて“資産”といえる
家が資産と呼べるかどうかは、「純資産」という指標で判断する必要があります。
具体的には、現在の住宅評価額から、住宅ローンの残債を差し引いたときにプラスになっている状態が、真の意味で「資産」といえる状態です。
ところが、購入直後の新築住宅は、販売価格に業者の利益が含まれており、引き渡しと同時に市場評価が下落します。
特に築10〜20年の間は純資産がマイナスになる傾向が強く、家を買った瞬間から“資産ではなく負債”を背負っている人も少なくありません。
「家を買えば自動的に資産になる」という考え方は、大きな誤解です。
所有しているだけでは資産ではない
資産という言葉には、「お金を生み出す」「換金できる」という機能が含まれます。
たとえば株や不動産投資物件のように、売ればお金になり、貸せば収入を生むものが本当の資産です。
一方、住宅ローンの残った持ち家は、換金できないどころか、固定資産税・修繕費などの維持コストが発生し続ける“消耗資産”になりかねません。
つまり、「所有=資産」というのは間違いだということです。
さらに、購入からしばらくの間は売却してもローンを完済できないケースも多く、急な転勤・離婚・介護などで住み替えが必要になっても身動きが取れない状態に陥るリスクがあります。
住宅ローン控除も“資産化”の根拠にはならない
「住宅ローン控除があるから得」と思っている人も注意が必要です。
たしかに一定期間、所得税や住民税の軽減措置を受けられるのは事実ですが、それは一時的な税優遇であり、家の資産価値とは関係ありません。
この制度を根拠に「得だから買う」という判断をしてしまうと、将来ローンが重荷となったときに想定外の損失や後悔を生むことになります。
家の資産性は「見える化」して把握する
自宅が資産かどうかを判断するには、定期的にその価値を把握しておくことが重要です。
たとえば、以下の方法が役立ちます。
こうした「資産価値の見える化」によって、自分の家の現在地がわかり、売却や住み替えの判断材料にもなります。
「家=資産」ではなく「家=消費+生活基盤」として考える
本来、住宅は生活の質を高めるための「支出」です。
その支出が将来、少しでも損失を減らせるようにするためにこそ、「資産性」という視点が必要なのです。
家を資産と信じて高額な住宅を買ってしまうと、のちに生活を圧迫しかねません。
反対に、「資産になりにくいもの」と理解して冷静に選べば、後悔のない住まい選びができるようになります。
特徴⑨家計管理ができていない人
住宅ローンは、数十年にわたる長期の返済計画が必要です。
そのため、家計管理ができていない人が家を買うのは、住宅ローン破綻の大きなリスクを抱えることになります。
支出の実態が見えていないと、ローン破綻のリスクが高まる
「毎月いくら使っているのか分からない」「なんとなくお金が足りなくなる」
このような状況では、ローン返済に無理が生じやすくなります。
住宅ローンを組む際、金融機関は「いくら借りられるか」で審査します。
しかし本当に重要なのは、自分の家計にとって“いくら返せるかという視点です。
目安としては、ローン返済額が手取り月収の25%を超えないことが望ましいとされています。
ところが家計管理ができていないと、その基準すら意識せず、借りられる上限ギリギリでローンを組んでしまう人が少なくありません。
その結果、教育費や急な出費に対応できなくなり、ローン破綻につながってしまうのです。
無駄な固定費に気づけない人は特に注意
家計管理が苦手な人ほど、保険・通信費・サブスクなどの“固定費”を見直せていない傾向があります。
これらの積み重ねは、年間で数万〜十数万円の支出になります。
家計に余裕がない状態でこれらを放置しておくと、ローン返済が少しのことで行き詰まる可能性が高くなります。
団信加入と生命保険の重複にも要注意
住宅ローンには、団体信用生命保険(団信)が付帯するのが一般的です。
これは、ローン契約者が死亡または高度障害となった場合、ローン残債が保険によって完済される制度です。
それにもかかわらず、既存の生命保険をそのままにしていると、保障が重複して保険料を二重に支払っている状態になってしまいます。
これは多くの家庭で見直しがされておらず、毎月数千〜数万円の無駄な支出につながっている可能性があります。
家を買う前には、団信の内容を確認し、不要な保険を解約・見直すことで、家計にゆとりを生み出すことができます。
家計管理は“我慢”ではなく“仕組み化”がカギ
家計を整えるには、無理な節約や我慢をする必要はありません。
むしろ大切なのは、支出を可視化し、仕組みで自動的に管理する体制をつくることです。
たとえば…
このような工夫によって、手間をかけずに支出を管理する習慣が身につきます。
家計が整えば、住宅ローンの返済も自然とコントロールしやすくなり、将来への不安を大きく減らすことができるのです。
特徴⑩住宅・お金の勉強をしていない人
「家は人生で一番高い買い物」とよく言われます。
にもかかわらず、住宅やお金の知識を身につけないまま家を買ってしまう人は、少なくありません。
このような姿勢は、ローン破綻や資産価値の低下といった、将来的な後悔を招く可能性が高まります。
知識がないと「間違った選択」をしてしまう
住宅の知識が乏しいまま購入を進めると、営業担当者の提案を鵜呑みにしやすくなります。
その結果…
など、あとから気づく“高額な失敗につながりかねません。
「知識がない人ほど、粗悪な家を高く買わされる」リスクが高まります。
「選べない人」は勉強していない人
住宅購入では、建物の構造・耐震・断熱・換気性能、保証内容、土地の将来性、資金計画など、検討すべき項目が多岐にわたります。
しかし勉強していないと、それぞれの違いを理解できず、比較検討する軸が持てません。
その結果、提示された選択肢の中から「なんとなく良さそう」という感覚で選んでしまい、後々トラブルや不満に繋がるケースが非常に多いのです。
勉強とは、「住宅会社を疑うこと」ではなく、「自分の価値観と目的に合うかを判断する準備」と言い換えることができます。
性能・構造の知識がないと「住んでから後悔」する
見た目や間取りばかりに目がいき、断熱性・耐震性・換気性といった“見えない部分”を理解せずに契約してしまう人も少なくありません。
その結果…
といった、暮らしの快適性に直結する悩みが後から噴出することになります。
こうした技術的な知識も、最低限のポイントを押さえておくだけで、大きな後悔を避けることができます。
コスパの良い住宅会社を選ぶには、知識が必要
勉強していない人は、住宅会社の広告や営業トークに頼るしかなくなります。
一方で、知識がある人は「建物の中身」で住宅会社を比較できるため、割高な大手よりも、実直でコスパの高い地元の工務店などを選べるようになります。
勉強している人なら、大手ではなく地場の優良住宅会社を見極められることができ、価格と品質のバランスを取るためにも、学ぶことが重要です。
お金の知識も欠かせない
住宅は、ローン・保険・税金といった“お金”の知識とも深く関係しています。
これらを理解していないと、数百万円単位の損失が発生することもあります。
知らなかったでは済まされない問題ばかりだからこそ、最低限の知識を身につけておくことが、家計と人生を守ることに直結するのです。
営業マンはあなたの人生の責任を取らない
最終的に家を買うのはあなた自身です。
住宅会社や営業担当者が、あなたの将来に責任を持ってくれることはありません。
だからこそ、納得できる判断をするために、住宅やお金について学ぶことが不可欠です。
学ぶことで、無駄な出費を減らせるだけでなく、将来の後悔も避けられるようになります。

まずは情報収集が大事!
タウンライフなら、ハウスメーカーがあなたオリジナルの間取りプランを「無料」で作ってくれるので、効率よく家づくりを進められるよ♪

\入力はわずか3分で完了/
最大で5社分の間取りを無料で取り寄せ可能!
特徴⑪他人のせいにしがちな人(他責思考)
住宅購入において、物件選びや資金計画を「誰かに任せきり」にするのは非常に危険です。
特に、うまくいかなかったときに「営業担当が悪い」「制度が悪い」と他人のせいにしてしまう人は、家を買うべきではありません。
他責思考は“学び”や“改善”を妨げる
住宅購入には数多くの判断が求められます。
立地、ローンの組み方、設備の選定、家の性能…。
その一つひとつに責任を持たず、誰かのせいにしてしまう人は、トラブルが起きたときに状況を改善する力が育ちません。
他責思考の人は住宅会社からも敬遠されやすいです。
なぜなら、責任を業者に押し付けやすく、のちのクレームやトラブルにつながる可能性が高いからです。
良い住宅会社は「自責思考の人」を選ぶ
信頼できる住宅会社ほど、家を建てる過程でのコミュニケーションや価値観の一致を大切にします。
「任せきり」「説明を聞いていない」「感情的なクレームが多い」といった態度は、良質な業者にとってもリスクです。
一方、自ら情報を集め、しっかりと質問し、納得の上で判断する人は、丁寧に対応され、良い提案を受けやすくなります。
住宅購入は、売る側だけでなく、買う側も“選ばれる立場”であることを意識する必要があります。
他責思考は住宅ローン破綻の引き金にもなる
他人のせいにする人は、住宅購入後に問題が起きても自ら家計を見直したり、支出を削減したりといった対処を後回しにしがちです。
たとえば…
このように考えていると、改善策を実行しないまま事態が悪化し、住宅ローン破綻に直結するリスクが高くなります。
住宅購入には“継続して支払っていく力”が欠かせません。だからこそ、自ら責任を持ち、早めに対策できる人である必要があるのです。
家族関係にも影響を与える
他責思考は、家計や夫婦関係にも悪影響を及ぼします。
こうした考え方が続くと、家庭内の空気は悪化し、ストレスがたまり、家そのものが居心地の悪い場所になってしまいます。
これは、住宅の性能や価格とは関係なく、“住む人自身の姿勢”が住み心地を左右する典型例です。
正解のない家づくりにこそ「自己決定」が重要
住宅選びに“絶対的な正解”はありません。
間取りも立地も、ローンもすべて、自分と家族にとってどうかが基準になります。
だからこそ、誰かの意見や判断に依存するのではなく、自分の価値観と目的をもとに選ぶ姿勢が求められます。
営業担当者も制度も、あなたの人生の責任を取ってはくれません。
納得できる住まいを手に入れるには、「自分で決める」覚悟を持つことが欠かせません。

まずは情報収集が大事!
タウンライフなら、ハウスメーカーの資料を無料で一括請求できるから、効率よく家づくりを進められるよ♪
ハウスメーカーを悩んでいるあなたへ。
タウンライフ家づくりで資料請求してみませんか?
無料で間取りプラン・見積もり・資金計画書を作成してくれます。

- 家づくりのアンケートに回答(約3分)
- ハウスメーカーを選ぶ(1,100社提携)
- 待つだけ!間取り・見積もりが届く!
特徴⑫ 稼ぐ覚悟がない人
家を買うということは、ローンを組み、長期にわたって安定した支払いを続けていく責任を負うということです。
この先、社会や働き方がどう変わるか分からない時代において、「今の収入で何とかなるだろう」と考えるのは極めて危険です。
もし、将来に向けて収入を高めていく意欲や行動がないのであれば、今はまだ住宅購入を検討すべきタイミングではありません。
住宅は「生活の基盤」ではあるが「必需品」ではない
マイホームには安心感や満足感がありますが、生活そのものに絶対必要なものではありません。
実際、賃貸住宅でも快適に暮らすことは可能です。
そのため、家を持つということは、より良い暮らしを自分で築いていくための“選択”であり、贅沢品に近い側面もあります。
だからこそ、それを維持するためには、「今のままで大丈夫か」ではなく、「将来どうやって支え続けていくか」を考える視点が必要です。
収入がずっと変わらないという前提は通用しない
経済環境や企業の体力、業界構造が変わりやすい今の時代において、将来の収入が確約されている人はごくわずかです。
ボーナスや昇給、退職金など、昔は当たり前だった制度も、今ではあっても減額されたり、廃止されることもあります。
そのような時代だからこそ、家を買った後も、変化に対応できるだけの稼ぐ力と意志が欠かせません。
買った直後に収入が減ることも、家族構成が変わることも、想定しておくべきリスクです。
「収入を上げる方法」はひとつではない
稼ぐといっても、何も起業や副業に飛び込む必要はありません。
まずは、本業で評価される働き方をする、資格やスキルを磨く、環境を変えるために転職を検討するなど、自分にできる範囲から始めればいいのです。
重要なのは、「どうにかなる」ではなく、「どうにかする」という姿勢を持てるかどうか。
この違いが、住宅ローンを無理なく返済し続けられる人と、途中で破綻してしまう人を分けるポイントになります。
社会に頼りすぎず、自分で変える意識を持つ
「給料が上がらない」「物価ばかり上がって苦しい」という声はよく聞かれます。
もちろん、経済や制度の影響はありますが、ずっとそれを嘆いていても、現実が大きく変わるわけではありません。
今できる工夫や努力を一つずつ積み上げていくことが、将来の家計と暮らしを安定させます。
そして、そうした積み重ねが、より良い住まいを持つための選択肢を広げることにもつながっていきます。
収入が増えれば、家の選択肢も広がる
今の収入だけで家を選ぼうとすると、「立地」「広さ」「仕様」など、どこかを妥協しなければならないこともあります。
一方で、これから収入を高める意識があるなら、今は少し待って、理想に近い住まいを目指すという選択も可能です。
無理に「今買うこと」を目的にせず、将来の安心や満足を重視して、家計と収入を整えることに時間を使う方が結果的に後悔しない買い物になります。

まずは情報収集が大事!
タウンライフなら、ハウスメーカーがあなたオリジナルの間取りプランを「無料」で作ってくれるので、効率よく家づくりを進められるよ♪

\入力はわずか3分で完了/
最大で5社分の間取りを無料で取り寄せ可能!
家は「不動産投資」と同じ視点で考えるべき理由
家は「住む場所」としてだけでなく、「資産」としての側面も持つものです。
そのため、購入時には感情だけで判断せず、将来の損得を見据えた“投資的な視点を持つことが欠かせません。
仮に一生住むつもりであっても、転勤や転職、介護、離婚など、思いがけない事情で家を「売る」または「貸す」必要に迫られる可能性は誰にでもあります。
だからこそ、買う段階で「もし手放すことになったら?」という視点を持っておくことが、後悔しない家づくりにつながります。
「売る」「貸す」ことを想定した購入がリスクを減らす
不動産市場には流動性の差があります。
立地や条件によっては、売却してもローン残高が下回る「オーバーローン状態」になったり、貸し出しても赤字になるケースがあります。
それを避けるには、出口戦略を持った家選びが重要です。
「住むためだけの家」として選ぶのではなく、「売るとき」「貸すとき」にどう評価されるかを想像しておくことが、いざという時の選択肢の広さに直結します。
売れる家・貸せる家の特徴とは?
資産としての価値が落ちにくい家には、共通するポイントがあります。
以下のような条件を意識して選ぶと、将来の売却・賃貸に強くなります。
これらは、将来的な「出口」に強い家の共通点です。
単に「自分たちが気に入る家かどうか」だけでなく、第三者からも評価されやすいかを意識しておくことが、将来の後悔を防ぎます。
中古住宅という選択肢も視野に入れる
住宅の価値は、特に新築のときに大きく下がる傾向があります。
購入直後から値下がりが始まり、10〜20年程度で建物評価は大幅に減少するのが一般的です。
一方で、中古住宅(特に築15〜25年)であれば、価格の下落が落ち着いているため、資産としてのリスクが少なく、購入後に損をしにくいというメリットもあります。
リフォームやリノベーションを組み合わせることで、新築と遜色のない暮らしを手に入れながら、コストを抑える選択も可能です。
感情と経済合理性、どちらも大切にする視点を
家は人生で最も高額な買い物のひとつです。
「家族との時間を大切にしたい」「理想の空間で暮らしたい」といった感情も、もちろん大切です。
しかし、それだけで決めてしまうと、将来的に選択肢が狭まり、経済的な不安や制約を抱えることにもなりかねません。
だからこそ、家を買うときには「住み心地」だけでなく、「出口戦略」「将来の資産性」まで含めて考える。
このバランス感覚こそが、後悔しない住宅購入のカギになります。

まずは情報収集が大事!
タウンライフなら、ハウスメーカーがあなたオリジナルの間取りプランを「無料」で作ってくれるので、効率よく家づくりを進められるよ♪

\入力はわずか3分で完了/
最大で5社分の間取りを無料で取り寄せ可能!
住宅ローン破綻の実例から学べること
住宅ローンの破綻と聞くと、自分には関係のない話だと思うかもしれません。
しかし、実際には「まさか自分が」と語る人がほとんどであり、誰にとっても起こりうる現実的なリスクです。
家を買うときは、今の収入と支出を基に計画を立てがちですが、破綻の多くは“想定外の出来事”への備えがなかったことに起因します。
よくある破綻の原因とその背景
住宅ローンが返せなくなる原因には、以下のような事例が多く見られます。
- 離婚により収入が半減し、片方が支払えなくなった
- 病気やケガで長期間働けず、収入が途絶えた
- リストラや給与カットにより、家計が急激に悪化した
- 独立・起業後に想定ほど収入が伸びず、返済に行き詰まった
- 親の介護や子どもの教育費が想定以上にかかり、生活費を圧迫した
たとえば、40代で都心にマイホームを購入した会社員夫婦は、夫の転職による年収ダウンとボーナスカットが重なり、
3年後にはローン返済が困難に。最終的にやむなく家を手放すことになりました。
このように、「買ったときは問題なかった」のに、少しの変化が大きな破綻に直結するケースは少なくありません。
「うちは大丈夫」という思い込みが最大のリスク
破綻する人に共通しているのは、「まさか自分が」と思っていた点です。
- 正社員だから大丈夫
- 共働きだから安定している
- ボーナスが毎年出ているから返せる
このような思い込みに基づいた計画は、一つでも前提が崩れると一気に脆さを露呈します。
変化を前提としない返済計画は、住宅ローンという長期契約においては大きな落とし穴となるのです。
破綻を防ぐために今できる対策とは
完璧な未来予測はできません。だからこそ、「もしも」に備えて計画に余白を持たせることが大切です。
- 月々の返済額は年収の25%以下を目安にする
- ボーナス返済には頼らない
- 貯金を残した状態で購入する(頭金を入れすぎない)
- 万が一収入が減っても半年は生活できる資金を確保する
- 転職・育児・介護などのライフイベントを事前にシミュレーションする
これらを意識しておくだけで、生活環境が変わっても柔軟に対応でき、ローン返済の継続性を高めることができます。
想定外に強い計画が、人生の安定を支える
住宅ローンを組むということは、将来にわたる返済責任を背負うことです。
だからこそ、「今が大丈夫」ではなく、「将来変化があっても耐えられるかどうか」が重要な判断軸になります。
想定外をすべて防ぐことはできませんが、備えることはできます。
自分たちの生活を守るためにも、余裕を持った返済計画を立てることが、住宅購入を成功へと導く鍵になるのです。

まずは情報収集が大事!
タウンライフなら、ハウスメーカーの資料を無料で一括請求できるから、効率よく家づくりを進められるよ♪
ハウスメーカーを悩んでいるあなたへ。
タウンライフ家づくりで資料請求してみませんか?
無料で間取りプラン・見積もり・資金計画書を作成してくれます。

- 家づくりのアンケートに回答(約3分)
- ハウスメーカーを選ぶ(1,100社提携)
- 待つだけ!間取り・見積もりが届く!
逆に家を買ってもいい人の特徴とは?
ここまで「家を買ってはいけない人の特徴」について解説してきましたが、
その一方で、しっかりとした備えと視点を持っていれば、家を購入しても問題のない人もいます。
マイホーム購入は人生の転機であると同時に、大きな責任を伴う意思決定です。
以下のような特徴を持つ方であれば、住宅ローンや将来の変化にも柔軟に対応でき、安心して家を持つ選択ができるでしょう。
安定した収入と生活防衛資金がある
最も重要なのは、長期的に安定した収入があり、万が一の事態にも備えられる貯蓄があることです。
住宅ローンは数十年にわたる契約です。一時的な勢いや短期の収入見込みで判断すべきものではありません。
目安としては、
- 住宅ローンの返済額が手取り月収の25%以下
- 購入後も半年から1年分の生活費に相当する貯蓄が残る状態
この条件を満たしていれば、収入が一時的に減少しても生活を維持しやすくなります。
資産性や立地を重視して家を選べる
感情だけで家を選ぶのではなく、将来の資産価値まで見据えて判断できる人は、マイホームを「資産」として活用できます。
具体的には、
- 駅から徒歩10分圏内など立地にこだわる
- 流動性のあるエリアを選び、「貸す・売る」可能性を考慮する
- 新築信仰にこだわらず、中古+リフォームも選択肢に入れる
また、「家は資産ではなく負債である」という考え方を理解し、そのうえで負債を最小限に抑える選択ができる人は、住宅購入後に後悔するリスクを減らせます。
住宅ローンの仕組みを理解し、活用できる
住宅ローンは「借金」ですが、うまく活用すれば資金繰りに役立つツールにもなります。
金融リテラシーが高く、金利のしくみや返済計画の柔軟性を理解している人は、住宅ローンとの付き合い方にも余裕があります。
たとえば、
- 繰上返済に固執せず、手元資金の流動性を維持できる
- ボーナス返済に依存せず、収入減リスクにも備える
- ローン控除や住宅取得支援策を活用できる
このように、ローンを“ただ返すだけ”ではなく、“戦略的に使いこなす”姿勢がある人も、家を買ってよい人の条件に当てはまります。
自ら学び、判断し、行動できる
家の購入は専門用語も多く、わからないまま進めると高額なミスにつながります。
自分で調べ、正しい情報を集めたうえで判断できる人は、住宅会社の営業トークや流行に流されにくくなります。
このように、“人任せ”ではなく“自分の責任で決める姿勢”を持つことが、家を買って後悔しないための土台になります。
家族と将来の暮らしを明確に描けている
家は、今の暮らしだけではなく、10年後・20年後のライフプランに合うかどうかも重要です。
家族の変化や転勤の可能性などを見越して判断できる人は、長く満足できる住まいを手にすることができます。
将来の暮らし方を想像し、それに合った家を計画できる人は、購入後も慌てて住み替えたりするリスクを減らせます。

まずは情報収集が大事!
タウンライフなら、ハウスメーカーの資料を無料で一括請求できるから、効率よく家づくりを進められるよ♪
ハウスメーカーを悩んでいるあなたへ。
タウンライフ家づくりで資料請求してみませんか?
無料で間取りプラン・見積もり・資金計画書を作成してくれます。

- 家づくりのアンケートに回答(約3分)
- ハウスメーカーを選ぶ(1,100社提携)
- 待つだけ!間取り・見積もりが届く!
まとめ
この記事では、「家を買ってはいけない人の特徴12選」を取り上げ、それぞれの背景や注意点についてご紹介してきました。
中でも、特に意識したいポイントは以下の3つです。
ひとつでも当てはまる点があるなら、今はまだ購入を慎重に見直す時期かもしれません。
マイホームは焦って手に入れるものではなく、備えが整ってこそ「買ってよかった」と思えるものです。
安定した収入や貯金だけでなく、物件選びの視点や、将来を見通す力も大切です。
後悔のない家づくりを目指すなら、いま一度、ご自身の状況や考え方を振り返ってみてはいかがでしょうか。

まずは情報収集が大事!
タウンライフなら、ハウスメーカーの資料を無料で一括請求できるから、効率よく家づくりを進められるよ♪
ハウスメーカーを悩んでいるあなたへ。
タウンライフ家づくりで資料請求してみませんか?
無料で間取りプラン・見積もり・資金計画書を作成してくれます。

- 家づくりのアンケートに回答(約3分)
- ハウスメーカーを選ぶ(1,100社提携)
- 待つだけ!間取り・見積もりが届く!