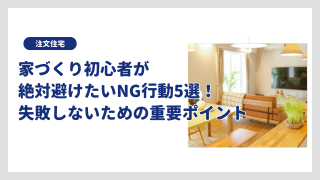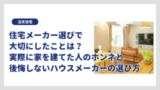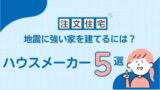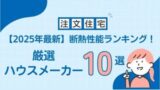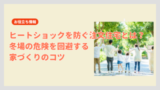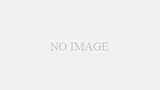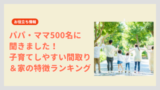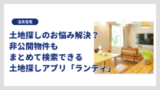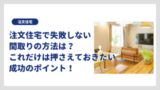家づくりで失敗したくないというのは、初めての方にとって特に強く感じることですよね。
でも、意外と気づかないうちにやってしまいがちなNG行動がいくつかあるんです。
たとえば、間取りの計画で迷ったり、収納スペースを作りすぎたり…。
家づくりは一生に一度の大きなイベントだからこそ、しっかり成功させたいですよね。
今回の記事では、そんな家づくり初心者さんに向けて、「これだけは絶対避けて!」というNG行動5つを紹介します。
この記事を読むことで、家づくりで失敗しないためのポイントがわかりますし、「ああ、あの時知っておけば…」と後悔することもなくなります。
実際に、これまでに多くの人が経験した失敗談も交えながら、成功するためのコツをお伝えします。
ぜひ最後までお付き合いくださいね!
- 家づくりで注意すべき5つのNG行動とその理由
- 失敗を防ぐための対策とアドバイス
- 理想の家づくりを成功させるために必要な心構えと基本知識
注文住宅で失敗しないための基本知識【耐震・断熱・換気】
注文住宅は一生に一度の大きな買い物。しかし、デザインや間取りばかりに気を取られ、住宅の本質である「耐震性」「快適性」「エネルギー効率」を見落としてしまうケースが少なくありません。
「おしゃれな家を建てたのに、冬は寒くて光熱費がかさむ…」
「地震が起きた時に、自分の家は本当に安全なのか不安…」
こうした後悔を防ぐためには、「頑丈かつ健康で快適な家」を作ることが最も重要です。
そのために押さえておくべき基本知識を、この記事で詳しく解説します。

家づくりは、まず性能を優先することが大切です!
住宅の頑丈さとは?
頑丈な家とは、「見た目がしっかりしている家」ではなく、「地震に強く、長期にわたって安全に暮らせる家」を指します。
日本は地震大国であり、大きな地震が発生するリスクを考えれば、住宅の耐震性は最優先で考えるべきポイントです。
では、どのような家を建てれば地震に強いのか? ここでは、そのポイントを詳しく解説します。
耐震等級3の重要性
「耐震等級3」という言葉を聞いたことはありますか?
「耐震等級3」は建築基準法で定められている耐震性能の指標で、最も高いレベルの耐震性を示します。
具体的には、震度6〜7の1.5倍の地震に耐えられる構造になっており、消防署や警察署などの防災拠点と同等の強度を持っています。
近年の大地震では、耐震等級3の住宅は被害が少なかったというデータもあり、家族を守るためにも、この基準を満たす住宅を選ぶことが重要です。
木造と鉄骨の違いと選び方
「木造と鉄骨、どちらが地震に強いのか?」これは多くの人が気になるポイントです。
実は、耐震性に関しては、木造でも鉄骨でも 「耐震等級3をクリアしているかどうか」 が重要であり、構造の違い自体は大きな問題ではありません。
では、どのように選べばよいのか? それは家を建てる立地条件に注目すると答えが見えてきます。
- 都心部や住宅密集地では鉄骨住宅が有利
→ 隣家との距離が近く、隣の建物の倒壊リスクがあるため、強度の高い鉄骨が安心。 - 敷地に余裕があるエリアでは木造住宅が適している
→ 木は鉄に比べて断熱性が高く、温度変化が少ないため快適性に優れている。
要するに、「どちらが優れているか?」ではなく、「建てる場所に適しているか?」が大事なのです。
健康な住宅をつくるポイント
住まいの快適性は、単に間取りやデザインの問題ではありません。
「室内の温度・湿度を適切に保ち、健康的に暮らせる家」を作ることが、長期的な満足度を大きく左右します。
そのために欠かせないのが、高気密・高断熱の住宅づくりです。
高気密高断熱がなぜ必要か?
「夏は涼しく、冬は暖かい家に住みたい」これは誰もが望むことですが、実際にそうした快適な環境を実現するには、高気密高断熱の家づくりが必須になります。
なぜなら、室内の温度が安定しないと、体調を崩す原因になりやすいからです。
- 気温の変化が激しいと、風邪を引きやすい
- 寒暖差が大きいと、高齢者のヒートショックのリスクが高まる
- 湿気が多いと、カビやダニが発生しやすく、アレルギーの原因になる
つまり、家全体の温度と湿度を一定に保つことが、健康的な住まいの条件なのです。
断熱→気密→換気→空調の順で考える
高気密高断熱の住宅を作るには、以下の順番で考えることが大切です。
- 断熱:外気の影響を受けにくいようにする
- 気密:家の隙間を減らし、温度管理をしやすくする
- 換気:計画的に空気の流れを作り、湿気や汚れた空気を排出する
- 空調:最小限のエネルギーで快適な温度を維持する
この順番を間違えると、どれだけ高価な空調設備を導入しても「夏は暑く、冬は寒い家」になってしまいます。
断熱材の厚みと窓の選び方
2022年10月に、断熱等級が「4」から「7」まで引き上げられました。
これにより、北海道基準の高断熱住宅を本州でも求められる時代になっています。
特に窓の性能は重要で、熱の70%以上は窓から出入りすると言われています。そのため、アルミサッシではなく、樹脂サッシやトリプルガラス窓を選ぶことで、家全体の断熱性能を大幅に向上させることができます。
C値1.0以下を目指す理由
「C値(気密性能の指標)が1.0以下なら合格」と言われる理由は、エネルギー効率と快適性の両方を確保できるラインだからです。
C値が悪いと、せっかく暖房や冷房をかけても空気が隙間から漏れてしまい、光熱費が無駄にかかることになります。
例えば、C値が4.0の家では、1時間で30%の室内空気が勝手に入れ替わってしまうため、効率が非常に悪くなります。
都心部の住宅密集地なら、周囲の建物が防風壁の役割を果たし、C値が少し悪くても影響を受けにくいですが、基本的にはC値1.0以下を目指すことが、快適な住まいづくりの最低条件となります。
注文住宅を成功させるには、耐震性能と快適性をしっかり考慮することが不可欠です。
この基本を押さえておけば、後悔のない家づくりができるはずです。

まずは情報収集が大事!
タウンライフなら、ハウスメーカーの資料を無料で一括請求できるから、効率よく家づくりを進められるよ♪
ハウスメーカーを悩んでいるあなたへ。
タウンライフ家づくりで資料請求してみませんか?
無料で間取りプラン・見積もり・資金計画書を作成してくれます。

- 家づくりのアンケートに回答(約3分)
- ハウスメーカーを選ぶ(1,100社提携)
- 待つだけ!間取り・見積もりが届く!
家づくりで避けたいNG行動とは?

家づくりを進める中で、思わぬ失敗に陥ることがあります。
特に、初めて家を建てる方にとって、知らないうちにやってしまうNG行動は、後悔のもとになりがちです。
ここでは、初心者が気をつけたい失敗例を具体的に挙げていきます。
これを読めば、後悔しない家づくりの一歩を踏み出せるはずです。
NG行動1: 間取りにこだわりすぎる
家づくりを始めると、多くの人が理想の間取りにこだわります。
しかし、間取りにあまりにも固執すると、家全体のバランスが崩れる原因になります。
例えば、「リビングは20畳以上ほしい」といった具体的な要望を最優先してしまうと、他の部屋が狭くなったり、動線が悪くなることがあります。
こうした配置の偏りは、日常の生活の利便性を大きく損なう可能性があります。
また、広いリビングを確保したことで他の重要なスペースが削られ、家全体の使い勝手が悪くなることもあります。

間取りにこだわりすぎると、住みにくい家になってしまいます!
間取りにこだわりすぎると起こる問題
間取りのこだわりが強すぎると、かえって住みにくい家になってしまうことがあります。
特に、デザインや広さを優先しすぎた結果、生活動線が悪化したり、収納スペースが不足したりするケースが多いです。
また、間取りの変更が増えるほど建築コストも膨らみやすく、結果的に予算オーバーを引き起こす可能性もあります。
生活動線が悪くなり、住みにくい家になる
間取りの理想を追求するあまり、実際の生活を考えた動線が二の次になってしまうことがあります。
例えば、キッチンとダイニングが離れすぎていると料理の配膳が面倒になり、家事の効率が大幅に低下する可能性があります。
また、トイレや浴室の位置によっては、夜中に家族が目を覚ましてしまうような騒音問題が発生することも。実際に暮らし始めたときの動線を考慮しながら間取りを決めることが重要です。
収納不足やデッドスペースが生まれる
間取りにこだわりすぎると、収納スペースが後回しになり、実際に住んでみると収納不足に悩まされることがあります。
例えば、吹き抜けを大きく取りすぎた結果、収納スペースが確保できず、生活感が出やすい家になってしまうこともあります。
また、こだわりの強い間取りにすると、部屋の形が複雑になり、使いづらいデッドスペースが増えてしまうことがあります。こうしたスペースは活用しにくく、結果的に無駄な空間が生まれる原因になります。
建築コストが想定以上に膨らむ
自由設計の注文住宅では、間取りの変更が増えるほど設計・施工の手間がかかり、追加コストが発生しやすくなります。
特に、以下のようなケースでは費用が大きく増える傾向があります。
- 複雑な形状の間取りにする(建築コストが上がる)
- 水回りの位置を分散させる(配管工事のコストが増える)
- 吹き抜けを大きくする(冷暖房効率が悪くなり、光熱費も増加)
注文住宅では、こだわればこだわるほどコストが増えるため、予算内でバランスの取れた間取りを考えることが重要です。
適切な間取りを決めるためのポイント
住みやすい家をつくるためには、間取りを考える際にいくつかのポイントを押さえておくことが大切です。
デザインだけにとらわれず、実際の生活を想像しながら間取りを決めることで、快適で機能的な住まいを実現できます。
生活動線を最優先に考える
家の間取りを決める際には、デザインや広さよりも、実際にどのように生活するのかをイメージすることが重要です。
例えば、以下のような動線を意識すると、家の使いやすさが大きく向上します。
- 家事動線:キッチン、洗面所、ランドリールームの距離を近くする
- 生活動線:玄関からリビング、各部屋までスムーズに移動できるようにする
- 子育て動線:リビングから子ども部屋が見えるようにする
特に家事動線が悪いと、毎日の家事にかかる負担が増えるため、しっかりと検討することが大切です。
収納スペースを計画的に配置する
収納は後から増やすことが難しいため、間取りを決める段階でしっかりと計画する必要があります。
- 各部屋に適切な収納を確保する(必要な場所に収納を作る)
- ウォークインクローゼットやパントリーを活用する(収納効率を上げる)
- デッドスペースを減らす(使いやすい収納設計をする)
収納が不足すると、生活感があふれやすくなり、スッキリした家を維持するのが難しくなります。
コストとバランスを考えて間取りを決める
間取りを決める際は、「どこにこだわるべきか」「どこをシンプルにすべきか」を明確にすることが大切です。例えば、
- 家族が長く過ごすリビングにはこだわる
- 水回りの配置をまとめてコストを抑える
- 吹き抜けや特殊な形状の部屋は慎重に検討する
間取りの自由度が高いからこそ、メリハリをつけた設計が、コストを抑えながら住みやすい家を作るポイントになります。
NG行動2: 収納スペースを作りすぎる
多くの人が「収納は多いほうが良い」と考えがちですが、これは必ずしも正解ではありません。
収納スペースを過剰に作ると、その分だけ建設コストが増加します。
また、収納が多すぎると、不要なものをため込んでしまい、結果的に使わないスペースが増えてしまいます。
こうした無駄なスペースは、家全体のレイアウトに影響を与え、効率の悪い動線を生む原因にもなります。
さらに、収納に使われたスペースが他の重要な生活空間を圧迫する可能性もあります。

収納が多すぎると、生活空間が狭くなってしまいます!
収納スペースが多すぎると起こる問題
収納が多いことは一見便利に思えますが、必要以上に収納を増やすことで思わぬデメリットが生じることがあります。
限られた床面積の中で収納を増やしすぎると、居住スペースが圧迫されたり、かえって使い勝手が悪くなるケースも少なくありません。
居住スペースが狭くなる
収納を増やせば増やすほど、その分だけ居住空間が圧迫されます。
例えば、収納率(家の床面積に対する収納スペースの割合)が高くなりすぎると、リビングや寝室が狭くなり、快適性が損なわれる可能性があります。
収納率の目安は一般的延床面積の12〜15%程度が適切とされており、これを大幅に超えるとバランスが悪くなります。
デッドスペースが生まれる
収納は「作れば使うもの」ですが、使い勝手が悪い収納は逆にデッドスペース化しやすいです。
例えば、奥行きが深すぎるクローゼットや、アクセスしづらい天井裏収納などは、物を入れても取り出しにくくなり、結果的に使われないスペースになりがちです。
収納に余裕があると、不要な物が増える
収納が多すぎると、本来は不要な物を捨てるタイミングを逃しやすくなるというデメリットがあります。
収納が限られている場合は、定期的に整理し不要なものを処分する習慣が生まれますが、収納が豊富すぎると「とりあえずしまう」ことで物が増え続け、結果的にスペースが圧迫されることになります。
収納スペースを適切に確保するためのポイント
収納を適切な量・場所に確保することが、住みやすい家づくりのカギとなります。
ただ広く作るだけではなく、「どこに」「何を」収納するのかを計画的に考えることが重要です。
収納量は「生活スタイル」に合わせて決める
適切な収納量は、家族構成やライフスタイルによって異なります。例えば、ミニマリスト志向の家庭では収納は最小限で済む一方で、趣味の道具が多い家庭では十分な収納が必要になります。
収納計画を立てる際には、「何を」「どこに」「どのくらい収納するか」を事前に整理し、具体的なリストを作成すると良いでしょう。
使いやすい収納を意識する
収納は、量だけでなく「使いやすさ」が重要です。
適切な収納スペースを作るために、以下の点を意識しましょう。
- 取り出しやすい高さに配置する(手の届かない収納は使わなくなる)
- 奥行きを適切にする(クローゼットや押し入れは奥行き60cm前後が理想)
- 動線を考えて配置する(キッチンの近くにパントリー、玄関にシューズクロークなど)
将来の生活変化を見越して柔軟な収納を作る
子どもが成長すると物が増えたり、逆に独立後は収納が余ることがあります。そのため、将来の変化に対応できるような収納設計が重要です。
例えば、可動棚を設けたり、間仕切りを使って収納スペースを変更できるようにするのも一つの方法です。
NG行動3: 自分で土地探しをする
家づくりを始める際、多くの人が「まずは土地を探そう」と考えがちです。
しかし、自己流で土地を探すことは大きなリスクを伴います。
特に、土地探しの初心者が陥りやすい失敗として、不動産業者に個人情報を渡してしまうことや、土地と家のバランスを考えずに購入してしまうことが挙げられます。

土地探しはハウスメーカーと一緒に進めるのが安全です!
不動産業者に個人情報を渡すと価格を吊り上げられるリスク
土地を探す際、多くの人は不動産会社に問い合わせをします。
しかし、ここで安易に「購入希望の意思」や「予算」などの個人情報を伝えてしまうと、価格が吊り上げられるリスクがあります。
例えば、以下のようなケースが考えられます。
不動産業者もビジネスであり、できるだけ高く売りたいと考えるのは当然のこと。「この人は本気で購入を考えている」と判断されると、交渉の余地がなくなり、相場よりも高い価格で契約させられることも少なくありません。
まずはハウスメーカーを決め、土地探しを一緒にする方が安全
「では、どうすれば適正価格で良い土地を購入できるのか?」
答えはシンプルで、先にハウスメーカーを決めてから土地探しをすることです。
その理由は以下の通りです。
- ハウスメーカーが土地選びのプロだから
→ 耐震性や建築コストを考慮した土地の選び方を知っているため、不適切な土地を避けられる。 - 建築費用とのバランスを考えながら土地を選べる
→ 土地に予算を使いすぎて、家のグレードを落とすことになるのを防げる。 - ハウスメーカーが業者と直接交渉するため、価格の吊り上げを防げる
→ プロの視点で交渉できるので、初心者が不利な条件で契約するリスクが減る。
実際、ハウスメーカーと一緒に土地を探すことで、条件に合った土地を適正価格で購入できるケースが多いのです。

まずは情報収集が大事!
タウンライフなら、ハウスメーカーの資料を無料で一括請求できるから、効率よく家づくりを進められるよ♪
ハウスメーカーを悩んでいるあなたへ。
タウンライフ家づくりで資料請求してみませんか?
無料で間取りプラン・見積もり・資金計画書を作成してくれます。

- 家づくりのアンケートに回答(約3分)
- ハウスメーカーを選ぶ(1,100社提携)
- 待つだけ!間取り・見積もりが届く!
NG行動4: 無計画な窓の設置
窓は住宅のデザインや採光・通風を左右する重要な要素ですが、設置を誤ると快適性や住宅性能を大きく損なう原因になります。
特に、注文住宅を建てる際に「デザインを優先して窓を増やしすぎる」「間取りとのバランスを考えずに配置する」などの失敗がよく見られます。

窓の配置を間違えると、快適に暮らせなくなりますよ!
デザイン重視で窓を増やすと、断熱性能が大幅に低下する
「大きな窓があると開放感が出る」「おしゃれなデザインにしたい」という理由で、必要以上に窓を設置すると住宅の断熱性能が大幅に低下してしまいます。
実際、住宅における熱の出入りの約70%は窓から発生しているとされており、窓の性能が低いと夏は暑く、冬は寒い家になりやすいのです。
窓の配置ミスによる具体的なデメリット
- 夏場は窓から74%もの熱が室内に流入し、冷房効率が悪くなる
- 冬場は窓から50%もの熱が逃げてしまい、暖房をつけても室内が暖まりにくくなる
- 必要以上に窓が多いと壁が少なくなり、家の耐震性が低下する
- 隣家との距離を考えずに設置すると、プライバシーが確保できない
このように、デザインを優先して窓を増やしすぎると、住みにくい家になってしまうのです。
断熱性能の低い窓を選ぶと快適性が損なわれる
日本の一般的な住宅では、【アルミ樹脂複合サッシ】と呼ばれる、外側がアルミで内側が樹脂の窓がよく使われています。
しかし、このタイプの窓は断熱性能が低く、冷暖房の効率を大きく下げる原因になります。
なぜアルミ窓は問題なのか?
- アルミは熱を伝えやすい素材であり、外気温の影響を室内に伝えてしまう
- 結露が発生しやすく、カビやダニの原因になる
- 冬場は冷気が入り込み、夏場は熱気がこもるため冷暖房コストが上がる
海外ではほとんどの住宅が「オール樹脂サッシ」を採用しており、日本の住宅の窓性能は遅れを取っているのが現状です。例えば、ハンガリーではコンテナハウスですら樹脂サッシが使われているほどです。
住宅の快適性を高めるためには、アルミ樹脂複合サッシではなく、オール樹脂サッシの窓を採用するのが理想です。
最適な窓の配置と選び方
窓の設置を失敗しないためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
- 窓の数は最小限にする
- 必要以上に大きな窓を設置しない
- 採光や通風を考慮しつつ、断熱性能を優先する
- 窓の種類を適切に選ぶ
- オール樹脂サッシ + トリプルガラスを選ぶと、断熱性能が大幅に向上する
- 省エネ性の高い窓を選ぶことで、冷暖房費を削減できる
- 窓の向きと配置を計算する
- 夏場の日射を遮るために、南面には軒や庇を設置する
- 西日が入る西側の窓は小さくするか、遮熱対策を行う
窓の設置は、デザイン性だけでなく、住宅の性能や住み心地を大きく左右する要素です。間取りの計画段階でしっかりと考慮し、無計画に窓を増やさないよう注意しましょう。
NG行動5: 予算オーバーを招く仕様変更
注文住宅の打ち合わせが進むにつれて、「せっかくならここもグレードアップしたい」「オプションを追加したい」といった希望が増えてしまい、気づいたら当初の予算を大幅にオーバーしていたというケースはよくあります。
仕様変更は、快適な住まいを作るうえで重要な判断ですが、無計画に変更を重ねると、最終的な建築費が数百万円単位で膨らむことも珍しくありません。

仕様変更を繰り返すと、予算オーバーになってしまいます!
なぜ仕様変更で予算オーバーが起こるのか?
注文住宅の打ち合わせが始まると、カタログやショールームで魅力的なオプションや高級仕様を見せられる機会が増えます。
営業担当者や設計士から「この設備は快適ですよ」「将来的に便利ですよ」と提案されると、つい取り入れたくなってしまうものです。
しかし、個々のオプションは数万円〜数十万円程度でも、小さな追加を積み重ねることで、最終的なコストは数百万円単位に膨らんでしまうのです。
仕様変更でコストが膨らむ具体例
- キッチンのグレードアップ(+30万円〜100万円)
- 浴室の広さ変更や機能追加(+20万円〜80万円)
- 外壁や屋根材の変更(+50万円〜200万円)
- 床材や建具のアップグレード(+30万円〜100万円)
- 造作家具や収納の追加(+50万円〜150万円)
こうした仕様変更が重なると、最初の見積もりから簡単に300万円〜500万円の予算オーバーが発生してしまうのです。
予算オーバーを防ぐためのポイント
仕様変更を繰り返すと、住宅の建築費は簡単に数百万円単位で膨らんでしまうため、最初からしっかり計画を立てることが重要です。
仕様変更の優先順位を決める
すべてをグレードアップするのではなく、本当に必要な部分だけ仕様変更をすることが重要です。
特に、次の2点に絞って優先順位を決めましょう。
- 住宅の性能に関わるもの(耐震・断熱・気密・換気)
- 生活の利便性やランニングコストに直結するもの(省エネ設備・収納計画)
「デザイン性」や「贅沢な設備」は、予算が余った場合に考えるくらいの気持ちでいると、無駄な出費を防げます。
住宅の仕様は最初の契約段階でしっかり決める
仕様変更が多くなるほど、追加費用が割高になりやすいため、最初の契約段階で可能な限り決定しておくことが重要です。
また、仕様変更のタイミングが遅れると、施工が始まった後に変更を加えることになり、工事のやり直し費用まで発生してしまうこともあります。
予算の「余白」を確保しておく
どれだけ計画的に進めても、打ち合わせを進めるうちに想定外の出費が発生することがあります。
そこで、あらかじめ全体予算の5〜10%を「予備費」として確保しておくと、急な仕様変更にも対応しやすくなります。
例えば、総予算4,000万円の住宅なら、200万円〜400万円程度の余裕を持つことで、仕様変更が発生しても大きな問題になりにくくなります。
まとめ
この記事では、家づくり初心者がついやってしまいがちなNG行動についてお伝えしました。
家を建てるのは一生に一度の大きなイベント。
だからこそ、失敗しないためにしっかり準備しておきたいですよね。
ここで改めて、今回のポイントを振り返ってみましょう。
これらのポイントを押さえておけば、家づくりでの失敗をぐっと減らすことができます。
家づくりは大変なことも多いけれど、同時にとてもワクワクするプロジェクトでもありますよね。
理想の住まいを手に入れるために、焦らず一歩ずつ進めていきましょう。
そして何より大切なのは、家づくりの過程を楽しむこと。完璧を目指すよりも、自分たちのライフスタイルに合った家をつくることが一番です。
そうすれば、新しいお家での生活がきっともっと素敵なものになるはずです。
あなたの家づくりが素晴らしいものになりますように!

まずは情報収集が大事!
タウンライフなら、ハウスメーカーの資料を無料で一括請求できるから、効率よく家づくりを進められるよ♪
ハウスメーカーを悩んでいるあなたへ。
タウンライフ家づくりで資料請求してみませんか?
無料で間取りプラン・見積もり・資金計画書を作成してくれます。

- 家づくりのアンケートに回答(約3分)
- ハウスメーカーを選ぶ(1,100社提携)
- 待つだけ!間取り・見積もりが届く!