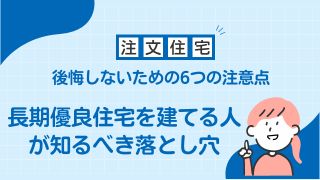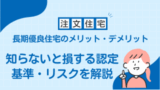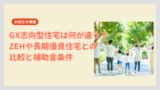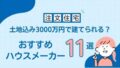家づくりを考え始めたとき、「長期優良住宅なら安心」と感じる方も多いのではないでしょうか。
一定の基準を満たすことで補助金や税制優遇を受けられるなど、お得な制度として注目されています。
ですがその一方で、「認定を取って安心していたのに、後から想定外の費用や制限に悩まされた」という声も少なくありません。
実は長期優良住宅には、建てる前に知っておきたい見落とされがちな注意点がいくつかあるのです。
この記事では、長期優良住宅に潜む6つの落とし穴と、後悔しないための判断ポイントをわかりやすく解説していきます。
長期優良住宅とはどんな制度なのか
家を建てるときに「長期優良住宅にするかどうか」は、大きな判断ポイントのひとつです。
この制度は、国が定めた基準をクリアした住宅に対して、さまざまな優遇措置を与えるというものです。
では、長期優良住宅とは具体的にどのような制度なのでしょうか。
長期優良住宅の基本的な定義と目的
長期優良住宅とは、長く安心して住める家を増やすために国がつくった制度です。
耐久性や省エネ性、維持管理のしやすさなど、一定の基準を満たした住宅が「長期優良住宅」として認定されます。
この制度の目的は、ひとことで言えば「いい家を建てて、長く大切に使いましょう」という考え方を広めることです。
認定に必要な9つの要件
長期優良住宅として認められるには、以下の9つの条件を満たす必要があります。
この9つを満たし、書類を作成して所管行政庁に申請・認定されると「長期優良住宅」として認められます。
制度で得られる主なメリット
長期優良住宅の認定を受けると、次のようなメリットがあります。
こうした制度面のメリットがあるため、建築会社や不動産会社でも長期優良住宅を推奨することが増えています。

「長期優良住宅は“書類上だけの制度”ではなく、建て方そのものが変わってきます。
性能や維持の面で、基準を満たすための設計が必要になるんです。
このように、長期優良住宅は制度上のメリットが多く、一見すると「選ばない理由がない」と思われがちです。
後悔しないために知っておきたい6つの落とし穴
長期優良住宅にはたくさんのメリットがある一方で、実際に建てた方の中には後悔したという声もあるのが事実です。
ここでは、特に見落とされやすい6つの注意点を、順を追ってわかりやすくご紹介します。
建築費用が高くなりやすい
長期優良住宅の認定を受けるには、耐震性や断熱性などで定められた性能基準を満たす必要があります。
そのため、一般的な住宅に比べて建築費が100万円〜200万円前後高くなるのが実情です。
また、構造計算や省エネ計算、維持管理計画などの書類作成費用も別途発生します。
これらの追加費用は必須であり、予算を組む段階で明確に把握しておく必要があります。
「長期優良住宅なら補助金も出るし得」と思っていたのに、初期費用が想定以上に膨らんでしまったという例も少なくありません。
着工までに時間がかかる
長期優良住宅を建てるには、通常の建築確認申請に加えて、認定のための申請手続きを行う必要があります。
この過程には1〜2ヶ月程度の追加期間が必要です。
さらに、サッシのサイズや設備仕様などを変更すると再申請が必要になるため、打ち合わせや決定の自由度も制限されます。
家づくりのスケジュールは確実に延びると考えておくべきです。
実は“最高性能の家”とは限らない
長期優良住宅という名前から「とても高性能な家」と思われがちですが、実際には断熱等級5、耐震等級3が基本です。
現在は断熱等級6や7、HEAT20といったさらに上位の基準が存在しており、
等級5では「今の住宅の中でやや上」程度の性能という見方もできます。
また、耐震性についても注意が必要です。実は一定条件を満たせば等級2でも認定される場合があるのです。
特に「許容応力度計算」を採用している場合は、耐震等級2でも認定が下りることがあります。
つまり、長期優良住宅の認定=必ず耐震性が最高レベルとは限らないということを知っておく必要があります。
リフォームや増改築に制限がある
長期優良住宅として認定を受けた建物には、後から行う間取り変更や設備改修に制限がかかります。
たとえば、窓を大きくしたり壁を取り除いたりすると、断熱や耐震の基準から外れてしまいます。
これらの変更はすべて行政への再申請が必要になり、勝手にリフォームを実施すると認定取り消しとなります。
将来的な改修を自由に行いたい方にとっては大きな制約になります。
「将来のライフスタイルに合わせて柔軟に変えていきたい」と考えている方には、少し不自由に感じるかもしれません。
維持管理の義務と費用がある
長期優良住宅は、建てたあとも長く使うことが前提になっています。
そのため、10年ごとの点検や修繕が義務付けられており、30年間で15~20万円程度の維持費が必要になることもあります。
点検を怠った場合、補助金の返還請求や認定の取り消しが発生することもあるため注意が必要です。
施工不良により性能が発揮されないことも
図面上で長期優良住宅の基準を満たしていても、現場の施工が雑であれば、本来の性能は出ません。
たとえば、
こうした施工ミスがあれば、省エネ性や耐震性が期待どおりにならない可能性があります。
実際の性能は、図面や書類ではなく施工の技術力と管理体制によって大きく左右されます。

認定を取ったから安心、ではありません。実際の家づくりでは、制度の中身と施工の質をしっかり見極めることが大切です。
長期優良住宅を選ぶ際には、表面的なメリットだけでなく、これらのリスクを必ず理解しておく必要があります。
制度の名前に安心せず、自分にとって本当に価値のある住まいかどうかを冷静に判断しましょう。
制度のスペックは時代遅れになりつつある?
長期優良住宅と聞くと「高性能な住宅」という印象を持つ方も多いでしょう。
しかし実際には、制度が設計されたのは2009年であり、当時の住宅性能基準に基づいたものです。
そこから15年以上が経ち、住宅業界では断熱・耐震・省エネといった分野で技術が大きく進化しています。
そのため、現在の視点で見ると、長期優良住宅の基準はすでに“古くなりつつある制度”と言わざるを得ません。
断熱性能は平均レベルにとどまっている
長期優良住宅が求める断熱性能は「断熱等級5」が基本です。
かつては高性能とされていた基準ですが、現在では等級6や等級7といった上位グレードが存在します。
さらに、民間で提唱されるHEAT20 G2・G3水準では、より快適で省エネな住宅が実現されています。
つまり、断熱等級5の家はもはや「標準より少し上程度」の性能にとどまります。
寒冷地や暑さの厳しい地域では、快適性に不満を感じるレベルと言えるでしょう。
耐震等級も仕様次第でばらつきがある
長期優良住宅では耐震等級3が推奨されていますが、等級2でも認定が下りる仕組みが制度内にあります。
これは、許容応力度計算によって建物の強度を証明できる場合に限り、耐震等級2でも長期優良住宅として認められるためです。
一方で、地震大国である日本では、耐震等級3を最低ラインとして考えるべきというのが多くの専門家の共通認識です。
同じ“認定住宅”でも、等級の違いによって地震への強さが大きく異なるため、
制度任せにせず、自ら設計仕様を指定することが不可欠です。
制度をゴールにしてしまうと後悔する
長期優良住宅の制度はあくまで「最低限の良質住宅の基準」です。
そのため、制度をクリアすることが家づくりのゴールになってしまうと、必要な性能が不足した家になる恐れがあります。
たとえば、
こういった“本当に暮らしに直結する部分”は、認定基準には含まれていません。
制度に合格するかどうかではなく、住む人にとって快適で安心な家かどうかを基準に判断することが大切です。

制度はあくまで“出発点”。
本当に後悔しない家を建てたいなら、制度の枠を超えた設計が必要です。
長期優良住宅という名前に安心感を覚えるのは自然なことです。
しかし、その認定基準は2009年当時の水準にとどまっており、現在求められる住宅性能とはズレがあることを理解しておく必要があります。
制度はあくまで基準のひとつ。最終的に判断するのは、あなた自身の暮らしと価値観です。
地域によって選択肢が限られることもある
長期優良住宅は全国共通の制度ですが、実際の運用には地域差が存在します。
施工会社や担当者の知識・経験、そして自治体の対応体制などによって、同じ申請でも対応や結果が大きく異なるケースがあるのです。
制度を活用したいと考えるなら、「どこで建てるか」「誰に依頼するか」も重要な判断軸になります。
認定に対応できない工務店や建築会社もある
長期優良住宅の認定には、耐震性や省エネ性の証明書類の作成、維持保全計画の提出など、高い専門性と実務経験が求められます。
そのため、特に小規模な工務店やローコスト系の住宅会社では制度対応を断られることがあります。
また、「対応はできるが申請業務を外注するため、費用が割高になる」といったケースも少なくありません。
実際に、「制度に対応していないから」と希望していた地元の工務店での建築を断念した方もいます。
自治体ごとの審査スピードや柔軟性に差がある
長期優良住宅の審査は、制度としては全国共通ですが、実務上は各自治体が審査・認定を行います。
そのため、地域によって以下のような違いが発生します。
- 審査期間の長短(2週間〜2ヶ月以上の差)
- 設計変更への対応スピード
- 申請内容に対する指摘の細かさや厳しさ
こうした違いによって、着工スケジュールに大きな影響が出る可能性もあるため要注意です。
制度に対応している会社が少ない地域もある
都市部では制度対応が進んでいても、地方では長期優良住宅の実績が少ない会社もまだ多く見られます。
その結果、制度対応を条件にすると、
といった弊害が生じます。
特に、「信頼している地場工務店に頼みたい」「間取りや素材にこだわりたい」と考えている方にとっては、制度がハードルになる可能性があります。

制度を活用しようと思っていたけれど、地元の工務店では対応していないことが分かって、結局諦めることになりました。
長期優良住宅を前提に家づくりを進める場合は、次の3点を早い段階で確認することが重要です。
制度の可否だけでなく、「地域の実情」に合わせて柔軟に判断することが後悔を防ぐ鍵です。

まずは情報収集が大事!
タウンライフなら、ハウスメーカーの資料を無料で一括請求できるから、効率よく家づくりを進められるよ♪
まだハウスメーカーが決まっていないあなたへ。
タウンライフ家づくりでハウスメーカーを比較・検討してみませんか?
希望する複数のハウスメーカーが、無料で間取りプラン・見積もり・資金計画書を作成してくれます。

- 家づくりのアンケートに回答(約3分)
- ハウスメーカーを選ぶ(1,100社提携)
- 待つだけ!間取り・見積もりが届く!
\入力はわずか3分で完了/
最大で5社分の資金計画・間取りを無料で取り寄せ可能!
それでも長期優良住宅がおすすめな人の特徴
ここまでで、長期優良住宅には多くのメリットがある一方で、制度には見落とされがちな注意点や制限があることをお伝えしてきました。
それでも、目的や考え方が制度と合っていれば、長期優良住宅は今も有力な選択肢です。
では、どのような人がこの制度に向いているのでしょうか?以下に詳しく解説します。
長く同じ家に住み続けたいと考えている人
「将来的にも転居や売却の予定がない」「建て替えは避けたい」という方には特におすすめです。
長期優良住宅は、「長く快適に住めること」を重視した制度です。
耐久性や劣化対策、点検体制が整っているため、建てた家に20年、30年と住み続けたい方にとって非常に相性が良い制度です。
税制優遇や補助金を最大限に活用したい人
長期優良住宅に認定されることで、住宅ローン控除の期間延長、固定資産税の軽減、補助金の対象化など複数の経済的メリットが得られます。
また、「子育てグリーン住宅支援事業」や「地域型住宅グリーン化事業」など、子育て世帯や若年層を対象にした追加補助金制度と連携していることもあります。
これらを利用することで、数十万円から100万円を超える費用軽減が可能になるため、コストパフォーマンスを重視する方にも制度の価値があります。
将来の資産価値を意識して住宅を建てたい人
長期優良住宅は、住宅性能や点検履歴が明確に記録されるため、将来的な売却や相続の際に資産価値が維持されやすい住宅として評価されます。
特に今後は、「性能の見える化」が進む中で、認定住宅の方が市場で選ばれやすくなる傾向が強まっています。
「子どもに家を残したい」「将来的に手放す可能性がある」と考える方には、有利な選択になります。
維持管理をきちんと行うのが苦でない人
長期優良住宅には、10年ごとの定期点検と計画的なメンテナンスが義務づけられています。
そのため、「こまめな管理が得意」「定期的な手入れを当たり前と考えている」方にはとても向いています。
逆に「点検が面倒」「ほったらかしでもいい」と考える方にとっては、制度の維持がストレスになる可能性があります。
制度に適応できるかどうかは、性格や暮らし方にも左右される要素です。
信頼できる施工会社と出会えている人
制度を形だけ取得しても、施工品質が悪ければ本来の性能は発揮されません。
制度運用・書類申請・現場管理・引き渡し後の点検まで、すべてを任せられる建築会社がいることが前提条件です。
「制度に詳しく、丁寧に説明してくれる」「申請もメンテナンスも一貫して任せられる」会社に依頼できるなら、長期優良住宅を選ぶメリットは大きくなります。

制度を活かせる人は、ライフスタイルや考え方まで制度とマッチしている人なんです。
長期優良住宅が向いている人まとめ
長期優良住宅は、制度の仕組みをよく理解したうえで、自分のライフスタイルや将来設計と照らし合わせて選ぶことが大切です。
適切に活用できれば、暮らしにも資産にも長期的な安心をもたらしてくれます。

まずは情報収集が大事!
タウンライフなら、ハウスメーカーの資料を無料で一括請求できるから、効率よく家づくりを進められるよ♪
まだハウスメーカーが決まっていないあなたへ。
タウンライフ家づくりでハウスメーカーを比較・検討してみませんか?
希望する複数のハウスメーカーが、無料で間取りプラン・見積もり・資金計画書を作成してくれます。

- 家づくりのアンケートに回答(約3分)
- ハウスメーカーを選ぶ(1,100社提携)
- 待つだけ!間取り・見積もりが届く!
\入力はわずか3分で完了/
最大で5社分の資金計画・間取りを無料で取り寄せ可能!
まとめ:制度を正しく知ることが後悔しない家づくりへの第一歩
この記事では、長期優良住宅の落とし穴と、制度の本質を理解したうえで選ぶべきかどうかについて解説しました。
- 建築費の増加や認定の手間などの落とし穴がある
- 制度の基準はすでに最新性能とは言えない
- 地域や会社によって対応状況に差がある
- 一方で、条件が合えば資産性・安心感に優れる制度でもある
こうした点を押さえておけば、自分に本当に合った制度選びができるようになりますね。
長期優良住宅にするかどうか迷ったときは、制度のメリットだけでなく、実際の暮らし方や将来設計と照らし合わせて判断することが大切です。
後悔のない家づくりのために、じっくり比較・検討を進めていきましょう。

まずは情報収集が大事!
タウンライフなら、ハウスメーカーの資料を無料で一括請求できるから、効率よく家づくりを進められるよ♪
まだハウスメーカーが決まっていないあなたへ。
タウンライフ家づくりでハウスメーカーを比較・検討してみませんか?
希望する複数のハウスメーカーが、無料で間取りプラン・見積もり・資金計画書を作成してくれます。

- 家づくりのアンケートに回答(約3分)
- ハウスメーカーを選ぶ(1,100社提携)
- 待つだけ!間取り・見積もりが届く!
\入力はわずか3分で完了/
最大で5社分の資金計画・間取りを無料で取り寄せ可能!