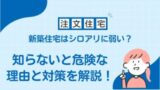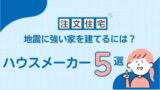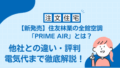「耐震等級3の家だから、うちは大丈夫。」
もし、そう思っているなら要注意です。
実はこの“安心感”、非常に危険な思い込みです。
耐震等級3というのは確かに「国の基準で最も高い耐震性能」とされています。
しかし、それはあくまで設計上”の評価であり、「実際に建てられた家がどれほど安全か」という答えではありません。
熊本地震では、耐震等級3を取得していたはずの住宅が倒壊する事例も発生しました。
また、近年は南海トラフ地震への備えとして「本当に安全な家」の必要性が急激に高まっています。
これから家を建てる方、今住んでいる家に不安を感じている方へ。
本記事では、「なぜ等級3だけでは命を守れないのか」をはじめ、見落とされがちな落とし穴や、本当に家族を守れる家づくりについてわかりやすく解説していきます。
- 耐震等級3の限界と、安心できない理由
- 本当に安全な家づくりに必要な構造・劣化対策とは?
- 地震に備えるために、今すぐできるチェックポイント
耐震等級3=安全ではない理由
「うちは耐震等級3の家だから、地震が来ても大丈夫でしょ?」
…実はその考え方、ちょっと危ないかもしれません。
耐震等級ってなに?
まず、耐震等級というのは「建物がどれくらい地震に耐えられるか」を、設計図の段階で評価した基準のことです。
1〜3までの等級があり、数字が大きいほど性能は高くなります。
| 等級 | 強さの目安 |
|---|---|
| 等級1 | 最低基準(建築基準法)=とりあえず建ててOKなレベル |
| 等級2 | 等級1の1.25倍(主に学校や病院レベル) |
| 等級3 | 等級1の1.5倍(警察署や消防署と同等の強さ) |
この中でも等級3は最上級の耐震性能として、多くの住宅メーカーが推しています。
でも実は「図面通りにできたら」の話です
耐震等級はあくまでも“設計上の話”。
つまり、「この通りに施工できれば、これくらい強い家になりますよ」という目安なんです。
現場での施工ミスやズレがあった場合は、残念ながら想定通りの強さが発揮されない可能性も…。
たとえば現実にはこんなことが起きています。
こうした“ちょっとしたミス”の積み重ねが、本来の耐震性を大きく下げてしまうこともあるんです。

耐震等級3だから安心、とは限らない理由がここにあります!
実際にあった話:等級3の家なのに、こんなトラブルも…
「新築で耐震等級3の家を建てたのに、地震のとき思ったより揺れて怖かった」
「壁紙に大きなヒビが入って、補修費用がかかってしまった…」
実はこうした声、意外と少なくありません。
見た目ではしっかりしてそうな家でも、
中身の“構造の部分”でミスや劣化があれば、性能は一気に下がってしまいます。
熊本地震でも、等級3の家が倒壊…
2016年に発生した熊本地震では、
なんと耐震等級3の木造住宅が実際に倒壊したという報告があります。
「一番強いはずの家が、どうして壊れたの?」と驚く方も多いはず。
原因としては、
など、「等級3を取っていてもダメな場合がある」ことを教えてくれる事例です。
安心できる家にするために大切なこと
耐震等級3は決して悪いわけではありません。
むしろ、安心のための“出発点”としては非常に大切な基準です。
でも、もっと大切なのはその先です。
- 正確な施工がされているか?
- 数値だけでなく、実物としての強さがあるか?
- 湿気・シロアリ・結露など、長く住んだときの劣化にも強いか?
これらをきちんと考えていないと、
せっかく等級3を選んでも**「図面だけが強い家」になってしまうんです。

耐震等級3は“安心のゴール”ではなく、“スタートライン”です。
これから家を建てる方は、ぜひこの視点を持っておくと安心ですよ。
建築基準法は“命を守る最低限”にすぎない
「建築基準法を守ってる家なら、安心でしょ?」
そう思っている方も多いかもしれません。
でも実は、それだけで安心とは言い切れない理由があるんです。
建築基準法ってそもそも何?
建築基準法とは、日本で建てる建物すべてに適用される、いわ*“最低限守るべきルール”のようなものです。
このルールでは、
など、命を守ることに重点を置いた基準が定められています。
でもここで大事なのは、この法律が目指しているのはあくまで…
「命が助かればOK」というレベル
だということです。
家が壊れても“基準クリア”ってどういうこと?
実は建築基準法では、震度6強~7程度の地震が起きた場合、「建物が多少壊れても、命が守れれば合格」とされています。
つまり、
というのが、建築基準法の許容範囲なんです。
法律を守っている家でも、地震後に“住めない家”になる可能性はあるんです。
地震で“命”は守れても“生活”は壊れることがある
実際の地震では、建築基準法を満たしていた住宅でも、
- 室内の壁が剥がれた
- ドアや窓が歪んで開かなくなった
- 床が傾いて家具が倒れた
といったケースが多く報告されています。
結果として…
など、「命は守れても、生活が守れない」という事態にもなりかねません。
「建築基準法+α」の備えが大切です
法律を守るのはもちろん大前提ですが、それだけで「地震に強い家」とは言えないのが現実です。
これからの家づくりで本当に必要なのは、
- 構造の根拠がしっかりした設計(許容応力度計算など)
- 施工精度の高い現場管理
- 湿気・白アリ・経年劣化への対策
といった、“その先”まで見据えた安心設計です。

「法律を守っている=安心」ではなく、
「家族が安心して暮らせるかどうか」で考えてみてくださいね。
構造計算の盲点|許容応力度計算をしないと意味がない
「耐震等級3ってちゃんと取ってるし、構造計算もされてるはずだから安心でしょ?」
…と思っている方、ちょっと注意が必要かもしれません。
「構造計算」って、実は3つの方法があるんです
家づくりの現場でよく耳にする「構造計算」という言葉。
でも実は、すべての家で同じ方法が使われているわけではありません。
一般的な木造住宅で使われる構造計算には、主に次の3つの種類があります。
| 計算方法 | 内容 |
|---|---|
| 使用規定 | マニュアル通りに材料を使えばOK。最も簡易的 |
| 壁量計算 | 壁の量で耐震性をチェックする、比較的シンプルな方法 |
| 許容応力度計算 | 柱や梁にかかる力を数値で細かく分析。最も根拠のある計算方法 |
この中で、最も信頼性が高いのが「許容応力度計算」です。
等級3でも、許容応力度計算じゃないことがある
ここが大きな盲点です。
耐震等級3は、「壁量計算」でも取得できます。
つまり…等級3でも、中身は“簡易的な計算”で済まされていることがあるということなんです。
「許容応力度計算」は、どこまで強いかが“数値でわかる”
許容応力度計算では、
- どの柱にどんな力がかかるか
- 地震や風でどこがどれだけ動くか
- 接合部がどれくらい耐えられるか
といったことが、数字ではっきりと算出されます。
つまり、「この家は○○kgの力まで耐えられます」といった、信頼できる裏付けがあるのです。
壁量計算だけだと…実は根拠が弱いことも
壁量計算は、壁の“面積とバランス”だけで耐震性を判断する方法です。
実際には、
- 柱の太さ
- 接合金物の種類
- 材料の品質
といった重要な部分までは踏み込んでいません。
例えるなら、「見た目はしっかりしてるけど、中身の強さがわからない家」になってしまうこともあるんです。
なぜ、ほとんどの住宅でやっていないの?
「だったら、みんな許容応力度計算をやればいいのに…」
と思うかもしれませんが、実はこんな事情があります。
- 計算が複雑で手間がかかる
- 高度な知識と専門ソフトが必要
- 5〜15万円ほどの費用が追加でかかることもある
さらにもうひとつ大きな理由が…
法律上、許容応力度計算は義務ではないという点です。
そのため、多くの住宅会社では「コストを抑える」「簡単な方法で済ませたい」という理由で、壁量計算などの簡易な方法だけで構造設計を行っているケースが多いのが現実です。
家族を守る家に必要なのは「数値で証明された強さ」
「等級3だから安心」ではなく、“どうやってその等級が取られたか”がとても大切です。
大地震が起きたとき、「この家、本当に大丈夫かな?」と思いたくないなら、
数値で強さが証明されている=許容応力度計算された家を選ぶことがポイントです。
「どこに頼めばいい?」と思った方へ
許容応力度計算をしっかり行っている会社には、次のような特徴があります。
まずは、こういった会社を探して話を聞いてみるだけでも大きな一歩になりますよ。

等級3は“ラベル”です。
そのラベルの中身が、しっかり詰まっているか?が、地震に強い家づくりのカギになります。
見落としがちな劣化リスク|白アリ・湿気・結露が家を壊す
「耐震等級3で、構造計算もしっかりしてるから安心」
…と思っていても、家は“時間とともに弱くなる”可能性があるって知っていましたか?
地震に強い家でも、“劣化”には勝てない
どんなに強い構造をもっていても、それが長く保たれなければ意味がありません。
特に木造住宅の場合、こんなリスクがあります。
- 湿気で柱や梁が腐る
- 壁の中で結露が起きて、構造材がボロボロに
- 白アリが侵入して、土台を食い荒らす
見た目は変わらなくても、内部からジワジワと耐震性能を下げてしまうのが劣化の怖さです。
よくある3つの劣化リスク
地震が来る前に、“家の中から壊れ始めている”こともあるんです。
ここではよくある3つの劣化リスクを紹介します。
白アリ被害(シロアリ)
- 地面に近い木材や断熱材を食い荒らす
- 見つけたときには、すでに土台がスカスカ…ということも
- 湿気の多い地域・通気性の悪い基礎で起こりやすい
湿気・通気不足
- 壁の中や床下の空気が動かないと、湿気がこもる
- 木材が腐り、接合部が弱くなる
- 結果的に、地震時の“支え”が失われる危険も
結露(冬型・夏型)
- 室内と外気の温度差で、壁の中に水滴が発生
- 見えない場所でカビや腐食が進む
- 夏型結露はエアコンの冷気によっても起こる
じゃあ、どうやって防ぐの?
劣化リスクを減らすには、設計段階からの工夫が重要です。
さらに、「通気できるつくりかどうか」も大きなポイントです。
劣化対策は“見えない安心”をつくるために必要
例えば…
- 「家の中はキレイだけど、床下はジメジメして白アリがいた」
- 「新築から10年で、結露で壁の中が腐っていた」
といった事例は少なくありません。
外からは見えない部分こそ、家の命を支えているということなんです。

家を「建てたときが一番丈夫」ではなく、10年後・30年後も強いままでいられること。
それが、本当に地震に強い家づくりの鍵です。
見逃し注意のヒートブリッジ|金物からの結露が家を壊す
「耐震性や劣化対策はバッチリしてるから大丈夫!」
…と思っていても、家の中には“見えない落とし穴”が潜んでいることをご存知でしょうか?
ヒートブリッジって何?
ヒートブリッジとは、金物や構造材など熱を通しやすい部分を通じて、外の冷気や熱気が家の中に伝わってしまう現象のことです。
たとえば、柱や梁に使われる金物、窓まわり、断熱材との接点などが該当します。

ヒートブリッジ=「熱の抜け道」とも呼ばれ、結露や腐食の原因になります。
何が起こるの?ヒートブリッジの影響
特に日本のように高温多湿な気候では、夏も冬も温度差+湿気による結露が起こりやすく、
ヒートブリッジによる被害が出やすい環境と言えます。
どうすれば防げるの?
ヒートブリッジを防ぐためには、次のような対策が効果的です。

ただし、このヒートブリッジ、図面だけでは気づきにくいことが多いのです。
実際には、施工中の現場を見ないと、どこにどんな金物が入っていて、どう断熱されているかまでは分かりません。
「気づきにくいリスク」だからこそ、見学と質問が大事
ヒートブリッジのリスクを防ぐには、家づくりの段階で“見えない部分”にも目を向けることが大切です。
たとえば…
- 現場見学会に参加して、金物や断熱材の施工状況を確認する
- 「ヒートブリッジ対策はどうされていますか?」と直接質問してみる
- 外断熱を取り入れているかをチェックする
こうした行動が、後から発生する見えない劣化の防止につながります。

図面にない部分こそ、住んでからの快適さ・安全性を左右します。
信頼できるハウスメーカーの選び方|見るべき3つのポイント
「本当に地震に強く、長く安心して暮らせる家を建てたい」
そう考えたときに大切なのが、“誰に建ててもらうか”という視点です。
どんなに知識があっても、施工会社の考え方や技術力によって家の品質は大きく変わります。
ここでは、プロの目線で「信頼できる住宅会社かどうかを見極めるための3つのチェックポイント」をご紹介します。
許容応力度計算の導入実績があるか?
まず注目したいのが、構造の「強さ」をどうやって証明しているかです。
「耐震等級3」といっても、その裏にある計算方法が重要。
壁量計算だけで取得したものと、許容応力度計算を経て取得したものでは、安心の根拠がまったく違います。

「許容応力度計算を導入しているか」「説明できるか」を確認してみましょう。
日常的に許容応力度計算を行っている会社であれば…
といった誠実な対応が期待できます。
劣化対策に言及しているか?(断熱・換気・基礎など)
どんなに構造が強くても、時間の経過とともに劣化すれば意味がありません。
だからこそ、劣化への備えにどれだけ力を入れているかが重要です。

「劣化しない家」ではなく、「劣化を防ぐ仕組みを持った家」に注目するのがポイントです。
さらに、点検のしやすさ(点検口・床下スペースなど)もあわせて確認するとよいでしょう。
見学会や構造公開を行っているか?
家の中身は、完成してからでは見えません。
だからこそ、建築途中の現場を“見せてくれるかどうか”が信頼の大きな指標になります。
こうした対応がある会社は、施工に自信と誠実さがある証拠です。
アフター対応や保証制度も確認しよう
家は建てて終わりではなく、住んでからが本当のスタートです。
どんなに対策をしていても、時間が経てばメンテナンスや点検が必要になります。
そのためにも…
- 定期点検の体制があるか
- 保証内容(構造・防水・シロアリなど)が明確に提示されているか
- 修繕やトラブル対応の窓口が設けられているか
こういったアフターの仕組みがしっかり整っていることも、信頼できる施工会社の条件です。
小さな違いが「安心の差」になる
- 等級の中身を説明できる
- 見えない部分にも気を配っている
- 見せてくれる・教えてくれる・答えてくれる
- そして、住んだあとも寄り添ってくれる
こうした姿勢の違いが、“安心して暮らせる家づくり”の明暗を分けます。

家づくりは、比べた人が後悔しません。
ぜひ複数の会社を見て、「中身」で選ぶ目線を持ってください。

まずは情報収集が大事!
タウンライフなら、ハウスメーカーの資料を無料で一括請求できるから、効率よく家づくりを進められるよ♪
まだハウスメーカーが決まっていないあなたへ。
タウンライフ家づくりでハウスメーカーを比較・検討してみませんか?
希望する複数のハウスメーカーが、無料で間取りプラン・見積もり・資金計画書を作成してくれます。

- 家づくりのアンケートに回答(約3分)
- ハウスメーカーを選ぶ(1,100社提携)
- 待つだけ!間取り・見積もりが届く!
\入力はわずか3分で完了/
最大で5社分の資金計画・間取りを無料で取り寄せ可能!
コストの真実|安心は高い?それとも安い?
「許容応力度計算ってお金かかるんでしょ?」
「断熱や劣化対策を強化したら、家づくりの費用が上がるんじゃない?」
こうした不安を持つ方は多いですが――
“本当のコスト”は、目先の金額だけでは見えてきません。
構造・性能にかかる追加コストの相場
安心できる家を建てるには、ある程度の「プラスアルファの投資」が必要です。
でも、それは決して“贅沢”ではなく、将来のリスクを回避するための合理的な支出です。
代表的な追加コストの目安
| 項目 | 追加費用の相場(概算) |
|---|---|
| 許容応力度計算 | 5〜15万円程度 |
| 高性能断熱・防湿仕様 | 標準との差額 20〜60万円程度 |
| 基礎の換気・白アリ対策 | 5〜20万円(薬剤処理・設計変更など) |
一般的な住宅価格に対して5〜10%未満の範囲内で済むことが多く、費用対効果の高い投資といえます。
「安く済ませたつもり」が高くつくケースも…
初期コストを削ってしまったことで、あとから想定外の出費が発生することも少なくありません。
例えばこんなケース
- 湿気や結露による壁内部の腐食 → 補修費数十万円
- 白アリ被害で土台が劣化 → 交換工事費 50万〜100万円
- 大地震で建物が大きく損傷 → 仮住まい+建て替え数千万円
「安く建てたのに、安心を買い直すことに…」そんな後悔を防ぐには、“最初の選択”が大切です。
「10万円の初期投資」が「50万円の修繕費」を防ぐ
たとえば、結露対策のために10〜15万円ほどかけて断熱材や通気設計を強化しておけば、10年後に壁の張り替えやカビ除去に50万円以上かかる事態を防げる可能性もあります。
こうして見てみると、初期投資はむしろ“節約”になることがよくわかります。
住宅ローンに組み込むとどうなる?
「とはいえ数十万円の上乗せはキツイ…」と感じる方もいるかもしれません。
ですが、住宅ローンで35年返済にすれば、月々の差額はごくわずかです。
仮に30万円の性能向上費用を追加 → 金利1.0%/35年ローンの場合
→ 月々の返済差:約850〜900円前後
1日あたり30円程度で、“安心と安全”をプラスできるなら、費用対効果としては十分といえるのではないでしょうか。
「目先の安さ」と「本当の安さ」は違います
住宅は数十年にわたって使い続けるもの。
一時的な安さではなく、“暮らしの中で何を守れるか”を基準に選ぶことが大切です。
初期費用だけを見るのではなく、修繕・建て替え・資産価値まで含めて「本当のコスト」を考えること。
それが、後悔のない家づくりへの第一歩です。
中古・既存住宅の場合|今からできる地震・劣化対策
「すでに家を持っているんだけど、どうすれば安心できるの?」
「新築じゃないと対策できないのでは…?」
そんなふうに感じている方も大丈夫です。
中古住宅や既存の持ち家でも、“今からできる”地震・劣化対策はたくさんあります。
まずは耐震診断 → 必要なら補強を
築年数の古い家や、旧耐震基準(1981年以前)の建物は、倒壊リスクが高い可能性があります。
まずは、自治体や専門家に相談して、耐震診断を受けましょう。
具体的な補強の例
耐震診断の費用は5〜10万円前後が相場です。
補助金を出している自治体もあるので、事前に確認しておくと安心です。
床下の湿気・白アリをチェック
家の外観はきれいでも、床下が湿気で傷んでいたり、白アリが発生していたら意味がありません。
築10年以上経過している住宅では、床下点検を定期的に行うことが重要です。
チェックポイント
床下点検は無料〜数万円で対応してくれる業者もあります。
「見えない場所」ほど、こまめに確認を。
通気層の後付け・断熱改修も可能
家が寒い、結露が多い、カビが気になる…といった悩みは、断熱や通気不足が原因かもしれません。
こうした問題も、あとから改善することが可能です。
改修の一例
床下点検は無料〜数万円で対応してくれる業者もあります。
「見えない場所」ほど、こまめに確認を。
一気にやらなくても大丈夫。部分的な改修も効果的
「対策したいけど、予算が…」「どこから始めていいかわからない」
そんなときは、一部からでも始めてOKです。
- まずは床下だけ点検・通気性を改善
- 外壁リフォーム時に通気層を加える
- 築年数が経った部分だけ断熱強化 など
すべてを一度にやる必要はありません。
“できるところから始める”ことが、結果的に家を守ることにつながります。
専門家に相談するのが安心・確実
どこに問題があるか分からないという方は、住宅診断(インスペクション)を利用しましょう。
すべてを一度にやる必要はありません。
“できるところから始める”ことが、結果的に家を守ることにつながります。
築年数より「手が入っているかどうか」
家の寿命や安全性は、「築年数」ではなく「手が入っているかどうか」で決まります。
- 築20年でも、点検・補強・劣化対策されている家は安心して住める
- 築5年でも、湿気や構造不備があれば早期に劣化する可能性も
適切な対策とメンテナンスがされていれば、家は何十年でも長く安心して使えます。

中古住宅でも、既存の家でも。
「今からでもできることがある」という事実を、ぜひ前向きに捉えてください。
まとめ|安心できる家づくりのために今できること
この記事では、「地震に強く、長く安心して住める家」を実現するために必要な知識と行動についてご紹介しました。
- 耐震等級3だけでは不十分であること
- 許容応力度計算や構造の中身が重要であること
- 劣化対策(湿気・白アリ・結露)が見えない部分に影響すること
- 信頼できる施工会社を見極める3つのポイント
- 新築だけでなく、中古住宅でもできる対策があること
- 「初期投資」が結果的に将来の出費を防ぐという視点の重要性
これらを知っておけば、ただの「数字上の安心」ではなく、実際に家族を守れる住まいを選ぶことができますね。
安心できる家を手に入れるには、「構造・劣化・施工・コスト」のすべてを正しく理解し、必要な行動を取ることが大切です。
まずは、耐震診断や床下点検など、“今できること”から始めてみましょう。

まずは情報収集が大事!
タウンライフなら、ハウスメーカーの資料を無料で一括請求できるから、効率よく家づくりを進められるよ♪
まだハウスメーカーが決まっていないあなたへ。
タウンライフ家づくりでハウスメーカーを比較・検討してみませんか?
希望する複数のハウスメーカーが、無料で間取りプラン・見積もり・資金計画書を作成してくれます。

- 家づくりのアンケートに回答(約3分)
- ハウスメーカーを選ぶ(1,100社提携)
- 待つだけ!間取り・見積もりが届く!
\入力はわずか3分で完了/
最大で5社分の資金計画・間取りを無料で取り寄せ可能!