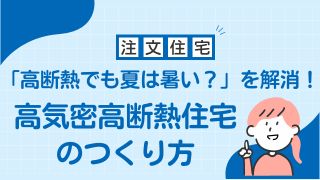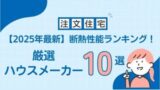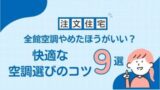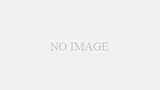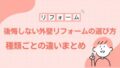注文住宅を計画するあなたは、夏の猛暑対策や省エネ性、冬の快適性を十分に検討できていますか?気候変動が進む今、従来の断熱設計では暑さ・寒さ・湿気への対応が追いつかなくなる可能性があります。
この記事では、最新の高気密高断熱住宅に欠かせない性能選びから施工ノウハウ、土地選びやメンテナンスまでをトータルに解説。失敗しない家づくり術を手に入れて、末永く快適&省エネな住まいを実現しましょう。
では、まず日本の気候変動シナリオの概要を見ていきましょう。
日本の気候変動シナリオ(2℃/4℃シナリオ)
2025年3月27日に気象庁・文部科学省が発表した『日本の気候変動2025』では、今後の温暖化パターンとして「2℃シナリオ」と「4℃シナリオ」の二つが示されています。
どちらのシナリオでも猛暑日や熱帯夜の増加、冬日数の減少、集中豪雨の頻度上昇などが予測され、注文住宅の快適性や省エネ性にも大きな影響を及ぼします。
- 2℃シナリオ:平均気温+約1.4℃/猛暑日+約18日/熱帯夜+約38日/冬日数−16日
- 4℃シナリオ:平均気温+約4.5℃/猛暑日・熱帯夜がさらに大幅増/冬日数−46日
- 集中豪雨頻度:100年に1度の大雨が年間約5.3回に増加(4℃シナリオ)
- 雪量変動:2℃シナリオで−30%、4℃シナリオで−60%減少、一度に降る量は増加の可能性
これらの予測を踏まえ、次では断熱・気密性能の基礎知識と具体的対策を見ていきます。
なぜ「高気密高断熱」が今、必須なのか
「高気密高断熱って、寒冷地向けでしょ?」「断熱しても夏は暑くなるんじゃ…?」
そんな声をよく聞きますが、それはもう“過去の常識”です。
現在の日本では、気候・災害・暮らし方のすべてが変化し、高気密高断熱の必要性はかつてないほど高まっています。
ここでは「なぜ今、注文住宅に高気密高断熱が欠かせないのか」を、3つの視点から解説します。
夏の暑さが“過去最高”を更新し続けているから
「昔より夏が暑くなった」と感じること、ありませんか?
実はそれ、気のせいではありません。データでもはっきり示されています。
2025年に発表された気候変動シナリオでは、地球温暖化が進んだ場合、
- 猛暑日は年間で+18日
- 熱帯夜は+38日
という驚くべき予測が出ています。つまり、1年のうち1ヶ月以上が“寝苦しい夜”になるということ。
これからの日本は、関東でも40℃超えが珍しくなくなり、東北でも37〜38℃が想定されるようになります。そうなると、エアコンがあっても「効かない」「冷えない」という家が続出する可能性があります。
こうした猛暑の中で快適に暮らすためには、「とにかく冷やす」ではなく、“熱を入れない家”にすることが大切です。
高気密高断熱住宅は、外の熱が壁・屋根・窓から入りにくく、室内で冷やした空気も逃げにくい構造になっているため、エアコンの効率が格段に上がります。
結果的に、冷房時間や電気代が大幅に減るだけでなく、冷えすぎや温度ムラも起きにくくなり、体にもやさしい暮らしが実現できます。
雨の降り方が“異常レベル”に変化しているから
「ゲリラ豪雨が増えた気がする」と思ったこと、ありませんか?
実際にここ数年で、雨の降り方は確実に変わっています。
気温が上がると空気がより多くの水蒸気を含めるようになり、その結果、一度に降る雨の量が跳ね上がります。4℃シナリオでは、“100年に1度の大雨”が、100年間で5回以上起きると予測されています。
これはつまり、これから家を建てる人は**“生涯に2回以上、大規模水害に遭うリスク”がある**ということ。
しかもそれは、いままで安全とされていた地域でも例外ではありません。
高気密高断熱住宅は、断熱材や壁の中まで密閉性が高いため、もし浸水すると断熱材が水を吸って性能が著しく落ちてしまうという特性があります。
だからこそ、気密性だけでなく水害に強い家の設計も一緒に考える必要があるのです。
といった対策を組み合わせることで、高性能な家を“長く保つ”ことができるようになります。
雪は減るのに“雪害リスク”は増えているから
「これから雪が減るなら、断熱にこだわらなくてもいいのでは?」そう思っている方がいたら、ぜひこのデータを知っておいてください。
日本の気候予測によると、
- 2℃シナリオで雪量は30%減少
- 4℃シナリオでは60%減少
とされています。けれど一方で、ドカ雪や氷と雪が繰り返す複雑な降り方が増えることも指摘されています。
つまり、「全体としては減っているけれど、一度に降る量が極端に多くなる」ということです。
このような雪の“質”が変わってくると、屋根に大きな荷重がかかったり、屋根裏で結露が発生しやすくなったりと、住宅へのダメージがより大きくなります。
特に、外気との温度差が大きい断熱不足の住宅では、壁の中に内部結露(壁体内結露)が起こりやすくなり、断熱材の劣化やカビの原因にも。
そのため、寒冷地では単に断熱材を入れるだけでなく、
といった工夫が欠かせません。
雪が少なくなった=断熱は不要、というわけでは決してないのです。
断熱・気密性能の基礎知識
高気密高断熱住宅をつくるには、単に「断熱材が入っていればいい」「窓が二重なら安心」では不十分です。
性能の違いは“数値”で明確に判断できるもの。ここでは、家の基本性能を左右する「断熱材の種類」「断熱等級」「気密性の指標(C値)」について、順を追って整理します。
熱伝導率×厚みで決まる断熱性能(フェノールフォーム vs グラスウール)
「この断熱材、なんか分厚いけど…性能は高いの?」そう思ったことがあるなら、“厚み”だけで判断してはいけません。
断熱性能を左右するのは、
この2つの掛け算で、最終的な断熱性能=熱抵抗値(R値)が決まります。
フェノールフォーム
- 熱伝導率:約0.020W/m・K(非常に低い=熱を通しにくい)
- 薄くても高い性能を出せる
- 主に一条工務店など高性能住宅で採用されることが多い
グラスウール(16kg品)
- 熱伝導率:約0.038〜0.045W/m・K
- 厚くすればそれなりに効果あり
- 安価で施工しやすく、広く使われているが、湿気に弱い一面も
たとえば、フェノールフォーム50mm ≒ グラスウール100mm前後の性能になるケースもあり、「同じ厚さ」でも中身によって効果が大きく変わるというわけです。
また、施工の丁寧さや断熱材の隙間処理も重要。特に壁や床・天井のつなぎ目で熱が逃げる熱橋(ヒートブリッジ)が発生しないよう、丁寧な施工技術とのセットで判断しましょう。
断熱等級1〜7の仕組みと“冬基準”の盲点
「断熱等級7だから夏も快適!」…と思ってしまいがちですが、実はこの断熱等級は“冬の保温性能”を基準に設計されています。
断熱等級の概要
たとえば、等級7は「北海道レベルの寒冷地でも十分に暖かく保てる性能」ということですが、夏の暑さにどれだけ強いかは、等級だけでは判断できません。
夏対策で大事なのは、
- 断熱材の種類・配置(特に屋根・天井)
- 窓からの熱の侵入をどれだけ抑えられるか(遮熱ガラス・シェード等)
- 換気設計・遮熱外構
といった、「断熱等級とは別の設計視点」が必要です。
つまり、「断熱等級が高ければOK」ではなく、冬と夏、両方に対応できる設計であるかを見極める必要があるということです。
気密性能(C値)と気密測定の重要性
「断熱はしっかりしてるのに、冬は足元がスースー冷える…」その原因、気密性の不足かもしれません。
住宅の気密性能は、「C値(相当隙間面積)」という数値で評価されます。
これは、建物1㎡あたりにどれだけ隙間があるか(cm²/㎡)を示すもので、
数値が低いほど隙間が少なく、空気が逃げにくい住宅という意味になります。
C値の目安
ただし、注意したいのは、C値は施工の精度によって大きく左右されるという点です。
いくら性能の高い断熱材を使っても、隙間だらけの施工では意味がありません。
そこで重要になるのが「気密測定の実施」です。
引き渡し前に専用機器で建物の隙間を実測することで、カタログ値ではない“実際の気密性能”が明らかになります。
以下のような質問を住宅会社にしておくと安心です。
このように、断熱性能と同じくらい、気密性能の“見える化”が家づくりの質を左右する要素となります。
各部位ごとの最適対策
高気密高断熱の家づくりにおいて、性能を最大限に活かすためには、家全体をバランスよく設計することが重要です。
特に「熱の出入りが多い場所」に着目し、それぞれの部位ごとに最適な対策を講じることで、住まいの快適性と省エネ性は大きく変わってきます。
ここでは、窓・天井・壁・換気・外構の5つのポイントについて対策を解説します。
窓:熱の出入りをもっとも許しやすい場所
住宅の中でも、もっとも多くの熱が出入りするのが窓です。
冬は暖房の熱が逃げ、夏は強い日差しと外気熱が侵入してきます。実際に、冬の室内の熱のうち約5割、夏の外気熱の約7割が窓から出入りしていると言われています。そのため、窓まわりの断熱・遮熱対策は、住宅の性能に直結する重要なポイントです。
主な対策は次の通りです。
窓の内側、ガラス本体、外側の三方向から対策を講じることで、夏の冷房効率と冬の保温性を大きく高めることができます。
天井・屋根:夏の熱は“上から”入ってくる
夏場、部屋がなかなか冷えない原因のひとつが、屋根からの熱の侵入です。
晴天時の屋根は60度を超えることもあり、その熱が天井を通して室内に伝わってきます。
この熱を防ぐには、次のような対策が有効です。
天井部分の断熱がしっかりしているかどうかは、冷房効率だけでなく、体感温度にも大きく影響します。
壁・床:目に見えない隙間が快適性を損なう
断熱材をしっかり入れても、冷気や熱気を感じる場所があるなら、それは気密性の不足が原因かもしれません。
住宅の隙間は、特に以下の部分で多く発生するとされています。
気密性を高めるための主な対策は以下の通りです。
見えない部分の処理が、断熱性能の発揮と快適性の維持に直結します。
換気システム:空気を入れ替えても室温を保つ仕組み
高気密住宅では、自然換気が起きにくくなるため、計画換気が必須になります。
その中でも、第一種換気と呼ばれる「給気・排気ともに機械で行う換気方式」が推奨されています。
第一種全熱交換型の換気システムでは、外の冷たい(または熱い)空気と室内の空気が熱と湿度を交換しながら入れ替わります。
特に、熱回収率が85パーセント以上の機種であれば、外気温が0度でも室内にはほぼ暖かい空気をそのまま取り込むことができます。
この仕組みによって、
といった効果が得られます。
空気の質と温熱環境を同時にコントロールするためにも、熱交換型の換気システムは重要な設備のひとつです。
外構・軒出し:外からの熱を家に入れない工夫
断熱材や窓ガラスにこだわっても、夏の日差しを直接浴びれば、室内温度は一気に上昇します。
そこで重要になるのが、家の外から熱をコントロールする工夫です。
まず効果的なのが、軒の出の調整です。
南向きの窓に対して、窓の高さの約3分の1を目安に軒を出すと、夏は日射を遮り、冬は太陽の光を室内に取り込むことができます。
その他にも、以下のような方法が有効です。
夏の暑さを抑えるには、家の中だけでなく、家の外で熱をどう扱うかも大切です。
土地選びと水害・ハザード対策
「うちは川から離れているから大丈夫」――そう考えていませんか?
近年の気候変動により、従来の常識では通用しない水害リスクが全国で増えています。
高気密高断熱住宅は、優れた保温性・遮熱性が魅力ですが、同時に一度水が入ってしまうと断熱材や構造へのダメージが大きくなる傾向もあります。
そのため、家を建てる前の段階、つまり「土地選び」や「基礎設計」から水害対策を講じることが、より重要になってきています。
ここでは、家づくりの初期段階で必ず確認しておきたい3つの視点をご紹介します。
ハザードマップの読み方と氾濫想定区域の確認方法
水害リスクを知るために、まず活用したいのがハザードマップです。
自治体や国土交通省が提供するもので、河川氾濫・土砂崩れ・高潮などの災害リスクが地図上に色分け表示されています。
とくに注意しておきたいのは、次の2点です。
ただし、ハザードマップでリスクが低く見えても安心はできません。
最近では、都市部の排水能力を超えて道路が冠水する内水氾濫や、山の中腹から流れ込んだ水による局地的浸水など、“川がない地域”でも被害が起きています。
また、地名にも注目してください。
「○○川」「○○谷」「○○田」といった地名は、もともと水辺や低地だった可能性が高く、地盤が軟弱だったり、雨水が溜まりやすい傾向もあります。
土地探しの際には、国土交通省の「重ねるハザードマップ」や各自治体のハザードマップを活用し、その土地がどんな災害リスクを抱えているかを事前に確認しておくことが重要です。
敷地かさ上げ・地盤改良・周辺排水計画のポイント
仮に希望の土地がややリスクのあるエリアだったとしても、敷地計画や施工方法によって被害を軽減することは十分可能です。
有効な対策には、次のようなものがあります。
- 敷地かさ上げ(30〜50cm)
→ 浸水のリスクを物理的に下げる、もっとも効果のある方法のひとつ - 地盤改良(砕石転圧・表層改良・柱状改良など)
→ 軟弱地盤による不同沈下や排水不良を防止し、住宅全体の耐久性も向上 - 排水経路の確認
→ 隣地や道路より敷地が低いと、雨水や泥水が流れ込む可能性がある。周囲の傾斜や排水路の位置を現地で確認しておくことが大切です。
また、擁壁のある土地では裏側からの水圧にも注意が必要です。
できれば、雨の日や直後に現地を訪れ、地面の水はけや排水状況を確認しておくと安心です。
水害に強い基礎仕様・自動排水設備の選び方
住宅そのものにも、水害リスクを軽減する工夫ができます。
とくに高気密高断熱住宅では、断熱材が一度水を含むと乾きにくく、断熱性能が大きく低下してしまうという特徴があるため、浸水を防ぐ構造そのものが重要になります。
対策としては、次のような設計・設備が有効です。
- 立ち上がりの高いベタ基礎
→ 基礎の高さを確保し、床下浸水リスクを低減 - 床下の基礎断熱+外周気密化
→ 従来の基礎換気口は水や虫の侵入リスクがあるため、密閉式構造へ変更
→ 気密性と防水性を両立できる設計が理想 - 自動排水ポンプ(排水ピット+バックアップ電源)
→ 浸水時に雨水を速やかに排出。地下室やガレージのある住宅では必須アイテム
→ 停電時でも作動するよう、蓄電池や非常用電源との連携も確認 - 住居スペースを2階以上に設ける設計
→ 万が一1階が水に浸かっても、生活の継続性を確保できる
さらに、近年では一条工務店やアイ工務店など、水害を想定した基礎仕様やかさ上げ対応を標準で行う住宅メーカーも増えています。
「うちの構造は水害に強いですか?」「排水や基礎の対策はどの程度可能ですか?」といった質問を住宅会社にしておくと、施工品質の見極めにもつながります。
水害の発生頻度は、4℃シナリオでは「100年に1度」だった大雨が「100年に5.3回」起こるとも言われています。
それだけに、土地選び・敷地設計・基礎構造の3点セットでリスクに備えることが、これからの住宅では“当たり前の基準”になるといえるでしょう。
屋根形状と雪害対策(雪国向け)
雪国で家を建てる際、特に注意したいのが「屋根の形状と雪への備え」です。
高気密高断熱の家では、外気と室内の温度差が大きくなるため、屋根の設計次第では思わぬ雪害につながる可能性もあります。
近年では、雪の総量こそ減っているものの、一度に大量の雪が降る「ドカ雪」が増加しています。こうした気候の変化に対応するためにも、屋根勾配・積雪荷重・雪止め・融雪設備などを総合的に検討することが大切です。
ここでは、雪国での屋根設計に欠かせない2つの視点をご紹介します。
ドカ雪への備え:屋根勾配と積雪荷重設計
突然の大雪で屋根に一気に雪が積もると、建物全体に大きな負荷がかかります。
さらに、屋根からの落雪が隣家や道路に被害を与えるリスクもあります。
そのため、屋根の勾配や構造には、次のような備えが求められます。
屋根勾配は緩やかに設計する
屋根の傾斜が急すぎると、雪が滑り落ちるスピードが速くなり、落雪による事故や周辺への被害を引き起こす恐れがあります。
雪を載せる前提であれば、2寸〜3寸程度(10〜15度)の緩い勾配にすることで、雪を安定して屋根上に保持できます。
積雪荷重に耐える構造設計を行う
地域の積雪量に応じて、屋根に1〜2m程度の雪が載ることを前提とした荷重設計が必要です。梁や柱のサイズ、配置など、構造全体で雪の重みに耐えられるかどうかを確認しておきましょう。
積雪荷重に耐える構造設計を行う
屋根勾配や構造、屋根材の工夫次第では、定期的な雪下ろしを不要にすることも可能です。
雪が留まりやすい金属系のマットな素材を選ぶ、周辺に落雪リスクのないスペースを確保するなど、意図的に“雪を載せる”設計が有効です。
加えて、高気密高断熱の住宅では、屋根裏の断熱や気密処理が甘いと、暖気がこもって屋根雪の一部だけが溶け、再凍結する「アイスダム現象」が起きやすくなります。
これは、雨樋の破損や屋根材の劣化、結露被害の原因になるため、屋根断熱の施工精度にも注意が必要です。
軒先形状・雪止め・融雪パネルシステム
屋根の雪対策を語るうえで、軒先の処理と雪止め金具の設計も見逃せません。
とくに軒の形状や出幅によって、落雪リスクや構造への負荷は大きく変わります。
軒の出は短め、または補強を前提に設計する
軒を深く出す場合は、その分だけ落雪による負荷も増えるため、補助柱や構造補強が必要になります。
設計段階で「軒をどの程度出すか」「その下に人が通るか」をしっかり検討しておきましょう。
雪止め金具をバランスよく配置する
雪止めは、屋根の雪を一気に滑り落とさないようにする装置です。
ただし、太陽光パネルと干渉する可能性があるため、架台との配置バランスや取り付け位置にも注意が必要です。
将来的にパネルを設置する予定がある場合も、あらかじめ設計に反映させておくのがおすすめです。
融雪パネルやヒーターの導入を検討する
屋根や軒先に電熱式の融雪パネルを敷設することで、雪の張り付きや凍結を予防できます。
特に効果が高いのは、雨樋や谷樋まわりなど、凍結しやすく被害が出やすい部位です。
近年は、積雪を感知して自動でオンオフするタイプの融雪装置もあり、電力消費を抑えながら安全性を高めることが可能です。
落雪ゾーンを外構計画に反映する
屋根や軒先からの落雪に備えて、玄関前や人の通る場所を雪の落下ルートから外すように設計することも有効です。
舗装・花壇・柵などを活用して、自然に人の動線と落雪ラインを分離できる外構設計が望まれます。
屋根の形状や軒の設計、融雪設備の導入は、見た目以上に暮らしの安全性や快適性に直結する大切なポイントです。
特に雪国では、年間を通じた維持管理コストやリスクを減らすためにも、“雪との付き合い方”を前提にした設計が求められます。
市場動向&おすすめハウスメーカー比較
住宅の高性能化が進むなか、「高気密・高断熱」を標準または強く意識した商品を打ち出すハウスメーカーが増えています。特にここ数年は、断熱等級6〜7に対応した高性能住宅のラインナップが充実し、選択肢が広がってきました。
この章では、そんな最新の市場動向を踏まえ、各ハウスメーカーの断熱・気密性能に注目して比較できるよう整理しました。標準仕様で性能が高いメーカー、ハイエンド新商品、オプション対応まで、タイプ別に紹介します。
標準ダブル断熱対応メーカー
まずご紹介するのは、「ダブル断熱」を標準採用しているハウスメーカーです。断熱材を外側と内側の両方に配置することで、熱の出入りを二重に防ぎます。
一条工務店(グラン・スマート/i-smart)
一条工務店は「外内ダブル断熱構法」を標準化し、業界トップクラスの断熱性能を誇る住宅を展開しています。
フェノールフォームを使った断熱材は熱伝導率が非常に低く、断熱等級7にも対応可能。全棟で気密測定を実施し、C値0.5以下の高い気密性も実現しています。ロスガード90という第一種熱交換換気システムも標準搭載です。
スウェーデンハウス
木製三層ガラスサッシとウレタン断熱材を組み合わせた北欧仕様の住宅が特徴です。
気密性・断熱性に優れ、断熱等級6〜7に対応。気密測定は希望に応じて対応可能で、数値を確認しながら家づくりを進められます。
アイ工務店(ニーズ)
モデルによっては「ニーズ」など、ダブル断熱に対応した商品があります。
断熱等級6〜7を視野に入れた設計が可能で、全棟で気密測定を実施。断熱材のグレードや厚み、サッシ仕様の選択によって、性能を柔軟に調整できます。
新製品ハイエンドモデル
断熱性能を強化した新しい商品シリーズも、ここ数年で続々と登場しています。標準仕様で断熱等級6以上を実現し、設備面や快適性にも配慮されたモデルが多いのが特徴です。
桧家住宅「エリート・ワン」
現場吹付断熱材「アクアフォーム」を使用し、全棟で気密測定を実施。
C値は平均で0.4c㎡/㎡と高性能です。全館空調システム「Z空調」も標準搭載され、1年を通じて快適な室温を保てます。
クレバリーホーム「クレバース」
断熱等級7・G3相当をクリアする仕様で、高気密・高断熱・高遮熱の三拍子を兼ね備えた住宅です。
外壁にはデザイン性と耐久性を両立するタイル外壁を採用し、メンテナンス性にも優れています。
株式会社ヤマダホームズ「ラシオ」
2024年登場のハイエンドモデル。トリプルガラスサッシやダブル断熱を採用し、断熱等級6〜7に対応。
全館空調との親和性も高く、設計段階で空調の流れまで踏まえた快適性の高い住まいを提供しています。
オプション断熱対応メーカー
標準では断熱等級が高くないものの、オプション選択によって高断熱化が可能なハウスメーカーも多く存在します。地域や予算に合わせて性能調整したい方にはおすすめです。
ダイワハウス
木造住宅「xevoGranWood(ウルトラW断熱仕様)」では断熱等級7相当を実現可能。
外張り断熱+遮熱対策で夏場の快適性にも配慮されています。モデルごとの仕様差があるため、商品ごとの確認が重要です。
三井ホーム
独自の「プレミアム・モノコック構法」で耐震性と断熱性を両立。
2×6構造をベースに、「モクスサーモ」仕様では断熱等級7に対応。オプションで断熱材の性能や厚みを高めることができます。
ウィザースホーム
全棟で気密測定を構造・完成の2回実施。
断熱材やサッシ性能の選択肢も幅広く、断熱等級6〜7相当の性能にアップグレードが可能です。第一種換気との組み合わせにも対応し、設計の自由度も高めです。
比較ポイント早見表
最後に、各社の主要モデルを比較できる早見表を掲載します。断熱材の種類や等級、気密測定の実施有無、換気方式など、選定の参考にご活用ください。
| メーカー名 | 商品名 | 断熱方式 | 熱伝導率(参考値) | 等級(目安) | 気密測定 | 換気方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一条工務店 | i-smart | ダブル断熱 | 約0.020(フェノール) | 等級7 | 全棟実施 | 第1種(ロスガード90) |
| スウェーデンハウス | 標準仕様 | ダブル断熱 | 約0.025(ウレタン) | 等級6〜7 | 希望対応 | 第1種換気 |
| アイ工務店 | ニーズなど | 選択式 | 約0.030〜0.035 | 等級6〜7 | 全棟実施 | 第1種換気 |
| 桧家住宅 | エリート・ワン | 吹付断熱 | 約0.034(アクアフォーム) | 等級6〜7 | 全棟実施 | 全館空調(Z空調) |
| クレバリーホーム | クレバース | ダブル断熱 | 約0.035(高性能GW) | 等級6〜7 | 一部対応 | 第1種換気 |
| ヤマダホームズ | ラシオ | ダブル断熱 | 非公表 | 等級6〜7 | 一部対応 | 全館空調対応 |
| ダイワハウス | xevoGranWood | オプション | 約0.038(GW) | 等級5〜7 | 商品により異なる | 第1種/第3種併用 |
| 三井ホーム | モクスサーモ | オプション | 約0.038〜0.045 | 等級6〜7 | 一部対応 | 第3種換気 |
| ウィザースホーム | カスタム対応 | オプション | 約0.035〜0.040 | 等級6〜7 | 全棟2回実施 | 第1種換気 |
※ 等級・仕様は地域や商品により異なります。詳細は各メーカー公式サイトまたは担当者にてご確認ください。
高気密高断熱住宅を建てるうえで、「どこまでの性能を求めるか」「標準かオプションか」を知っておくことは非常に重要です。
単に“高性能”というだけでなく、自分たちの暮らし方や優先順位に合った構成を選ぶことが、後悔のない家づくりにつながります。

まずは情報収集が大事!
タウンライフなら、ハウスメーカーの資料を無料で一括請求できるから、効率よく家づくりを進められるよ♪
ハウスメーカーを悩んでいるあなたへ。
タウンライフ家づくりで資料請求してみませんか?
無料で間取りプラン・見積もり・資金計画書を作成してくれます。

- 家づくりのアンケートに回答(約3分)
- ハウスメーカーを選ぶ(1,100社提携)
- 待つだけ!間取り・見積もりが届く!
パーソナル快適性設計:CLO値を使う逆算術
高気密高断熱の住宅が普及したことで、冷暖房の効率は格段に高まりました。しかし、室温を「何度に設定すれば快適なのか?」という疑問は、意外と多くの方が抱えているのではないでしょうか。
このときに役立つのが、CLO(クロ)値という保温性能の指標です。CLO値は、衣服の厚さを数値化したもので、服装に応じた室温の目安を導き出すヒントになります。
断熱性能の高い住宅だからこそ、自分にとって最適な「体感温度」を設計に落とし込むことが重要になります。ここでは、CLO値を使って快適な室温を“逆算”する考え方をご紹介します。
CLO値とは?服装ごとの保温指標
CLO値とは、「どの程度の服装が、どれだけの保温力を持つか」を数値で表した指標です。
数値が高いほど厚着、低いほど薄着を意味します。
たとえば、Tシャツ+短パンのような軽装は約0.3、スーツは1.0、冬用の寝袋に入った状態ではCLO値が8.0程度になるとされます。
代表的なCLO値の目安は以下の通りです。
| 服装例 | CLO値の目安 |
|---|---|
| 裸 | 0.0 |
| Tシャツ+短パン | 0.3 |
| ワイシャツ+スラックス | 0.6 |
| スーツ(上下) | 1.0 |
| セーター+スーツ | 1.2〜1.3 |
| ダウンジャケット | 1.5〜2.0 |
| 冬用寝袋 | 8.0 |
CLO値はあくまで目安であり、活動量や個人差によって快適と感じる温度には幅があります。
また、CLO値は衣服の保温力を表す指標であり、湿度や風の影響を加味した「体感温度」とは異なる概念です。
季節・生活リズム別の理想CLOから室温設定を導く
快適な住まいをつくるうえで大切なのは、「何℃に設定すればいいか?」を機械的に決めるのではなく、「どんな格好で、どんな暮らしをしたいか」から逆算する視点です。
ここでは、季節や生活シーンに応じたCLO値をもとに、理想的な室温の考え方を具体的に見ていきます。
夏の日中(CLO値:0.3)
Tシャツ+短パンのような軽装で過ごしたい場合、快適な室温はおおよそ26〜28℃程度。
断熱性が高い家であれば、冷房を軽くかけるだけでこの温度帯を維持しやすく、電気代の節約にもつながります。
冬のリビング(CLO値:1.0〜1.2)
セーターやスーツなどを着て快適に過ごしたいなら、室温は20〜22℃が目安になります。
床暖房やパネルヒーターなどを併用すれば、全体を温めすぎずに快適性を高められます。
就寝時(CLO値:0.7以下)
夜間は布団や毛布でCLO値が補われるため、室温は16〜18℃でも快適に眠れるとされています。
ただし冷えすぎると睡眠の質が下がる場合もあるため、湿度や換気にも配慮が必要です。
このように、服装や活動量に応じて「快適な室温のゾーン」を逆算することで、冷暖房の設定がぐっと合理的になります。
たとえば、「一年中Tシャツで過ごしたい(CLO=0.3)」という前提であれば、室温は常に高めにキープする設計が必要になりますし、逆に「厚着してもいいから冷暖房は抑えたい」なら、室温を低めに保ちつつCLO値で調整するという考え方も成り立ちます。
このような設計思想は、快適性だけでなく、エネルギー効率や冷暖房コストの抑制にも直結します。
冷暖房・熱源プランニング
高気密高断熱住宅では、わずかな冷暖房エネルギーで家中を快適に保てるのが特徴です。しかしその一方で、熱源の選び方を間違えたり、導入タイミングを後回しにしたりすると、「せっかくの性能が活かされない」といったケースも少なくありません。
住宅の断熱・気密性能が高まった今、冷暖房計画に求められるのは“少ない設備で、どこまで快適さを実現できるか”という視点です。
ここでは、全館空調や各部屋エアコン、床暖房の組み合わせなど、代表的な熱源プランを比較しながら、設計段階で考えておくべきポイントを解説します。
全館空調のメリット・デメリット
全館空調とは、1台の空調ユニットで住宅全体の温度・湿度を一定に保つ仕組みです。
家のどこにいても温度差がなく、体にも負担が少ないのが最大のメリットです。
主なメリット
とくに子育て中の家庭では、「暑い部屋に子どもが勝手に移動してしまう」「ドアを開けっ放しにしてエアコンの効きが悪くなる」といったストレスが減るのも利点のひとつです。
デメリット
全館空調は、高性能住宅との相性が良い一方で、コスト面と施工自由度に課題が残ります。導入を検討する際は、「自分たちの暮らしに必要か」を冷静に見極めておくことが大切です。
各部屋エアコン+床暖房の組み合わせ
コストや自由度を重視するなら、各部屋に個別エアコンを設置し、リビングなどに床暖房を組み合わせるスタイルも一般的です。
このプランでは、以下のような構成がよく見られます。
- リビング:床暖房+エアコン
- 寝室・子ども部屋:個別エアコン
- 脱衣所・浴室:ヒーターや暖房パネルなどの補助熱源
エアコン+床暖房の組み合わせは、初期費用を抑えつつ冷暖房の効率を確保できる点が魅力です。
ただし、使用者の温度管理に任される部分が大きいため、部屋によって温度差が出やすい点には注意が必要です。
とくに高断熱住宅の場合、ひとつの部屋の温度が他の部屋にも伝わりやすいため、「リビングのドアが開いている」「寝室の冷房が弱すぎる」といったちょっとしたことが、全体の快適性に影響を与えるケースもあります。
後付け機器の気密性低下リスク
高気密住宅においては、「後からエアコンを追加する」という行為が思わぬリスクを生むこともあります。
たとえば、「子ども部屋にはエアコンは不要だと思っていたが、実際に夏が暑くて追加した」というケースでは、壁に新たな配管穴を開ける必要が出てきます。このとき、気密処理が破れたり、断熱層に欠損が生じたりすることで、性能が大きく低下してしまう可能性があります。
主なリスクには以下のようなものがあります。
これらを避けるためにも、「熱源は後から考えよう」とせず、最初から“すべての部屋に快適な環境を届ける”という前提でプランニングすることが重要です。
初期導入すべき熱源戦略
断熱性能が高い家では、「少ない熱源で済む」と考える方も多いかもしれません。たしかにそれは事実ですが、忘れてはならないのは「熱源がなければ、室温は変わらない」という根本です。
よくある失敗例として、「高断熱だからエアコン1台でいけると思った」「リビングだけ空調しておけば何とかなる」という思い込みがあります。しかし、実際に暮らしてみると、「2階が暑くて寝られない」「冬の脱衣所が寒すぎる」という声も多く聞かれます。
こうした失敗を防ぐためには、初期の熱源戦略が不可欠です。
初期設計で押さえておきたいポイント
高性能な断熱・気密性能があっても、熱源の配置が適切でなければ快適性は実現できません。「なるべく少ない機器で快適に暮らす」ためにも、最初の段階で“どこに、どんな熱源を設けるか”を明確にしておくことが大切です。
災害・メンテナンスコストを見据えた長期視点
高気密高断熱住宅は、建てた瞬間が完成ではなく、住み続けてからの維持と管理が大きなテーマになります。いくら性能が高くても、フィルターやパッキン、配管といった小さな部材の劣化や放置が、大きな損傷や快適性の低下を招くことも。
さらに、近年増えている豪雨・台風・地震といった自然災害への備えや、将来にわたる保険・修繕コストも無視できません。
この章では、住んでからの安心と持続的な性能維持に必要な視点を、メンテナンス・保険・コスト比較の3つの観点から整理します。
換気フィルターや結露チェックなどの定期メンテナンス要点
高性能な住宅は「放っておいても快適」ではありません。快適な状態を長く保つための定期的な点検・掃除が欠かせません。
とくに注意したいのは以下の項目です。
換気システムのフィルター清掃
第一種換気システムを導入している住宅では、給気・排気ともにフィルターが装着されています。
フィルターの目詰まりは、空気の流れを妨げて換気効率を落とすだけでなく、熱交換効率の低下やアレルゲンの蓄積にもつながります。
【目安】
●屋外側フィルター:2~3ヶ月に1回
●室内側フィルター:半年~1年に1回
結露・水漏れのチェック
壁内・窓まわり・床下の結露は、断熱施工の隙や空調運用ミスが原因で発生することがあります。放置すればカビや木材腐食を引き起こすため、年に1回は点検・記録を取っておくのが理想です。
気密パッキンやコーキングの劣化
高気密住宅では、ドア・窓周り・配管まわりなどに用いられる気密パッキンや防水コーキングの劣化が進むと、C値(隙間面積)が悪化し、断熱性能にも影響します。
5年・10年単位でのチェックと、必要に応じた補修が推奨されます。
火災保険・水害保険との連携ポイント
気候変動の影響で、水害や大型台風のリスクが年々高まっています。特に近年では「100年に1度」の豪雨が、実際には20年や30年で複数回起きているという報告もあり、保険の見直しが重要になっています。
火災保険の補償範囲
火災保険の中には「風災・雹災・雪災」が含まれるケースが多く、台風で屋根や窓に被害が出たときの修理費は保険でカバーできる場合があります。ただし免責額や支払い条件に差があるため、契約前に補償内容を細かく確認しましょう。
水害保険(地震保険とのセット型も)
洪水・内水氾濫などに備えるには「水災補償」が必要です。ハザードマップで想定浸水深がある地域では、補償の有無が住宅価値や資産保全に大きく影響します。
【連携すべきポイント】
初期コスト vs ライフサイクルコスト比較
断熱等級7・C値0.3・全館空調といった仕様は、確かに初期費用が高くなります。しかし、光熱費・冷暖房効率・メンテナンス頻度まで含めた「30年スパン」で見ると、トータルではプラスになるケースも多くあります。
【一般的な比較例】
| 項目 | 低断熱住宅 | 高断熱・高気密住宅 |
|---|---|---|
| 初期建築コスト | △(安い) | △〜×(高い) |
| 冷暖房費(月) | ×(年間20〜30万) | ◎(年間5〜10万) |
| 結露・カビリスク | ×(窓や壁に発生しやすい) | ◎(温度差が小さく、湿度安定) |
| 設備の更新頻度 | △(熱源劣化しやすい) | ○(空調効率が高く、負荷が少ない) |
| 総支出(30年間) | 約2,500万円以上 | 約2,300〜2,400万円程度 |
さらに近年では、断熱性能の高さが「住宅資産価値の維持」にもつながる傾向があります。将来の売却・相続を考えたときにも、長期的な経済性でメリットが出てくる可能性があります。
地域・ライフスタイル別の選び方ガイド
高気密高断熱住宅の性能は全国どこでも通用しますが、「どこに住むか」「どう暮らすか」によって、必要な対策や設計方針には違いがあります。
北海道と沖縄では気候が大きく異なるため、適した断熱材や気密の基準も変わります。
また、家族構成や働き方、予算などによっても、重視すべきポイントが異なります。
この章では、地域特性・予算・ライフスタイルの3つの視点から、自分に合った住宅性能の選び方を整理していきます。
北海道〜沖縄:断熱等級・断熱材選びの地域特性
断熱等級は、国が定める「地域区分」によって求められる基準が異なります。
寒冷地ほど高い等級が必要で、温暖地ほど緩やかになるのが特徴です。
| 地域 | 想定される等級目安 | 特徴・注意点 |
|---|---|---|
| 北海道(1・2地域) | 等級6〜7 | 暖房負荷が大きいため、厚みある断熱と気密性が重要 |
| 東北〜関東内陸(3・4地域) | 等級6〜7 | 寒暖差が大きく、断熱・遮熱の両立が必要 |
| 東京・大阪周辺(5地域) | 等級5〜6 | 夏の暑さ対策として日射遮蔽・通風設計が鍵に |
| 九州・四国沿岸(6地域) | 等級5程度 | 冬よりも夏の蒸し暑さ対策を中心に考える |
| 沖縄(7地域) | 等級4〜5 | 高温多湿への通風・遮熱・結露対策を重視 |
また、地域に応じて断熱材の選定にも違いがあります。
※補足:現在の断熱等級はすべて「冬の寒さ」を前提に評価されています。そのため、等級が高くても“夏に快適”とは限らない点に注意が必要です。夏の快適性を確保するには、日射遮蔽や通風設計など、断熱以外の工夫が重要になります。
予算帯別の目安:コスパ重視 vs 快適性MAX
性能をどこまで求めるかは、当然ながら予算によっても変わります。ここでは、予算帯ごとの想定スペックと最適な方針を整理しました。
【予算3000万円未満】
- ペアガラス・高性能グラスウール中心
- C値は1.0前後、UA値0.6〜0.7を狙う
- 換気は第3種が基本(希望で第1種も可)
- 気密測定はオプション対応
必要最低限の断熱・気密性を確保しながら、費用対効果を重視した設計がメインになります。
【予算3000〜4000万円】
- 樹脂サッシ+トリプルガラスの採用が可能
- 吹付断熱やダブル断熱など外皮強化
- 気密測定を標準実施、等級6〜7が現実的に
- 熱交換型換気システムも導入可能
初期投資と快適性のバランスを取りつつ、暮らしやすさを実感しやすい帯域です。
【予算4000万円以上】
- ダブル断熱+高性能サッシを標準化
- 全館空調と第一種換気(熱交換率85%以上)をフル活用
- 結露・温度ムラ・空気の質までトータルに設計
“すべての部屋が快適”という性能重視の家づくりが可能になります。
家族構成・生活リズムに応じたカスタマイズ
高性能住宅の強みを最大限に活かすには、「誰が、どんな生活をするか」を軸に設計を考えることが大切です。
子育て世帯
- 全館空調や床暖房で温度差のない家に
- 子ども部屋や廊下にエアコン不要でも快適さを維持
- 「ドア閉めて!」と言わなくてよくなるストレスフリー設計
共働き・在宅勤務
- 書斎やワークスペースの個別空調を設ける
- 昼間のみ使用する部屋へのスポット冷暖房
- 気密性の高さを活かした静音性や空気の質もメリット
シニア・2世帯住宅
- 廊下や脱衣所も暖かく保てることでヒートショック防止に
- 換気フィルターの手入れや空調制御が簡単な仕様を選ぶ
- 長く住む視点でのメンテナンス性や耐久性も重視
また、見落とされがちなのが「敷地の特性を読む」設計の力です。
南中高度、太陽の動き、風の流れなどを読み取って窓の位置・軒の出を工夫すれば、冷暖房に頼りすぎずとも快適な住まいが実現できます。
こうした知識と工夫は、設計士やハウスメーカーによって提案力に差が出やすいポイントでもあるため、“自分たちの暮らし方を理解してくれる担当者”を選ぶことが成功のカギになります。

まずは情報収集が大事!
タウンライフなら、ハウスメーカーの資料を無料で一括請求できるから、効率よく家づくりを進められるよ♪
ハウスメーカーを悩んでいるあなたへ。
タウンライフ家づくりで資料請求してみませんか?
無料で間取りプラン・見積もり・資金計画書を作成してくれます。

- 家づくりのアンケートに回答(約3分)
- ハウスメーカーを選ぶ(1,100社提携)
- 待つだけ!間取り・見積もりが届く!
12. 設計・シミュレーションツール活用術
高気密高断熱住宅の快適性を最大限に活かすためには、建物そのものの性能だけでなく、敷地条件や太陽・風の動きといった「自然環境の読み取り」が非常に重要です。
どの時間帯にどこから日差しが入るか。隣家の影がどのように落ちるか。風はどの向きから吹き抜けるか――こうした要素を、建てる前から“見える化”できるのが、シミュレーションツールの役割です。
ここでは、日射シミュレーションアプリの活用法から、太陽高度の見極め方、敷地選びで見るべきチェックポイントまで、実践的に解説していきます。
サンシーカー/サンウェイヤーでの日射シミュレーション
「サンシーカー(Sun Seeker)」や「サンウェイヤー(Sun Surveyor)」といったスマホアプリは、敷地に立ったまま1年分の太陽の動きを視覚的に確認できるツールです。
これらのアプリでは、
といった点で、設計の根拠づけに大いに役立ちます。
特に、南向きに大開口を設けたいと考えている場合でも、実際には「冬場は隣家の影で日が入らない」ケースもあり得ます。
このような敷地条件を事前に把握しておくことで、断熱・日射取得・遮蔽のバランスを最適化した設計が可能になります。
真夏(7〜8月)・真冬(1月21日)の太陽高度チェック
太陽の高さ(南中高度)は、季節によって大きく変化します。
その変化に合わせて軒の出や窓の配置を工夫することで、「夏は日射を遮り、冬は取り込む」といった設計が実現できます。
代表的な太陽高度(東京基準)
| 時期 | 南中高度 | 特徴・設計上の注意点 |
|---|---|---|
| 夏至(6月21日前後) | 約78〜80° | 真上に近く、深い軒でも直射が入りやすい |
| 盛夏(7〜8月) | 約70〜75° | 遮蔽の主戦場。軒や外構による日射カットが重要 |
| 冬至(12月21日前後) | 約31〜33° | 太陽が低く、部屋の奥まで日が入る。取得を活かしたい |
| 最寒日(1月21日) | 同上 | 気温は冬至よりさらに下がるため、保温重視の設計を意識 |
また、窓の高さの1/3ほど軒を出すと、夏は日差しを遮り、冬はしっかり差し込む設計になります。
この点で有利なのが「平屋」です。
平屋は屋根が窓のすぐ上にあるため、軒をしっかり出しやすく、日射のコントロールが非常にしやすくなります。
一方、総2階建ての住宅では1階の軒が浅くなりがちです。その場合はパーゴラ(屋根付きフレーム)や外構の庇、可動式のタープなどで柔軟に日射調整する工夫が有効です。
敷地選びのチェックリスト
建物の性能がいかに優れていても、「土地との相性」を無視してはその力を発揮できません。
設計に入る前の段階から、太陽と風をどう活かせるかを意識した敷地選びを行うことが、後悔のない家づくりにつながります。
敷地選びの主なチェック項目
| チェックポイント | 解説 |
|---|---|
| 南側の開け具合 | 隣家や塀の影が、冬の日射を遮らないか。特に午前〜午後2時ごろの日照に注目 |
| 周辺建物の高さ | 将来的に新築や増築の可能性がある場所かどうかも含めて確認 |
| 北風の通り方 | 北側に樹木や外構で風除けをつくれると、冬の冷気を和らげられる |
| 通風の抜け道 | 夏の夜間通風が活かせる方角かどうか(東西窓や吹き抜けも考慮) |
| ハザードマップ | 水害・地盤沈下・液状化リスクがないか事前確認。建築前に必須 |
| 敷地の高低差 | 浸水リスクを防ぐためにかさ上げの必要があるかどうかも検討対象に |
また、どうしても影の影響を受けやすい敷地や、通風が取りづらい土地の場合には、グリーンカーテン・タープ・パーゴラ・落葉樹などの“外構による自然調整”が非常に有効です。
これらを想定したうえでの設計に取り組むことで、敷地が持つポテンシャルを最大限に引き出すことができます。
高気密高断熱の家づくり 総まとめ
この記事では、猛暑・水害・雪害が増えるこれからの時代にふさわしい「高気密高断熱の住まい」について、基本の考え方から設計・設備・土地選び・費用対策まで、幅広い観点で解説してきました。
最後に、家づくりで失敗しないために押さえておきたいポイントを振り返ってみましょう。
地球温暖化は“住まいの性能”を変えつつある!
気温上昇・熱帯夜の増加・ゲリラ豪雨の頻発により、冬だけでなく「夏への断熱対策」や「水害対応」も住まいに必須の視点になっています。
断熱・気密・熱源は三位一体で考えるのが基本!
フェノールフォームやグラスウールなど断熱材の性能だけでなく、**隙間を減らす施工技術(C値)**と、冷暖房設備の配置がセットで機能してはじめて快適性が成立します。
日射・風・敷地の特徴を設計に活かす!
アプリを使った太陽高度のシミュレーションや、通風・軒出し設計により、エネルギー効率を上げながら自然と共存する住まいづくりが可能になります。
地域・予算・暮らし方で“ちょうどいい”仕様を選ぶ!
北海道と沖縄では求められる性能が異なるように、自分のエリアや生活スタイルに合わせた選択が快適性・コスト・将来性すべてに直結します。
建てたあとも見据えて、保険やメンテナンス計画を立てよう!
災害保険との連携や、フィルター掃除・気密補修などの定期点検、ライフサイクルコストでの比較が、長く快適に暮らす鍵になります。
これらを押さえておけば、「断熱等級が高ければOK」といった思い込みにとらわれず、暮らしに合った本当に快適な家づくりができるはずです。
設計の段階で迷ったときは、
といった視点で“質問力”を持って打ち合わせに臨んでみてください。
これらを押さえておけば、性能に過信せず、快適性とコストのバランスが取れた家づくりができるはずです。
ぜひ今回の情報を参考にして、「後悔しない、暮らしにフィットする住まい」をじっくり検討してみてください

まずは情報収集が大事!
タウンライフなら、ハウスメーカーの資料を無料で一括請求できるから、効率よく家づくりを進められるよ♪
ハウスメーカーを悩んでいるあなたへ。
タウンライフ家づくりで資料請求してみませんか?
無料で間取りプラン・見積もり・資金計画書を作成してくれます。

- 家づくりのアンケートに回答(約3分)
- ハウスメーカーを選ぶ(1,100社提携)
- 待つだけ!間取り・見積もりが届く!